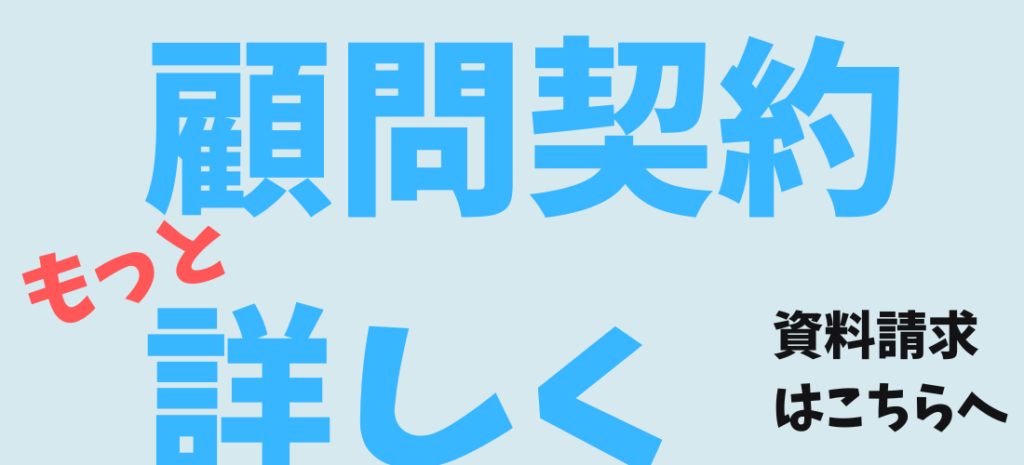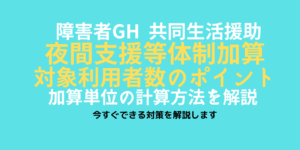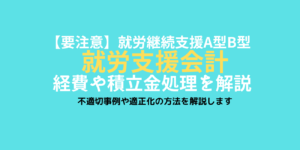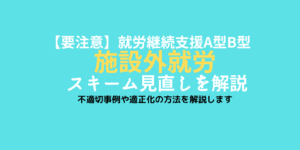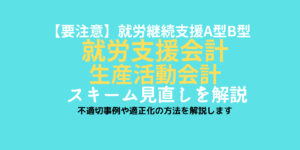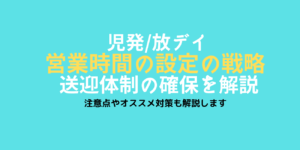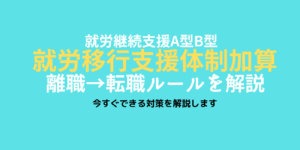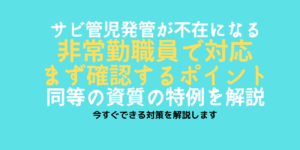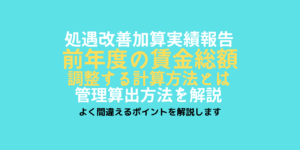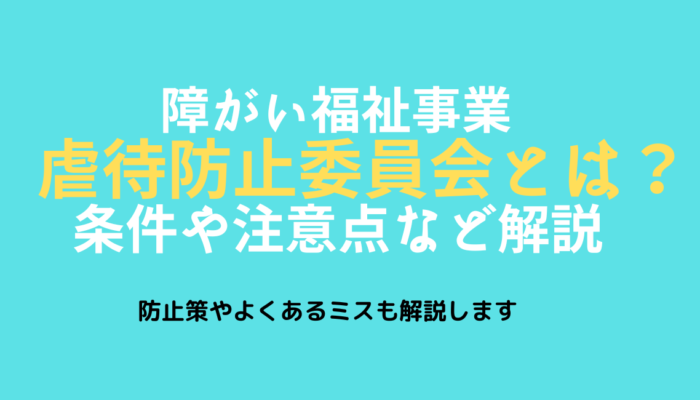
★★★記事執筆者のご紹介★★★
この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております。多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました。
戸根行政書士事務所のプロフィールはこちらですので、よろしければ弊社の支援方針や独自の強みなどご覧ください。

令和4年度から障害福祉事業所で「虐待防止委員会」の設置が義務化されたと知らず、実地指導で指摘されて驚きました。ただ「虐待防止委員会」で何をしたらいいのかさっぱりわかりません。
そこで「虐待防止委員会」の設置から検討内容まで詳しく教えていただけますでしょうか?
令和4年度から虐待防止委員会の設置が義務化され運営規程に必ず記さないといけません。
義務化への変更を知らず、運営規程の変更や必要書類の整備をしていないと実地指導の時に自治体とトラブルになる可能性があります。
この記事では事業者様の理解の一助になるように以下の内容を説明いたします。
- 「虐待防止委員会」の運営規程の書き方がわかります
- 「虐待防止委員会」の検討内容のポイントがわかります
- 「虐待防止のための指針」の作成手順がわかります
目次
虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説

令和4年度から障害福祉事業で「虐待防止委員会」の設置が義務化され、それに応じて運営規程や委員会記録を作成する必要が出てきました。
<「虐待防止委員会」の役割>
・虐待防止のための計画づくり(※研修、指針の作成、労働環境の確認)
・虐待防止のチェックとモニタリング
・虐待発生後の検証と再発防止の検討
「虐待防止委員会」は事業所の安全のための様々な役割を担っているのですね。
そこで「虐待防止委員会」を適正に運営したいと思うのですが、どのような点に注意すれば実地指導でも問題なく運営できるでしょうか?
ポイントは「虐待防止委員会」の構成員の責務や役割分担を明確にし、専任の虐待防止担当者を設置することです。
「虐待防止委員会」の組織体制を作って運営規程や記録書類に反映いたしましょう。
以下では具体的な例を示しつつ「虐待防止委員会」についてわかりやすく説明いたします。
運営規程に位置付ける

障害福祉事業で「虐待防止委員会」を設置する場合は、運営規程で虐待防止委員会の設置の文言を必ず加えて、重要事項説明書と整合性を取りましょう。
<運営規程の記載例>
第○条
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる通り必要な措置を講じます。
・虐待の防止に関する責任者の選定を行います。
・成年後見制度の利用支援を行います。
・苦情解決体制の整備を行います。
・従業者の虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施(研修方法や研修計画)を定期的に行い、研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。
・個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。
・従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整備するほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
・虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底いたします。
令和3年度以前に運営規程を作成された障害福祉事業所様は、条項の文言が「〜講じるよう努めます」と努力義務になっているか確認し修正いたしましょう。
自治体によっては虐待防止委員会の開催回数を指定しているところもあり、その場合は委員会の回数を運営規程に記す必要があります。
重要事項説明書との記載の齟齬にも気をつけながら運営規程を取りまとめましょう。
虐待防止委員会で何をするの

障害福祉事業の事業所で設置した虐待防止委員会では、事業所の虐待防止に関する対策を話し合い、その委員会記録を整備して残しておきましょう。
<虐待防止委員会で話し合う内容>
・虐待発生時の報告書の様式を作る
・様式に則った報告書を集計し分析する
・虐待の再発防止策を検討する
・虐待が発生しやすい労働環境かどうか検討する
・虐待の事例と分析結果を従業者に周知徹底する
※虐待防止委員会の開催記録の注意点
日時/参加者/検討内容/議事録証明者/参加者のアンケートを記すようにいたしましょう。
もし虐待にあたる事案がなければ、基本的には虐待が発生しやすい労働環境かどうかのチェックを行うことになります。
事業所に応じて従業員の言葉遣いやボディタッチの有無、従業者と利用者の配置などを検討し虐待の可能性を未然に防いでください。
「虐待防止のための指針」を作成する
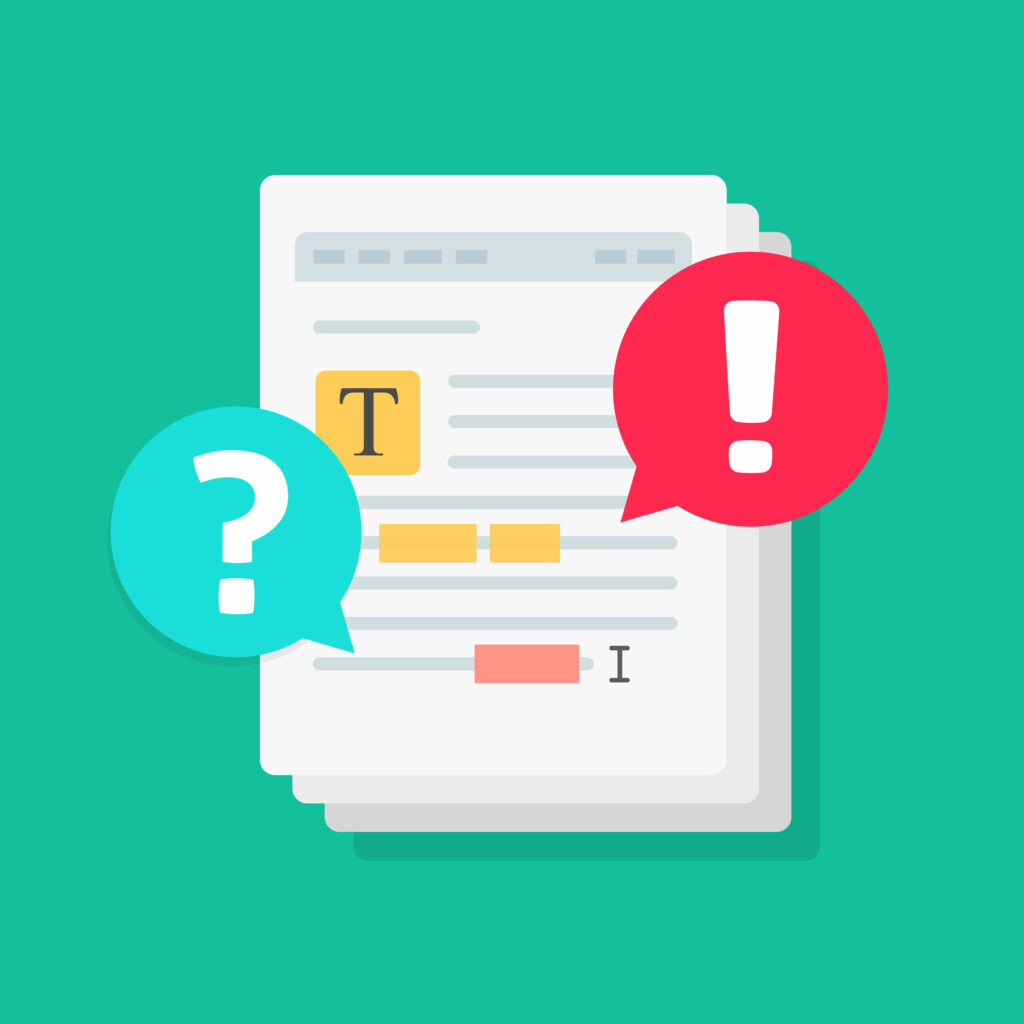
「虐待防止委員会」を設置した事業者は、委員会の開催規定だけでなく「虐待防止のための指針」も作成しておくことを忘れないようにいたしましょう。
<「虐待防止のための指針」の内容>
・事業所の虐待防止に関する基本的な考え方
・虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
・虐待防止のための職員研修に関する基本方針
・施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
・虐待発生時の対応に関する基本方針
・利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
・その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
意外と「虐待防止のための指針」を作成しておらず実地指導の時に指摘されるケースが目立ちます。
事業所ごとの基本方針が明確であれば、虐待防止委員会もスムーズに運営できて利用者さんも安心でしょう。
よくある質問

「虐待防止委員会」は事業所単位で設置する必要がありますか?
答:必ずしも事業所単位で設置する必要がありません。法人単位で設置も可能です。
「虐待防止委員会」の参加人数に決まりはありますか?
答:参加人数に決まりはありません。ただ事業所の管理者や虐待防止担当者の参加は必須です。
「虐待防止委員会」の開催頻度に決まりはありますか?
答:少なくとも年に1回開催する必要があります。
「虐待防止委員会」と「身体拘束等適正化検討委員会」は共催できますか?
答:一体的に設置運営することが可能です。
まとめ
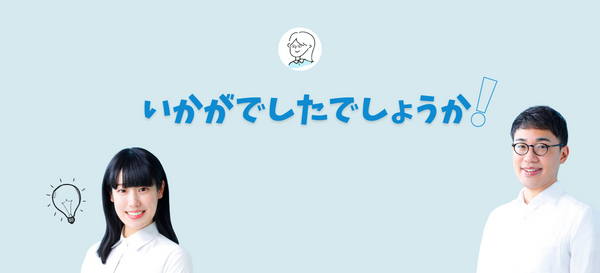
障害福祉事業で設定が義務化された「虐待防止委員会」について詳しく分かりました。ありがとうございます。
運営規程を変更するとともに、年に1回虐待防止委員会を開催して記録を残していきたいと思います。
「虐待防止委員会」の開催は、事業所内でのトラブルをなくし安定した運営を行うために必要な組織です。
何度ごとに委員会を必ず開催し、虐待に類する事案があっても迅速に対応して、安心して継続的に事業所を利用してもらえるようにいたしましょう。特にご家族に不安を覚える方がいらっしゃるので十分な説明をすることが安全です。
「虐待委員会」等の虐待防止と人権向上の仕組みを作ることは事業所の経営の安定につながるので、ぜひ要件をしっかり守って組織を作ってください。
戸根行政書士事務所からのお知らせ
<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ
・【まとめ】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から注意点まで解説
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
<減算について>
・【基本】人員欠如の減算とは?計算方法や注意点も解説
・【詳解】人員欠如の減算:基準や緊急対応・防止策をご説明
・【詳解】サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算とは?
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題点と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明