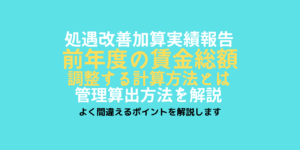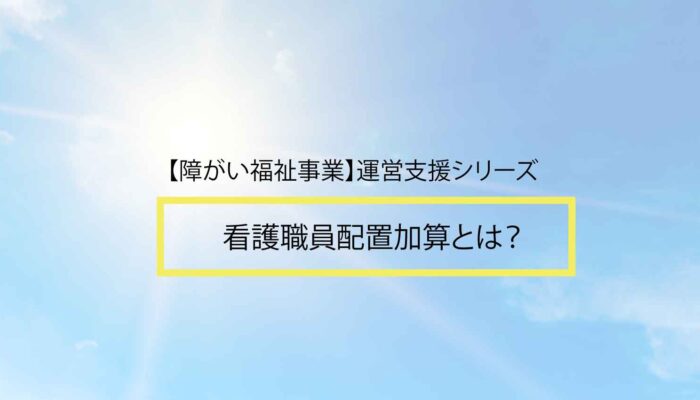
共同生活援助(グループホーム)における「看護職員配置加算」とは何でしょうか?
近年はグループホームの中でも、重度の方や高齢者の受け入れに力を入れる事業所が評価される傾向があります。
特に重度の方を受け入れているグループホームは利用者さまに健康上のトラブルが起こる可能性もあります。
そこで医療面からケアできるスタッフを配置しておくと安心です。
行政としてはそのような看護職員を配置する事業所を評価し、加算を設定しています。
この記事を読むと、グループホームの事業所さまが看護職員を配置し活用して、重度の方を支援していく体制づくりのノウハウが分かります
これまで多くのグループホームの事業所さまと関わってきて、「重度の方を受け入れる時に医療面で不安がある」というお声を度々伺いました。
しかし看護職員は病院で働いているイメージがあり、どのようにグループホームで配置して働いてもらうかイメージがつきません。
そこで本日は「看護職員配置加算」の説明を通して、介護職員を配置するグループホームのあり方を解説したいと思います。
目次
看護職員配置加算とは?
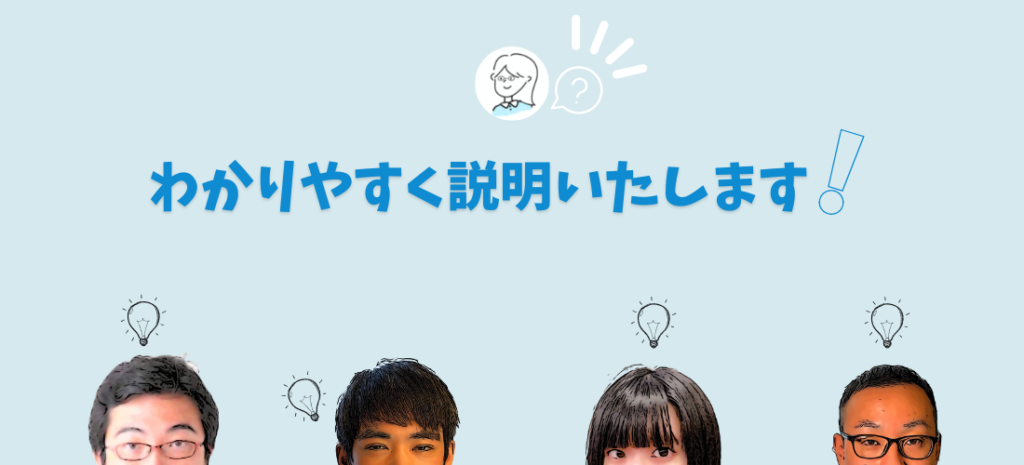
共同生活援助ことグループホームでは、必ずしも看護職員を配置する必要はありません。
けれども重度の方を受け入れる際には、医療面でのケアが心配になります。
そこでグループホームでも看護職員を配置すれば、次の点で支援が充実します。
- 看護サービスの提供
- 専門的な支援計画の方針の策定
- 医療機関との連携強化
このように支援の充実に貢献する看護職員の配置を促進するため「看護職員配置加算」があります。
では、
「看護職員配置加算」の取得要件や届出はどのようにすればいいの?
という点が気になりますよね。
そこで先ずは「看護職員配置加算」について記したいと思います。
取得要件

グループホームにおける「看護職員配置加算」の取得は、基準の人員(=世話人の必要な常勤換算数)に加えて「看護職員」を常勤換算で1.0以上追加で配置し、適切に健康管理等をすることで可能になります。
※「看護職員」 = 保健師/看護師/准看護師
<「看護職員」を常勤1以上確保するポイント>
基準の人員(=世話人の必要な常勤換算数)に加えて加配する必要がありますので、基準人員の中に看護職員が常勤1以上含まれていても、加算の算定条件にはなりません。
<複数の共同生活住居の配置の注意点>
利用者全体(=前年度の平均利用者数)÷20以上の看護師を常勤換算で配置する
ケース1
- 住居数:1/利用者数3
- 看護職員
→常勤換算1.0で配置
ケース2
- 住居数:4/利用者数25
- 看護職員
→常勤換算1.25で配置(員数は1以上)
<看護職員の配置による利用者への体調管理等のポイント>
・日常的な健康管理を行う
・医療ニーズが必要な利用者への看護の提供をする
・医療機関との連絡調整と受診等の支援を行う
・看護職員による常時の連絡体制を作る
・重度化した場合の指針の作成と家族への説明をする
※注意点:医療連携体制加算は算定できません
「看護職員配置加算」を算定している事業所は、医療連携体制加算(※(IV)は除きます)を算定することができません。
よくある質問
(よくある質問1)看護職員は非常勤でも大丈夫ですか?
答:非常勤でも大丈夫です。
(よくある質問2)看護職員に准看護師は含まれますか?
答:含まれます。
届出

「看護職員配置加算」を算定するには、管轄の役所に届出をしなければいけません。
届出書に記す項目は基本的に次の通りです。
・看護職員の配置状況
・利用者の数
・必要な看護職員の配置数
届出の項目はシンプルですが、監査指導などを踏まえて
- 雇用契約
- 労働条件通知書
- シフト表
- 出勤管理表
などを整備しておきましょう。
加算単位
看護職員を配置することで得られる加算の単位は、
・70単位/1日
です。
地域単価が仮に10 円とする700円になります。
そうすると利用者が5人のグループホームでは1日に3500円が加算額になります。
看護職員配置加算の活用事例とは?
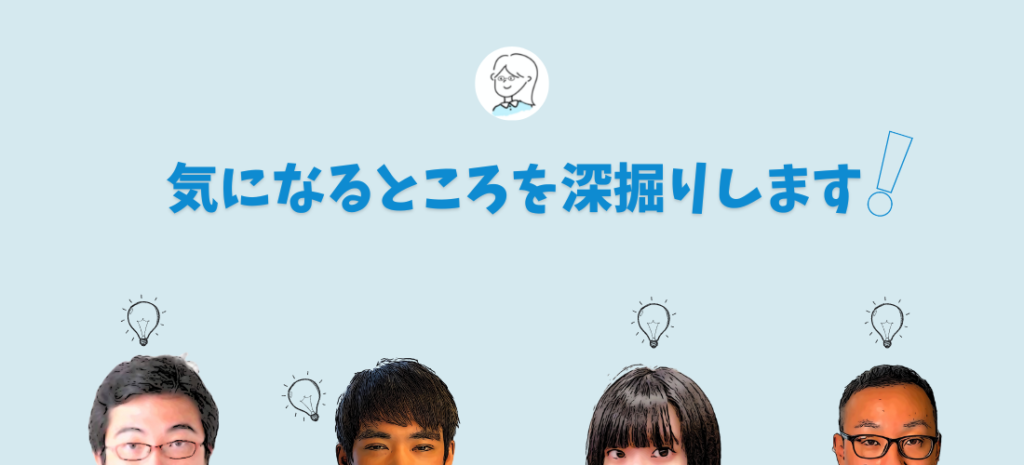
これまで「看護職員配置加算」の要件や届出条件についてお話しいたしました。
看護職員を配置することは常勤換算のルールを守っていれば難しくないことがわかります。
けれども1日あたり約700円であり、加算額=人件費という計算ができないことがわかります。
そこで気になるのは、
このような「看護職員配置加算」を活用してどのような組織を作っていけばいいのか?
という点ではないでしょうか。
続いて共同生活援助、つまりグループホームでどのように看護職員を配置して活用していけば良いのについて説明いたします。
地元医療機関からのリクルート

「看護職員配置加算」のオススメの活用事例は、
看護職員を地元の医療機関からリクルートすること
です。
現存のスタッフを看護職員になるよう訓練することは大変で現実的ではないでしょう。
そこで看護職員を採用し、既存のグループホームの人員配置である、
- 世話人
- 生活支援員
- 夜間支援員
のいずれかで働いてもらうのが一般的です。
もちろん医療的配慮を考慮した支援が特徴ですが、他にも重要なのは、
・地域の医療機関との連携
です。
医療的ケアを必要とする重度の方は既に地域でかかりつけの病院があり、そこに支援記録が蓄積されているはずです。
そこで看護職員の中でも地域の医療機関出身であると、医療機関とグループホームの連携が一層スムーズになるでしょう。
地域の医療機関出身の看護職員は福祉ネットワークにも馴染みがあり、共同生活援助の利用者の症状に合わせて的確な相談場所を探してくれるはずです。
地域の医療機関からの派遣
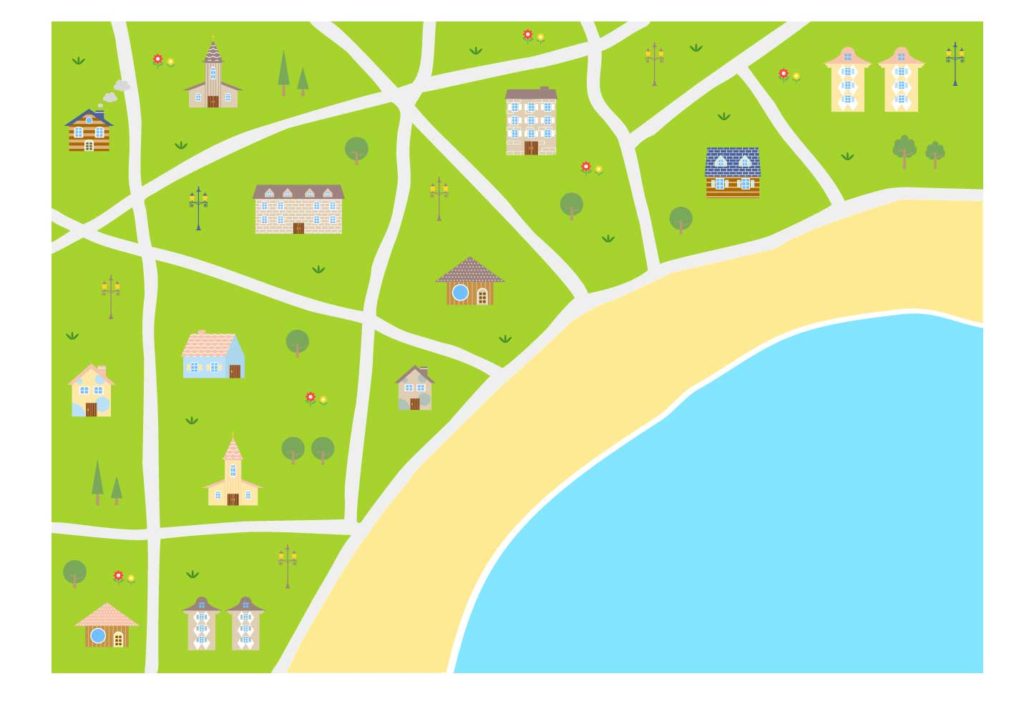
重度の方を支援する上で地域医療機関との連携を重視するなら、看護職員を採用するだけでなく、
・地域の医療機関がグループホームを設立し、看護職員を派遣する
ことも有効です。
「看護職員配置加算」のための看護職員は外部から引き入れてくる必要があります。
ただ病院に入院している患者が地域移行するために、そのような医療ケアを要する方のためのグループホームが求められることもあるでしょう。
そうすると
医療法人自体がグループホームを設立し、自前の看護職員を派遣すること
が有効です。
重度の利用者への医療情報は病院にいる時から蓄積しており、グループホームに移行しても継続的な支援が見込めるはずです。
まとめ
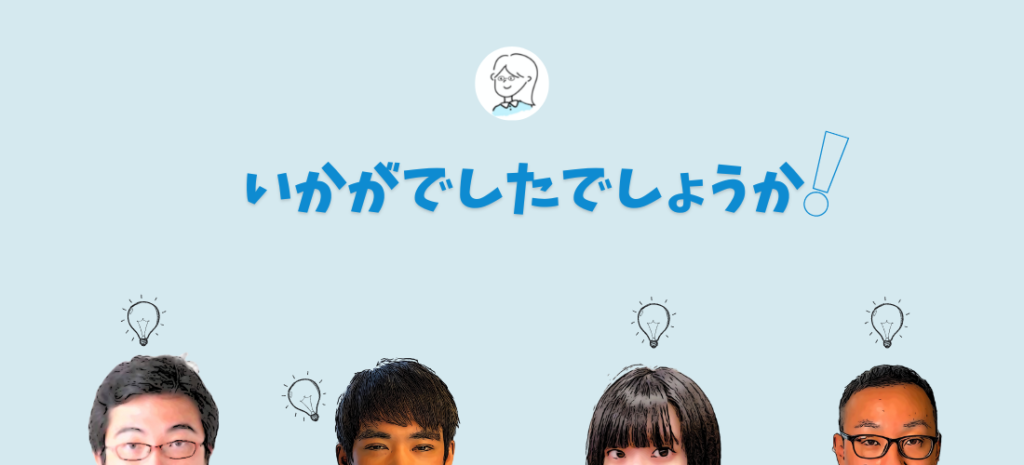
重度の障害の方をグループホームで受け入れるには看護師などの配置を考えないといけません。
そうすると「看護職員配置加算」を取得することができますが、それで人件費は補えません。
そこで医療連携の促進のために地域の看護師に在籍してもらったり。医療法人などがグループホームも開業する場合にこの加算を活用することが有効です。
戸根行政書士事務所からのお知らせ
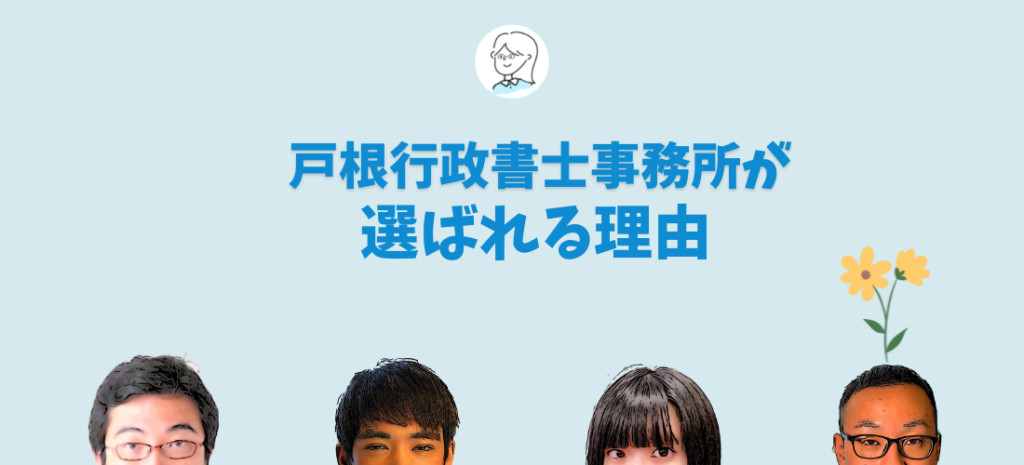
<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ
・【まとめ】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から注意点まで解説
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
<減算について>
・【基本】人員欠如の減算とは?計算方法や注意点も解説
・【詳解】人員欠如の減算:基準や緊急対応・防止策をご説明
・【詳解】サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算とは?
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題点と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
<夜間支援の加算等>
・【基本】夜勤職員加配加算の要件とは?注意点やオススメ活用事例あり
・【基本】重度障害者支援加算とは?注意点や活用事例あり
・【最新版】夜間支援等体制加算とは?注意点・活用事例も紹介
・【注意】グループホームの夜間支援体制のスタッフ配置:注意点も解説
・【要点】「夜間支援等体制加算」の利用者数の計算とは?
<医療/入院関係の加算等>
・【基本】看護職員配置加算とは?要件・活用事例も解説
・【基本】医療連携体制加算とは?要件・注意点・おすすめ活用も解説
・【注意点】個人単位で居宅介護は利用できるの?要件や注意点を説明
・【基本】強度行動障害者体験利用加算とは?取得条件や活用事例も紹介
・【基本】長期入院時支援特別加算とは?基準や注意点を解説
・【基本】入院時支援特別加算とは?基準や注意点を解説
・【基本】医療的ケア対応支援加算とは?加算条件や活用方法も解説
・【基本】「帰宅時支援加算」とは?取得条件や間違えやすいポイントを解説
・【基本】「長期帰宅時支援加算」とは?取得条件や間違えやすい点を解説
・【基本】「地域生活移行個別支援特別加算」とは?取得条件や活用法を解説
<利用者さんとのトラブルを避ける対策>
・【まず知りたい】グループホーム運営は何が難しいの?
・【注意】グループホーム利用者との金銭トラブルについて
・【質問】「通院時も付き合って欲しい」と言われたら?通院支援の対策を解説
・【注意】グループホームの費用設定はどのように?利用者負担も解説
・【基本】グループホーム体験利用の注意点とは?利用者負担の設定に留意
<実地指導のトラブルにならないための対策>
・【まず知りたい】実地指導とは?チェックリストもお教えします
・【直前対策】実地指導を受ける時の対応の注意点!
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【トラブル多発】グループホームの土日祝の支援とは?基本や注意点も解説
・【よく間違える】日中支援加算とは?基準や注意点を解説
・【基本】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から徹底解説
・【注意】生活支援員を外部業者に委託する際の注意点とは?
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【注意】大規模住居等減算とは?あえて減算になるメリットも解説
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】サービス管理責任者を配置する注意点とは?間違いやすい例も解説
・【注目】生活支援員の配置の注意点とは?外部の業務委託も解説
・【基本】勤務体制一覧表の注意点は?間違えやすいシフト例も解説
・【注意】定員増加の注意点とは?報酬額や人員配置の問題解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】障害者グループホームに短期入所を併設して収益を上げる方法とは?
<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり
・【注意】処遇改善加算等の社会保険料の計算の仕方とは?改善額の組み入れ