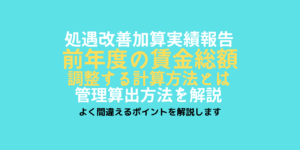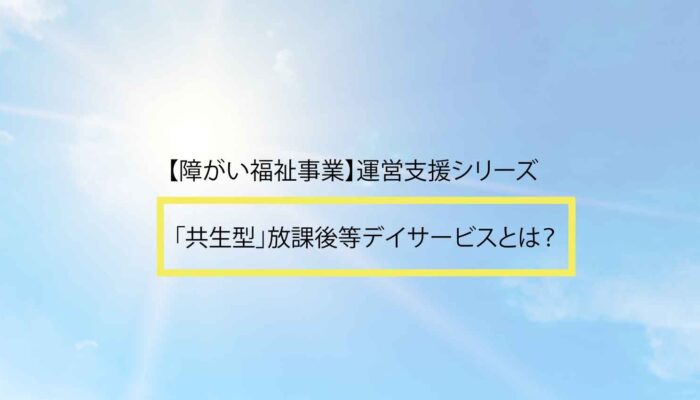
普通とは違った「共生型」の放課後等デイサービスとは何でしょうか?
実はこの「共生型」はどういう意味かというと、
介護保険サービスの事業者が障がい福祉事業の放課後等デイサービスをすること
なのです。
平成30年の介護保険法改正により、介護保険サービスと障害福祉サービスの両方が「共生」して行うことができるのです。
この記事を読めば、「共生型」放課後等デイサービスのポイントや運営上のコツが分かります
近頃、弊所にも介護事業所様から「新しく障がい福祉事業を始めたい」という相談が多数寄せられるようになりました。
そこでこの「共生型」を上手に利用すれば、介護保険の指定を受けた事業所が合わせて障がい福祉の指定も受けやすくなります。
「共生型」の独特のルールもありますので、それを踏まえて運営することが大事なポイントです。
そこで本日はこうした「共生型」の障がい福祉事業、特に放課後等デイサービスについてお話しいたします。
目次
「共生型」放課後等デイサービスとは?
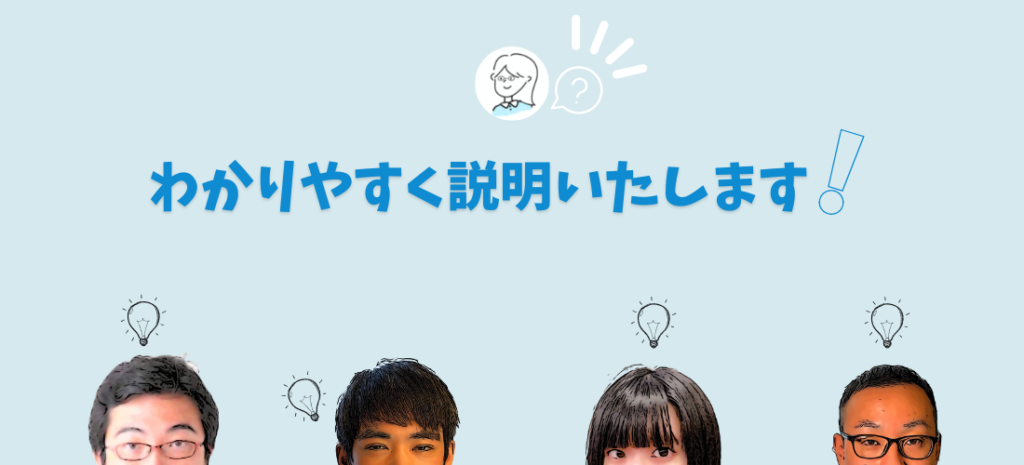
介護保険サービスの事業所さまが、障がい福祉事業の放課後等デイサービスを行うと「共生型」と言われます。
そこで介護保険サービスの種類ごとに必要とされる条件が異なってきますので、順に説明していきましょう。
指定「生活」介護事業者が始める

指定「生活」介護事業者が放課後等デイサービスを始める場合、人員基準を満たすことが主なポイントです。
| (人員配置) | (備考) |
| 従業者 | 「生活介護事業の利用者+障害児の数=合計数」に必要な配置 |
| 管理者 | 支障がなければ、放課後等デイサービス以外の他の職務と兼務できる |
ここでのポイントは児童発達支援管理責任者を配置しなくていい点です。
普通の放課後等デイサービスでは必須の要件になりますが、「共生型」の場合は配置が必ずしも求められません。
その代わり、
「障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること」
がチェックされます。
指定「通所」介護事業者が始める
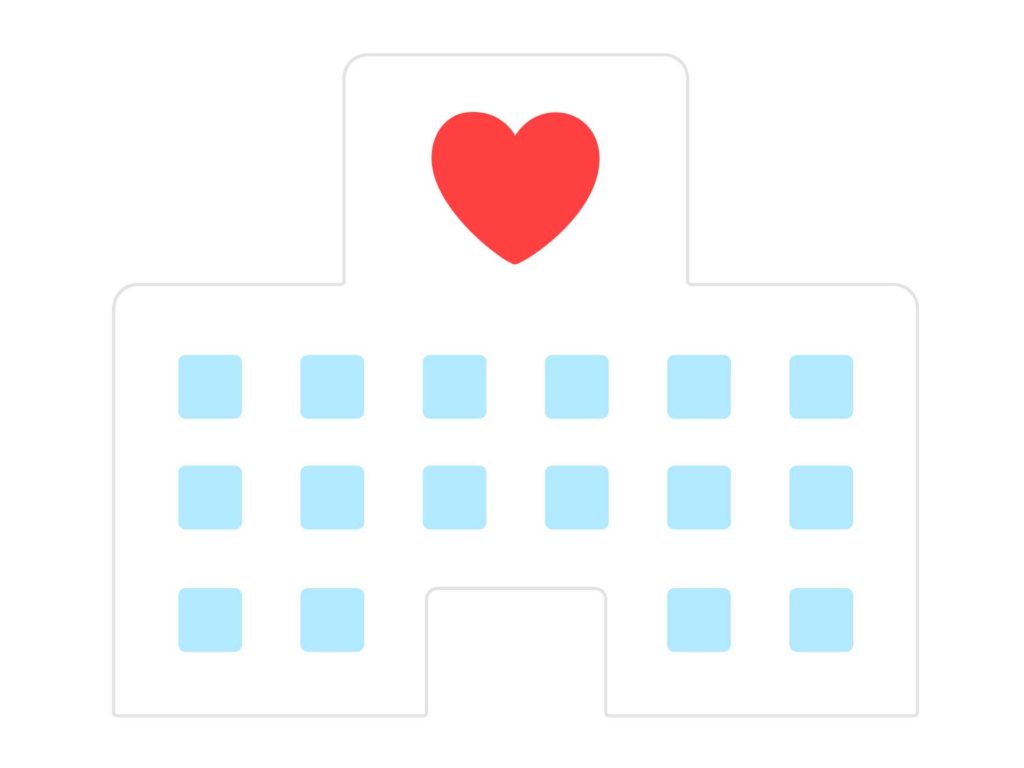
指定「通所」介護事業者が放課後等デイサービスを始めるには、どのような条件がいるのでしょうか?
注意したいのは「設備要件」がある点です。
| (人員配置) | (備考) |
| 従業者 | 「通所介護事業の利用者+障害児の数=合計数」に必要な配置 |
| 管理者 | 支障がなければ、放課後等デイサービス以外の他の職務と兼務できる |
| (設備基準) | (備考) |
| 食堂・機能訓練室 | 「通所介護事業の利用者+障害児の数=合計数」のそれぞれが3㎡以上あること |
ここでもやはり、放課後等デイサービスに必要な児童発達支援管理責任者が要件になっていません。
それゆえに、この「共生型」の特例措置のおかげで、放課後等デイサービスに独自で必要な要件は求められないのです。
小規模多機能型「居宅」介護事業者が始める

また小規模多機能型の居宅介護事業者でも、障がい福祉事業で放課後等デイサービスを開始することができます。
ただし人員配置・設備基準に加え、定員についても条件があるのでご注意ください。
| (人員配置) | (備考) |
| 従業員 | 「居宅介護事業の利用者+障害児の数=合計数」に必要な配置 |
| 管理者 | 支障がなければ、放課後等デイサービス以外の他の職務と兼務できる |
| (設備基準) | (備考) |
| 居間・食堂 | 機能を十分に発揮しうる適当な広さを有する |
| (定員) | (備考) |
| 居宅介護の登録定員 | 29人以下(※サテライトは18人以下) |
| 居宅介護の通所の定員 | 登録定員の二分の一から15人まで(※サテライトは12人以下) |
小規模多機能型の事業所は、訪問・宿泊・通所の3つのサービスがあります。
その中で「通所の定員」に関して特別に制限されている点にご注意ください。
「共生型」のオススメの活用事例
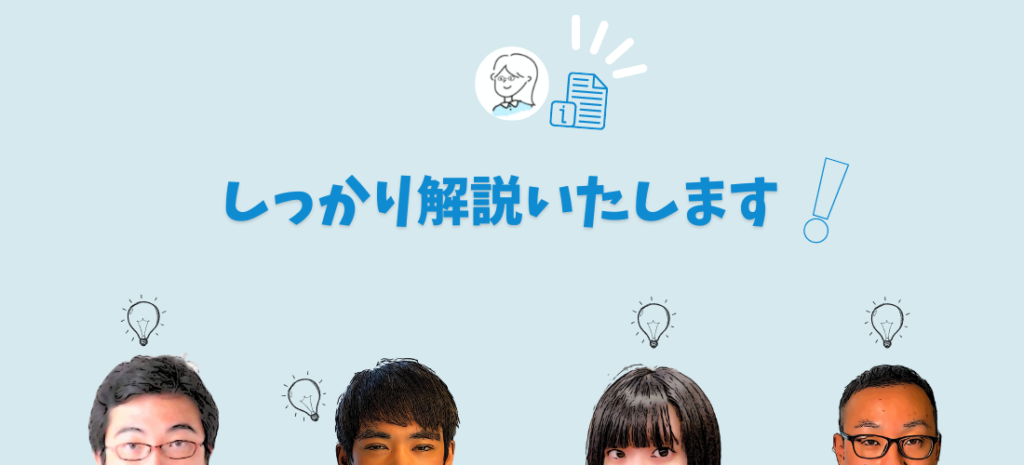
「共生型」放課後等デイサービスとは、
ことに特徴がありました。
だから「共生型」の事業では、児童福祉サービスを提供する事業所との密接な連携がポイントになります。
ただ普通の放課後等デイサービスが要求する基準は満たしていないので、報酬単位には差があります。
| (パターン) | (共生型) | (大小) | (従来:区分I) | (従来:区分II) |
| 授業終了後 | 427 | < | 529 | 426 |
| 休日 | 551 | < | 652 | 549 |
このような報酬単位の差異を踏まえると、次のような疑問が浮かぶでしょう。
どうして別事業として放課後等デイサービスを始めず、「共生型」として介護保険事業所の転用を試みるのか?
そこで最後に「共生型」の障がい福祉事業のオススメの活用事例をご紹介いたします。
人件費を節約して小規模ニーズに応える

事業所が所属する地域に小規模でも障がい福祉の需要があれば、リスクを減らして事業開始できます。
一般的には放課後等デイサービスは最低定員が10名ですし、スタッフとして自動発達支援管理責任者1名と保育士等を2名雇用しなければなりません。
これだけスタッフを雇用するとなると、ある程度の利用者見込みを算定しなければ事業として成立はしません。
それゆえ障がい福祉事業に新規に投資することなく、手持ちの施設とスタッフで対応できてしまう利点があります。
地域の福祉系の人材の活用
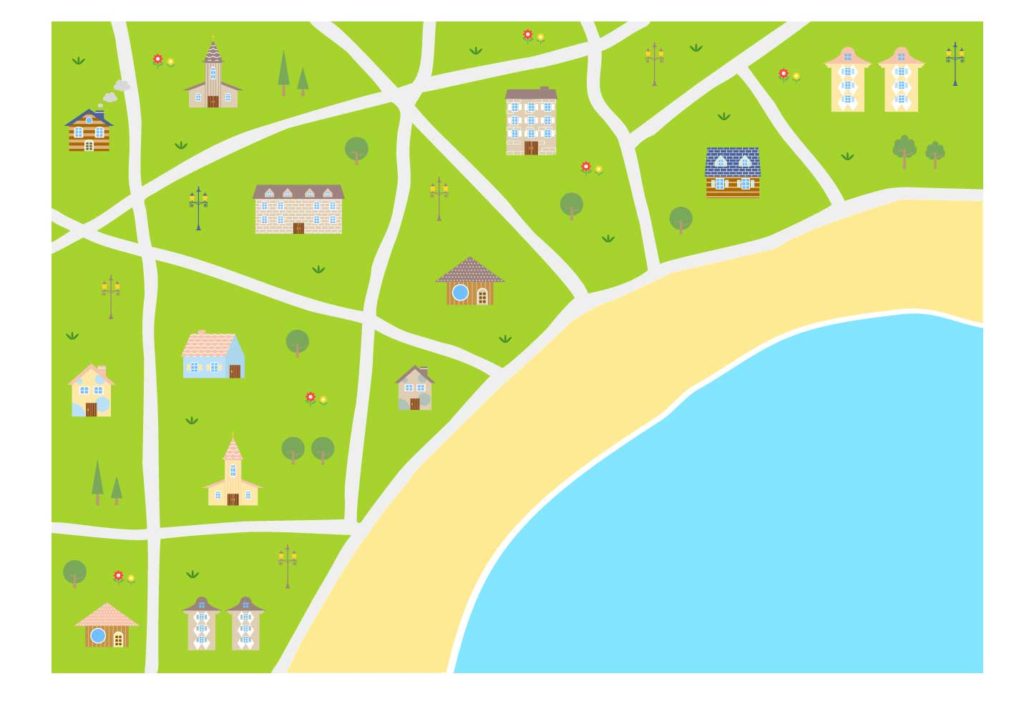
「共生型」の発想は、介護保険と障がい福祉という縦割りの区分を見直すことから始まります。
地域ごとにそれぞれ介護や障がい福祉のニーズは多様に存在するでしょう。
けれども支援に携われる福祉系の人材には限りがあります。
特にこれから少子高齢化がますます進み、数に限りのある人材で増え続ける福祉のニーズを支えていかなければなりません。
世代を横断する支援

また「共生型」で障がい福祉事業を始めることで、利用者の生まれた時から高齢者になって亡くなるまで、世代を横断した支援ができます。
介護事業は基本的に65歳以上から開始されますので、これまでその時点で慣れ親しんできた障がい福祉事業から切り離されてしまいます。
基本的には介護事業が障がい福祉事業に優先する原則があるのです。
そこで長い間、細やかな障がい福祉のサービスを担ってきた事業所が65歳以上からも福祉サービスを継続することは、地域の福祉の安定にとって欠かせないのです。
まとめ:「共生型」は事業の拡大と多角化につながる
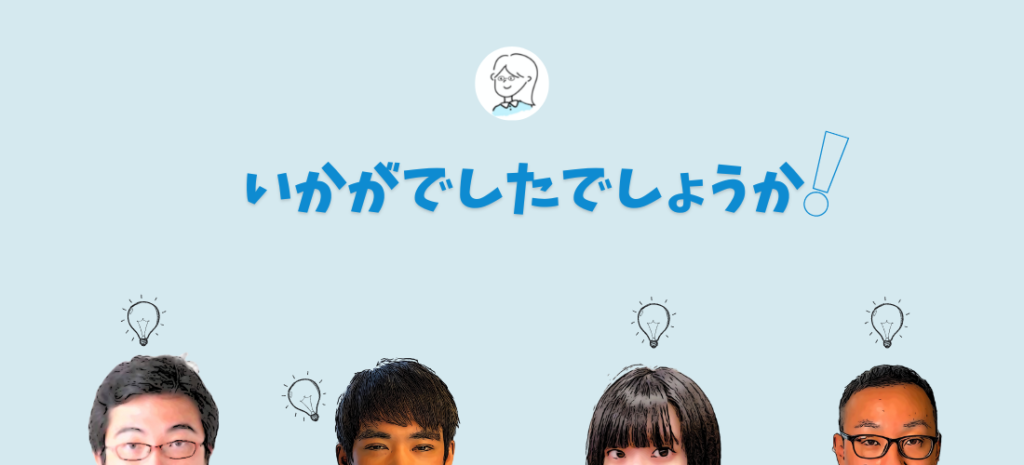
「共生型」のオススメの活用事例として、人材の活用と世代横断のサービス提供という観点をお伝えしてきました。
そこでこれらを整理すると、「共生型」の障がい福祉事業を展開することは福祉事業の拡大と多角化につながることが分かります。
・また年代によって福祉の種類が変わることもなく、亡くなるまでの長期間に渡って利用者とお付き合いすることができます。
それゆえに地域で必要とされている福祉の種類を把握すれば、小さな事業所でも事業規模を大きくすることができるでしょう。
戸根行政書士事務所からのお知らせ
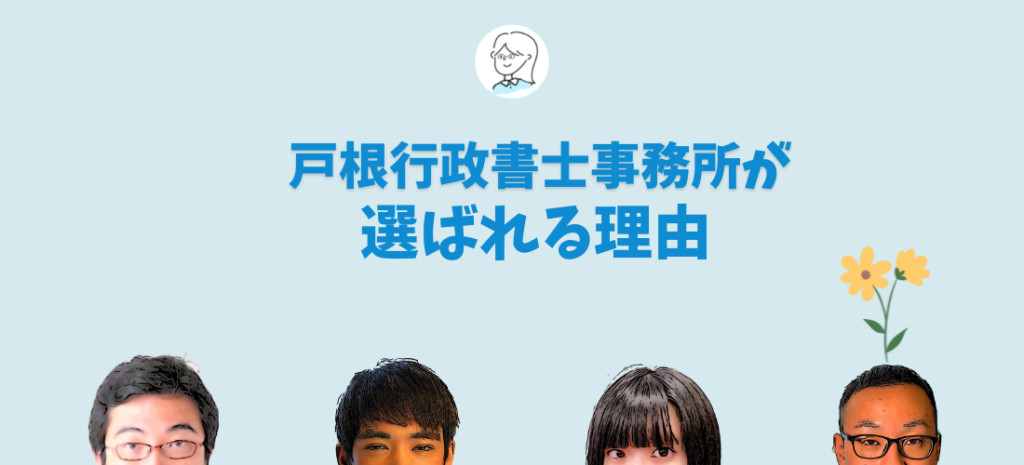
※まとめ:児発・放デイの相談支援系の加算の一覧
1 事業所内相談支援加算:事業所内で個別/グループに相談援助を行う(月に1回)
2 家庭連携加算:自宅訪問をして本人/家族に相談援助を行う(月に4回)
3 関係機関連携加算:関係機関と連携して相談援助を行う(月に1回)
<スタッフ配置のパターンを解説>
・【基本】これだけは覚えておきたい!児童系の人員配置の基本
・【基本】基準職員「営業時間を通じての配置」とは?
・【必見】児童系多機能型の人員配置について
・【確認】児童指導員等加配加算と適正なスタッフの配置について
<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ
<スタッフ配置に関する加算>
・【基本】児童指導員等加配加算とは?取得条件や注意点も解説
・【注意】児童指導員等加配加算と従業員シフト配置の可否について解説
・【確認】特別支援加算とは?条件やおすすめ活用法も解説
・【お勧め】専門的支援加算とは?条件や注意点も解説
<配慮を必要とする児童支援の加算>
・【新設】個別サポート加算とは?条件や注意点を解説
・【基本】「事業所内相談支援加算」とは?取得条件やミス防止もしっかり解説
・【基本】「家庭連携加算」とは?取得条件やミス防止もしっかり解説
・【基本】「関係機関連携加算」とは?取得条件や間違えやすいポイントも解説
・【応用】「強度行動障害児支援加算」とは?取得条件やトラブル事例も解説
<監査指導のトラブルにならないための対策>
・【注意】開所時間減算とは?ポイントや注意点を解説
・【注意】定員超過利用減算とは?条件や気を付ける点を解説
・【基本】延長支援加算について徹底解説!条件や注意点など
・【まとめ】放デイ特有の送迎加算とは?学校送迎の注意点も解説
・【注意】放デイ限定の欠席時対応加算とは?利用時間30分以内でもOK
・【基本】放デイの学校休日等の支援の注意点!トラブル回避のポイント
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
<実地指導のための対策>
・【基本】実地指導、ここがチェックされる!間違えない対策を解説
・【基本】実地指導、ここがチェックされる!②気になる論点の解説
<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり
・【注意】処遇改善加算等の社会保険料の計算の仕方とは?改善額の組み入れ
<事業所管理の健全化に努める>
・【基本】勤務体制一覧表の注意点は?間違えやすいシフト例も解説
・【注意】定員増加の注意点とは?報酬額や人員配置の問題解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】サービス提供時間の適正な設定とは?人件費や報酬単位とのバランス
<年度ごとの義務化への対応>
・【令和3年度】障害福祉のハラスメント防止の対策とは?運営規程の変更案
・【令和4年度】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説