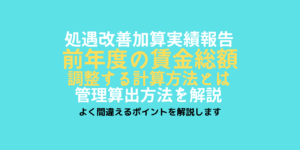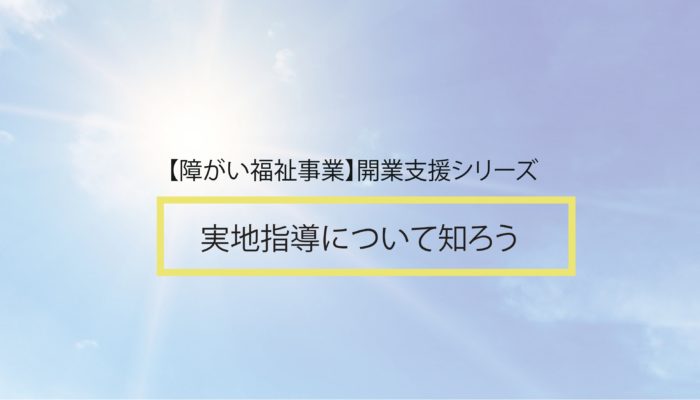
障がい福祉に携わる者は気になる「実地指導」とは何でしょうか?
障がい福祉事業は行政の指定を受けて開始し、それ以後もその公益性の観点から行政の目から見て適正な経営を続けなければなりません。
でも、まあバレないしいいかと思って、残念ですが不適切な経営をなさるところもあります。
そこで行政は一度障がい福祉事業に指定して、それから放置するのではなく、定期的にチェックする「実地指導」をしています。
これまで障がい福祉事業の設立・運営に携わってきた独自の経験からまとめました。
目次
実地指導とは
「実地指導」の時期
だいたい3年に1回の割合で行われます。
※6ヵ月程度で行われる場合もあれば、抜き打ちで行われる場合もありますのでご注意ください。

「実地指導」の種類

一般指導:計画的に行われて、予め文書で通知が届きます。
随時指導:緊急で行われる場合、当日通知で実地指導を行うことができます。
「実地指導」の原因
・苦情が多い
・「不適切な経営をしている」と情報提供がある
・再度の実地指導が必要である
・実施指導が必要と認める時

「実地指導」対策チェックポイント

日々の業務の適正化
毎日
・サービス提供の記録をする
・サービス提供の実績をまとめる
・従業員の出勤をつける
月に1度
・人員配置や資格基準の確認
・加算減算の基準の確認
・適正に給付金の請求をする
サービス提供の適正化
利用者への支援
・アセスメント から個別支援計画を作成
・モニタリングを実施して成果を測る
・家族や支援者を交えたケース会議の実施
利用者への保護
・重要事項や利用契約書を詳しく説明する
・定期的な虐待防止の研修の実施
・苦情や事故を想定したマニュアルの作成と周知
労働環境の適正化
雇用
・雇用契約書を結ぶ
・労働条件通知書を出す
・秘密保持系役所を結ぶ
健康
・定期的に健康診断を受診してもらう
・感染症対策の規定への署名
・定期的な検温や消毒の実施
まとめ
・「実地指導」が抜き打ちで行われるケースもある
・日々の業務の適正化、サービス提供の適正化、労働者の適正化を意識する
戸根行政書士事務所からのお知らせ
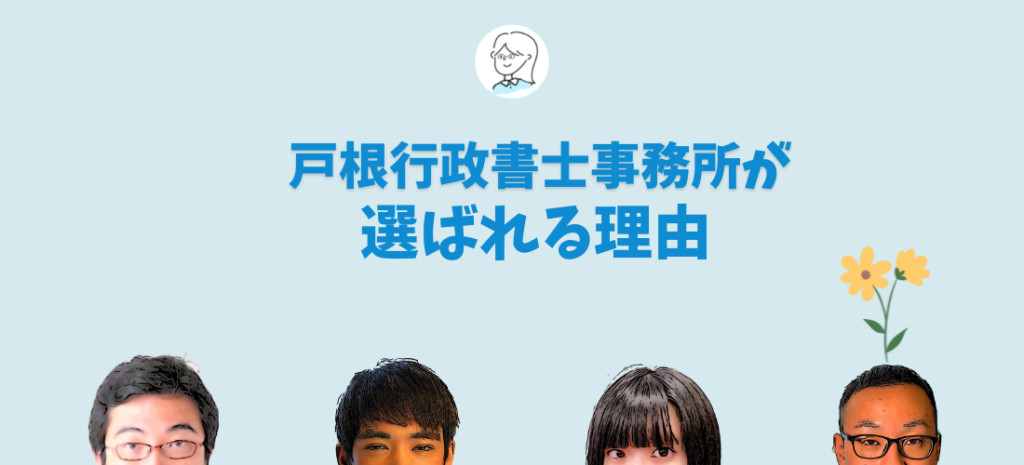
<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ
・【まとめ】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から注意点まで解説
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
<減算について>
・【基本】人員欠如の減算とは?計算方法や注意点も解説
・【詳解】人員欠如の減算:基準や緊急対応・防止策をご説明
・【詳解】サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算とは?
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題点と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【必見】就労支援事業会計とは?会計区分や按分処理のポイント解説
・【注意】就労支援事業の積立金とは?余剰金を発生させない会計処理
・【注意】サービス管理責任者の更新研修の条件とは?
・【基本】サービス管理責任者の実務経験おすすめルートとは?
・【基本】「一体型」と「多機能型」の違いとは?事業拡大のチャンス!
・【大注目】令和5年サービス管理責任者の実務経験が6ヶ月に変更!
・【大注目】令和5年サービス管理責任者不在の猶予期間が2年に!
<工賃上昇のための体制づくり>
・【高収入】施設外就労支援の注意点とは?基本から間違えやすいミスまで説明
・【推奨】就労移行連携加算とは?オススメ活用事例あり
・【注目】就労移行支援体制加算とは?オススメ活用事例あり
・【注目】就労継続支援事業所に計画相談支援事業所を併設して収益アップ!
<工賃支払いを適正に管理する>
・【基本】就労継続支援B型:工賃支払いの注意点は?月ごとの手続き解説
<現状に応じた適切な事業所体制を作る>
・【基本】平均工賃月額の計算の仕方は?解説と注意点とは
・【重度】「重度者支援体制加算」とは?よくある間違いも解説
<工賃支払以外の参加・共感型の新体制を目指す>
・【令和3年】ピアサポート体制・実施加算とは?オススメ活用事例あり
・【令和3年】地域協働加算とは?オススメ活用事例あり
<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
・【義務化】身体拘束適正化委員会と「身体拘束廃止未実施減算」とは
<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援A型編>
・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説
・実地指導、ここがチェックされる②!間違えやすいポイント解説
<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援B型編>
・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説