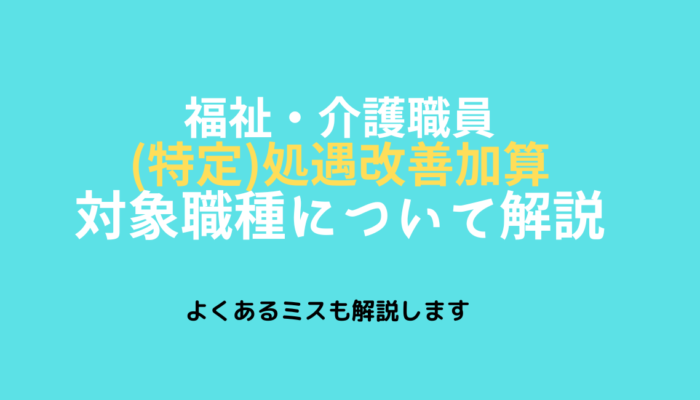
障がい者福祉事業をしていて処遇改善加算や特定処遇改善加算の取得を検討しております。
従業員の待遇を上げて職場環境をよくしたいと思うのですが、処遇改善加算はどの従業員に対して可能なのでしょうか?
普通の処遇改善加算や特定処遇改善加算を取得するための条件や注意点をわかりやすく教えてもらえるでしょうか?
よくあるミスとして、処遇改善加算により賃金改善をする従業員の職種を間違えることが挙げられます。
放置していると実地指導の時にトラブルになるのでご注意ください。
処遇改善加算と特定処遇改善加算の各々が対象職種の選び方も異なります。この記事では事業者様の理解の一助になるように以下のような内容がわかるように説明いたします。。
- 「福祉・介護職員処遇改善加算」の対象職種がわかります
- 「福祉・介護職員特定処遇改善加算」の対象職種がわかります
- 兼務や法人役員の問題に関するの疑問や不安が解消されます
目次
- 1 「福祉・介護職員処遇改善加算」の対象職種は?
- 2 「福祉・介護職員特定処遇改善加算」の対象職種は?
- 3 よくある質問
- 3.1 「経験・技能のある障害福祉人材」と「その他の職員」だけで特定処遇改善加算を取得できますか?
- 3.2 「その他の職員」の中でも小分けのグループを作ることができますか?
- 3.3 サービス区分の異なる複数のサービスを運営している場合、「月額8万円以上もしくは年収440万円となる者」はサービス区分ごとに設定しますか?
- 3.4 特定処遇改善加算のための配分ルールが変更になった場合はどうすればいいか?
- 3.5 「月額8万円以上もしくは年収440万円となる者」が年度の途中で退職した場合はどうすればいいか?
- 3.6 賃金改善を行う前に年収440万円を上回る「その他の職員」は前年度の職員数に含むか?
- 3.7 本部の人事部や事業部で働く職員は「その他の職員」に含めて賃金改善できますか?
- 3.8 「経験・技能のある障害福祉人材」をグループ化する時に、他の法人での業務の経験数は含めて考えることはできますか?
- 3.9 賃金改善期間中に勤続10年に達する者で、「他の介護職員」から「経験・技能のある職員」に変更になる者はどうすればいいでしょうか?
- 3.10 法人単位で処遇改善加算を申請する場合、「月額8万円もしくは年収440万円の者」は法人内の各事業所に1人を必要としますか?
- 3.11 非常勤職員の賃金が440万円以上であることをどのように判断するか?
- 3.12 「経験・技能のある障害福祉人材」と「他の介護職員:を区別せず処遇改善を配分している場合は、どうすればいいでしょうか?
- 4 まとめ
「福祉・介護職員処遇改善加算」の対象職種は?
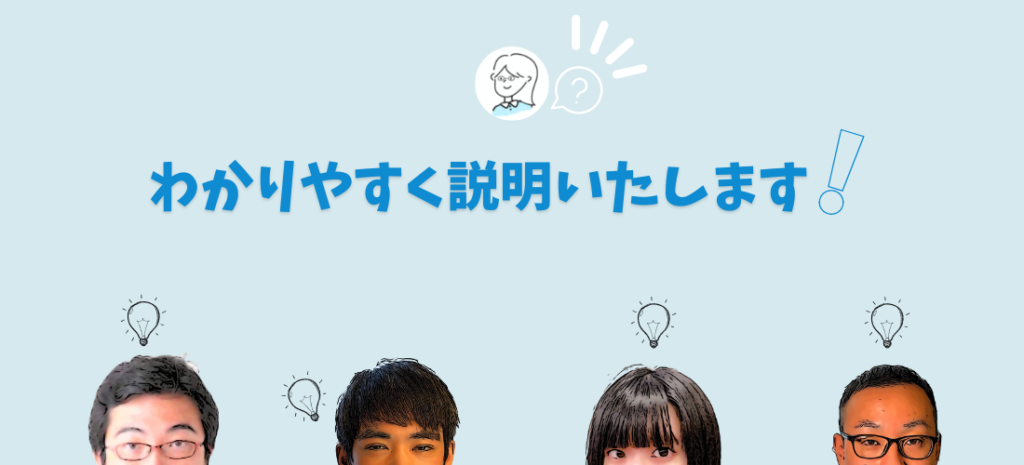
「福祉・介護職員等処遇改善加算」は、職員の賃金を改善して職場環境を良くしたり、優秀な職員を集めたりするため役に立つ加算です。
<福祉・介護職員等処遇改善加算とは?>
福祉・介護職員の賃金改善等について、一定の基準に適合する取り組みを実施している場合に算定することができます
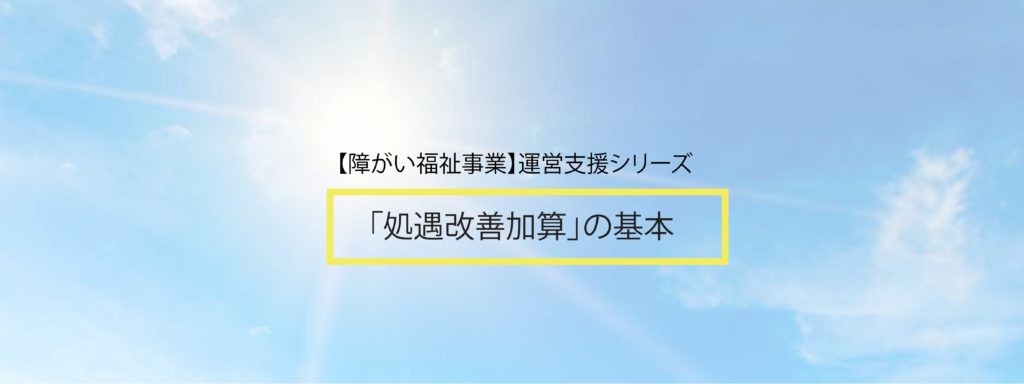
「福祉・介護職員処遇改善加算」の賃金改善には計画書を毎年自治体に提出する必要がありますよね。
賃金規程や就業規則の変更も行いたいので、そのためにも普通の処遇改善加算の対象となる職種について詳しく解説してもらえるでしょうか?
「福祉・介護職員処遇改善加算」の取得は、従業員のモチベーションを上げるためにも、またより良い福祉サービスを提供できる環境づくりにも必要な加算です。
ただよくある間違いとして、全従業員の処遇を改善してしまうことなど挙げられます。
それでは「福祉・介護職員処遇改善加算」の対象者についてしっかり説明したいと思います。
基本:福祉・介護職員の定義について
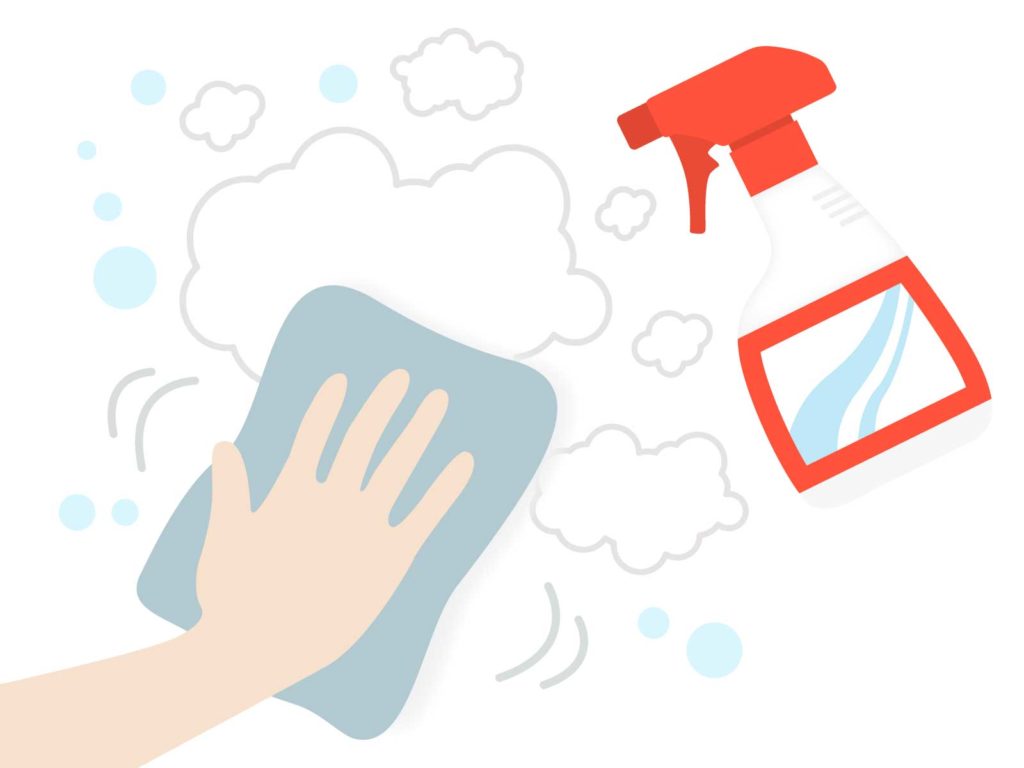
一般の「福祉・介護職員処遇改善加算」の対象職種は、成人系でも児童系でも「福祉・介護職員」に限定されています。
※事業所内の全員に加算を分配することはできません。
<(成人系)福祉・介護職員とは>
・ホームヘルパー
・生活支援員
・世話人
・夜間支援従業者
・職業指導員
・就労支援員
・目標工賃達成指導員
・工賃向上達成指導員
・訪問支援員
・地域移行支援員
・介護職(共生型)
<(児童系)福祉・介護職員とは>
・児童指導員
・保育士
・障害福祉サービス経験者
処遇改善加算でよくある間違いはサービス管理責任者を対象職種と考えてしまうミスです。サビ管は直接支援をするわけではありませんので処遇改善の対象にはなりません。
また各サービスの人員基準で必要とされる職種以外でも、上記区分に該当するなら処遇改善の加算となるのでご注意ください。
論点1:他業務との兼務ができる?
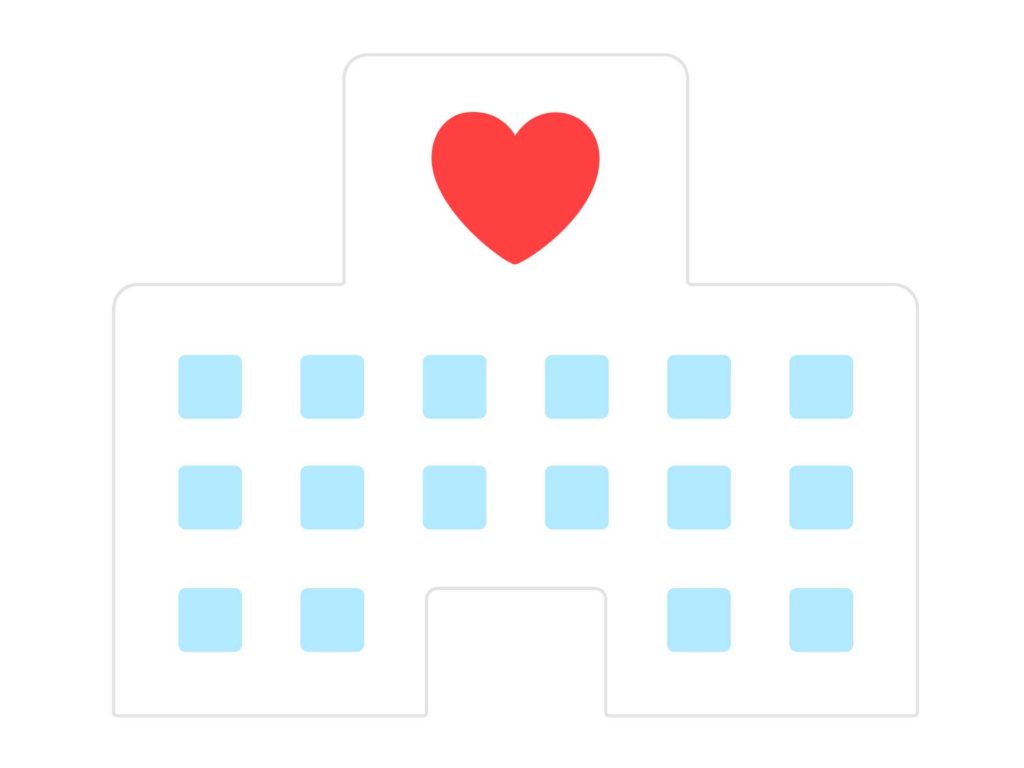
一般の「福祉・介護職員等処遇改善加算」を取得するにあたって、対象となる介護・福祉職員が他業務と兼務しているでも算定することが可能です。
※ただし兼務の職員を含める場合は以下の条件が必要です。
<兼務の職員を処遇改善する条件>
・辞令や雇用契約書に障害福祉事業に従事する旨の記載があること
・勤務表等に障害福祉事業に従事する旨の記録等が残されていること
・当該事業所の職員配置について、法的基準をクリアしていること
・職種の資格証、研修修了証等を保管しておく
他業務と兼務している職員に対して、「福祉・介護職員等処遇改善加算」の賃金改善を行うことは可能ですが、勤務している配置上の実態の証明が必要になります。
特に介護事業と兼務している場合が多く、複数のサービスを運営している会社様は誰がどの割合で兼務しているかを明確に把握しておくと安心です。
論点2:法人役員は対象?
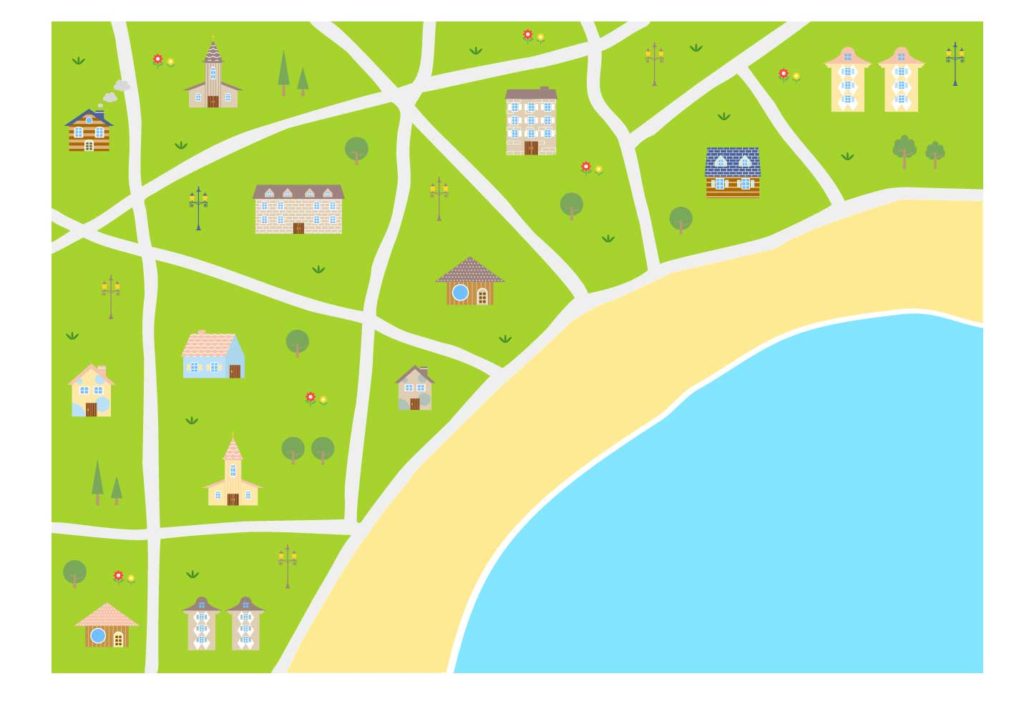
一般の「福祉・介護職員処遇改善加算」の対象になる職種に関して、法人の役員は原則として処遇改善加算の対象になりません。
※ただし以下の条件で直接支援の職務と兼務している場合は例外的に認められます
<例外的に法人役員が処遇改善加算の対象となる場合>
・シフト表等に福祉・介護職員として従事していることの実態が記録されている場合
・本人に対して「役員報酬」だけでなく「給与」が払われていること
・兼務役員の届出をハローワークに出していること
よくある間違いで法人役員は絶対処遇改善の対象にならないと思ってしまうミスがあります。でも福祉・介護職員と兼務している場合は条件付きで対象になる点を注意しましょう。
ただし役員報酬以外に給与明細所を形式上は発行し源泉徴収も別で行う必要があるのでご注意ください。
※法人の代表役員は処遇改善の対象になりません
法人の役員の中でも代表役員は処遇改善にならないので、前年度の賃金の総額など各種計算も代表役員の額を含めずに計算することになります。
※法人の代表以外等であっても持ち株比率によって使用人兼役員にはなれません
・その役員と同族関係者で所有が10%超
・その役員と配偶者で所有が50%超
・順位が1〜3位の株主/出資者で所有が50%超の場合にその役員がいる
以上の要件全てが当てはまった場合に代表以外の役員も使用人兼役員にはなれません
論点3:派遣労働者の扱い方は?
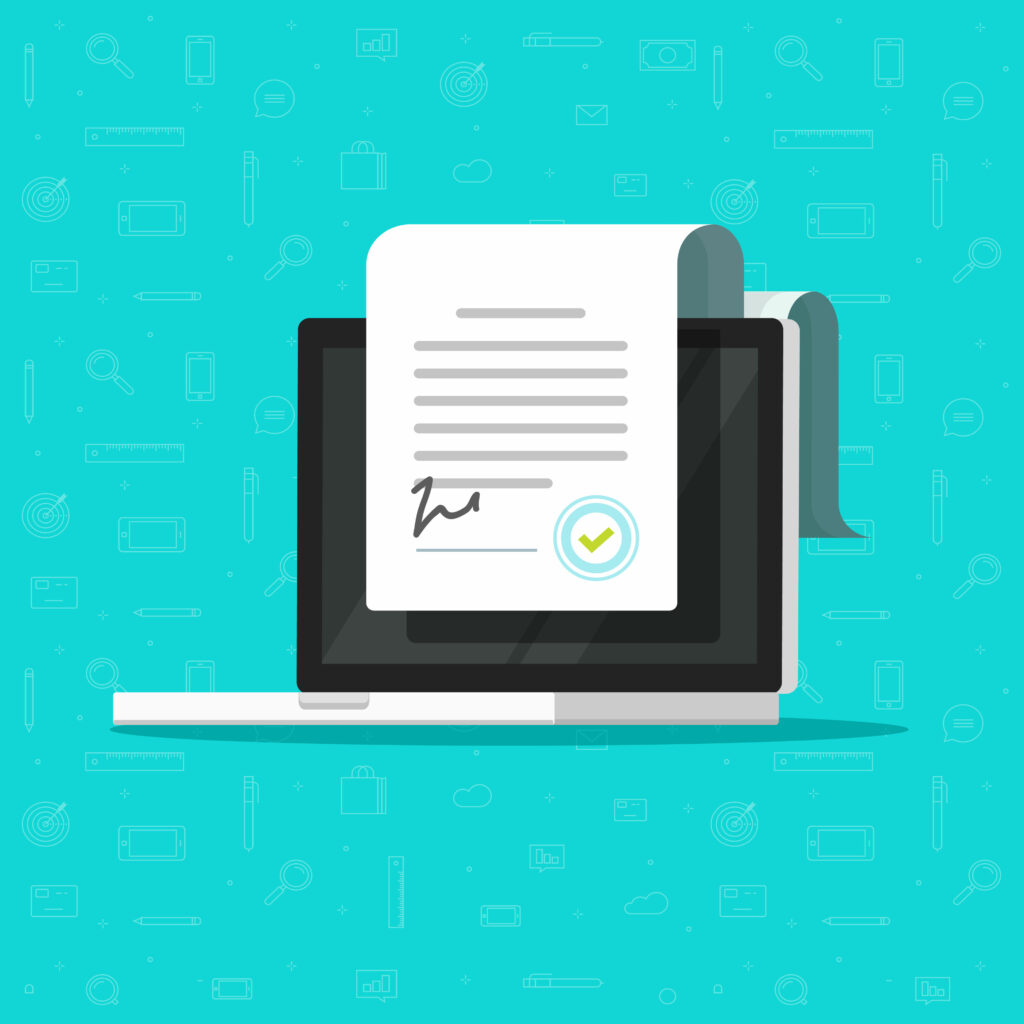
一般の「福祉・介護職員等処遇改善加算」を取得する時、派遣労働者という形態であっても処遇改善加算で賃金改善することが可能です。
※事業所の固有の職員と区別する必要はありません。
<派遣労働者に対して賃金改善するポイント>
・計画書や実績計画書は派遣労働者を含めて作成する
・賃金改善の方法は派遣金額を増額するという形にする
派遣労働者の直接支援職員であっても、指揮命令は加算を取得する事業所にあるので処遇改善をすることができます。
派遣先との契約関係などを確認して、自社の職員と不当に差別することがないように賃金改善を行いましょう。
「福祉・介護職員特定処遇改善加算」の対象職種は?
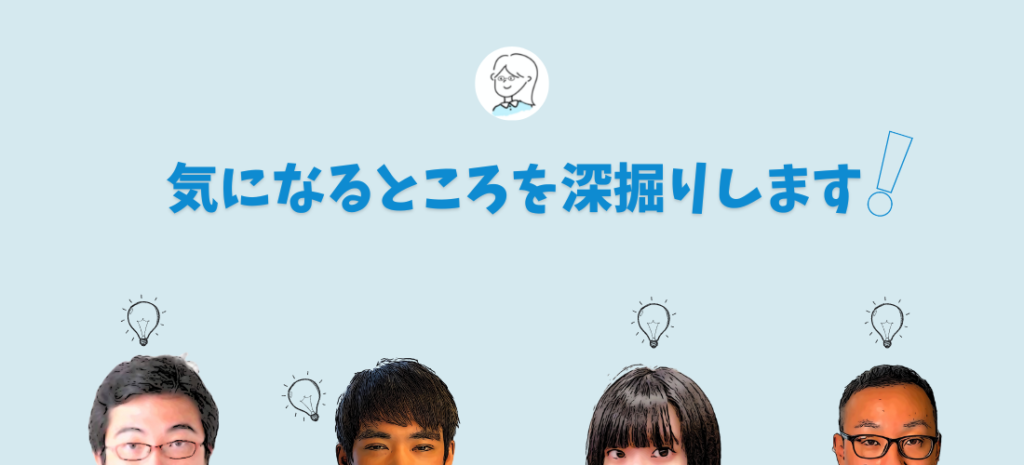
「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」は、普通の処遇改善加算の取得要件をより厳密にした上位バージョンであるとご理解ください。
※処遇改善(I)から(III)を取得していることが前提になります。
<福祉・介護職員等特定処遇改善加算とは?>
処遇改善加算の(I)から(III)までのいずれかを取得している事業所が、当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行なっていて、その内容をホームページへの掲載等の見える化を行なっている場合に取得できる加算です
| (区分) | (加算率) | (備考) |
| 特定処遇改善加算(I) | 所定単位の1.3% | |
| 特定処遇改善加算(II) | 所定単位の1.0% | 福祉専門職員等配置加算なし |
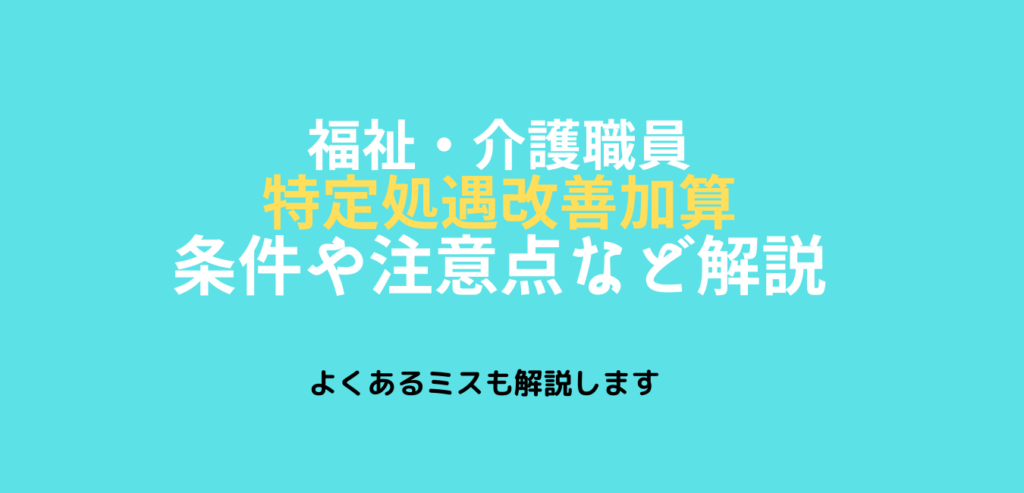
「福祉・介護職員特定処遇改善加算」は普通の処遇改善の上位モデルなのですね。「福祉専門職員等配置加算」の有無でカテゴリーが変わるとも知りました。
それでは特定処遇改善の対象職種も、普通の処遇改善の対象職種と同じでしょうか?計画書式を見ていると難しそうな式でグループ分けされているのですがどういうことでしょうか?
「福祉・介護職員特定処遇改善加算」の対象職種は一般的な処遇改善と全く異なります。
特定処遇改善の対象者はかなり幅広い範囲で設定することができます。
それでは「福祉・介護職員特定処遇改善加算」の対象職種についてしっかり説明したいと思います。
前提:スタッフを3パターンに分類して分配率を決める

「福祉・介護職員特定処遇改善加算」と一般の処遇改善が異なる点は、その前提として分配率を決めるために「賃金改善を行うスタッフ」を3パターンに分類することです。
※必ずしも全てのグループに分配する必要はありません。
| (分類) | (定義) |
| 「障害福祉人材」 | 福祉・介護職員、サビ管、児発管理等 |
| 「経験・技能のある障害福祉人材」 | 「障害福祉人材」の中で一定の技能があり同時に経験のある者 |
| 「その他の職員」 | 「障害福祉人材」以外の者 |
<「経験・技能のある障害福祉人材」について>
基本的には勤続年数10年以上の社会福祉士等とされていて、その基準をもとに事業所ごとに任意で定義することが可能です。
<「社会福祉士等」とは?>
・介護福祉士/社会福祉士/精神保健福祉士/保育士
・心理指導担当職員(公認心理師含む)
・サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者
<勤続年数10年以上とは?>
・勤続年数の計算は同一法人だけでなく他法人や医療機関等での経験も通算できる
・10年未満の勤続年数でも事業所内の能力評価・等級システムにより該当ありとみなすことができる
特定処遇改善加算の対象職種は、直接支援を行う福祉・介護職員に限定する必要はありません。
サービス管理責任者、そして直接支援に携わらない事務方も含めて特定処遇改善加算の対象職種とすることができます。
1人が月額8万円以上の賃金改善もしくは年額440万円以上
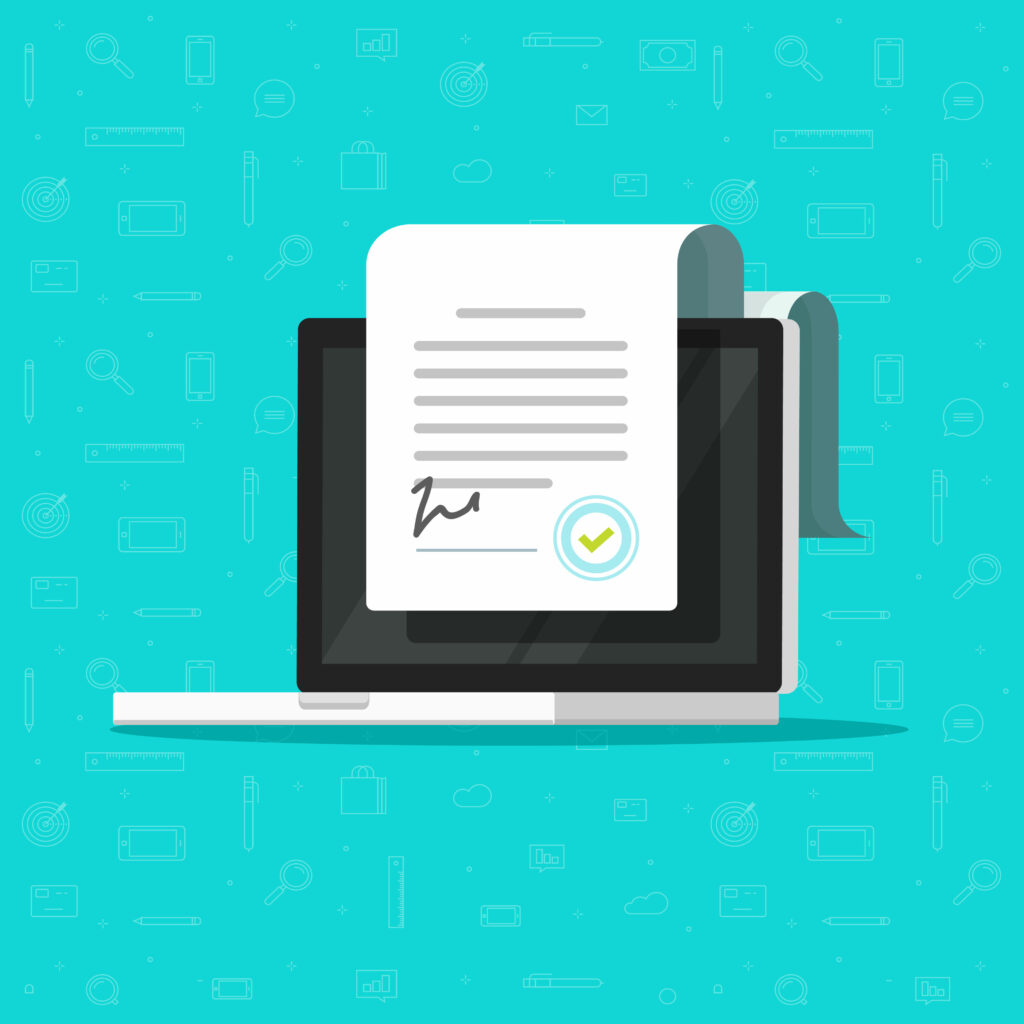
「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を取得するには、「経験・技能のある障害福祉人材」グループに属する対象職種1人が、賃金改善により月額8万円以上、もしくは年額440万円以上になる必要があります。
※小規模な事業所等はこの条件を満たす必要がない場合もあります。
※複数の非常勤職員で常勤換算合計が1人以上でも問題ありません。
<「年額440万円以上」のポイント>
・退職手当は含まなくていい
・処遇改善加算の手当は含む
・年度途中から加算を取得する場合、仮に12ヶ月勤務していたという仮定で計算する
・現に年額440万円以上の方がいれば充当できる
・社会保険料の事業主負担など法定福利費は含まない
<「月額8万円以上」のポイント>
・期間内の平均月額賃金改善が8万円以上
・介護と兼務の場合、障害だけで8万円の賃金改善を行う
・現行の処遇改善に関する手当は含まない
・法定福利費の増加分を含めて判断できる
「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の取得に際して対象職種として、このような一定額以上の賃金を受けるスタッフを選ぶ必要があります。
「月額8万円以上」か「年額440万円以上」のどちらかのパターンを選択していただき、それぞれのルールを守って候補者を絞っていただければと思います。
ただこの条件が適用されない例外的なケースもあるので、以下でご紹介いたします。
<基準を満たせない例外的なケースについて>
・小規模事業所で加算額全体が少額である場合
・全体の賃金水準が低く、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
・これまで以上に事業所内の階層/役職/能力/処遇の明確化が必要になるため、規程の整備/研修・実務経験の蓄積に一定期間を要する場合
よくある質問

「経験・技能のある障害福祉人材」と「その他の職員」だけで特定処遇改善加算を取得できますか?
答:可能です。ただし「経験・技能のある障害福祉人材」が「その他の職種」より2倍より高い平均賃金改善額を得てください。
「その他の職員」の中でも小分けのグループを作ることができますか?
答:可能です。その場合、「その他の職員」全体で「障害福祉人材」の平均賃金額を上回っていても、特定の「その他の職員」のグループだけ上回らないなら、そのグループだけ「障害福祉人材」と等しくなるまで賃金改善できる。
サービス区分の異なる複数のサービスを運営している場合、「月額8万円以上もしくは年収440万円となる者」はサービス区分ごとに設定しますか?
答:設定いたしません。一体的に複数のサービスを運営していると認められた場合は全体で1人設定すれば十分です。ただし複数の事業所がある場合それぞれで設定する必要があります。
特定処遇改善加算のための配分ルールが変更になった場合はどうすればいいか?
答:実績報告の際に合理的な理由を説明してください。ただし加算による収入額以上の賃金改善は必要になります。
「月額8万円以上もしくは年収440万円となる者」が年度の途中で退職した場合はどうすればいいか?
答:合理的な説明ができれば存在していたとみなすことができます。
賃金改善を行う前に年収440万円を上回る「その他の職員」は前年度の職員数に含むか?
答:含みます。賃金改善を行わない職員も「その他の職員」の範囲に含みます。
本部の人事部や事業部で働く職員は「その他の職員」に含めて賃金改善できますか?
答:算定対象サービス事業所で業務を行なっていると判断できる場合に算定可能です。
「経験・技能のある障害福祉人材」をグループ化する時に、他の法人での業務の経験数は含めて考えることはできますか?
答:可能です。
賃金改善期間中に勤続10年に達する者で、「他の介護職員」から「経験・技能のある職員」に変更になる者はどうすればいいでしょうか?
答:計画書は現時点の職種で提出し、途中で配分を調整し、最終的に「他の職員」と「経験・技能のある職員」の配分比率を守りましょう。
法人単位で処遇改善加算を申請する場合、「月額8万円もしくは年収440万円の者」は法人内の各事業所に1人を必要としますか?
答:必要といたしません。事業所内の事業所の数だけ「月額8万円もしくは年収440万円の者」を確保すれば問題ありません。
非常勤職員の賃金が440万円以上であることをどのように判断するか?
答:440万円に常勤換算後の数をかけた金額であれば達成していることにします。
例)常勤換算0.4の職員なら440万円×0.4=176万円
「経験・技能のある障害福祉人材」と「他の介護職員:を区別せず処遇改善を配分している場合は、どうすればいいでしょうか?
答:人数比により推計し各グループに配分された額を求めてください。
まとめ
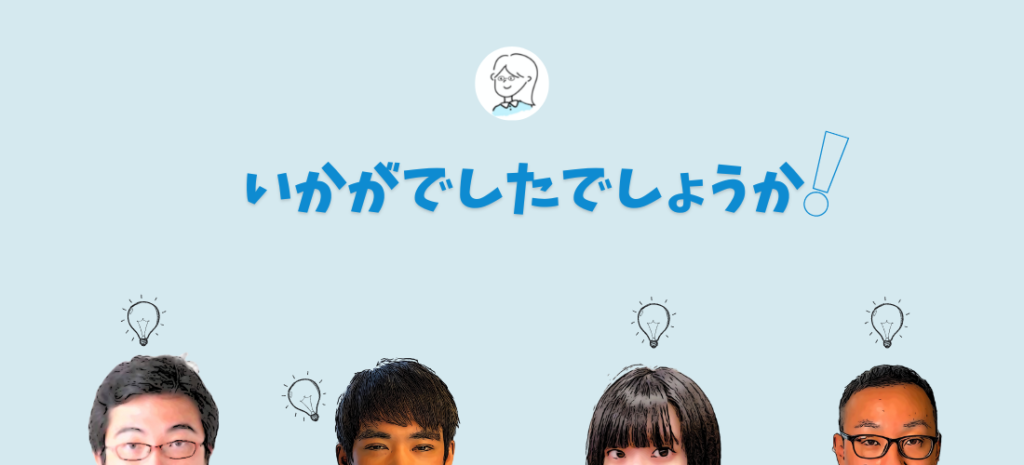
本日は「福祉・介護職員処遇改善加算」の対象職種について詳しく理解することができました。ありがとうございます。
加算により賃金改善する時に間違えて対象外のスタッフに賃金を追加で支給しないように気をつけます。
処遇改善加算・特定処遇改善加算は人手不足が言われている障害福祉業界で役に立つ加算です。
賃金改善が常に行われれば職場環境も良くなるでしょう。ただし間違えて対象外の職種に加算を分配するとトラブルになるのでお気をつけください。
特定処遇改善はスタッフの方の賃金を上げて事業全体を安定させるためにも重要な加算ですので活用していただければと思います。
<特定処遇改善加算の注意点1:「経験・技能のある障害福祉人材」を適正に定義する>
・事業所の規模と現状に応じて基準に照らし定義する
・月額8万円以上もしくは年額440万円以上の者がいるか確認する
・役職名は関係ない
戸根行政書士事務所からのお知らせ
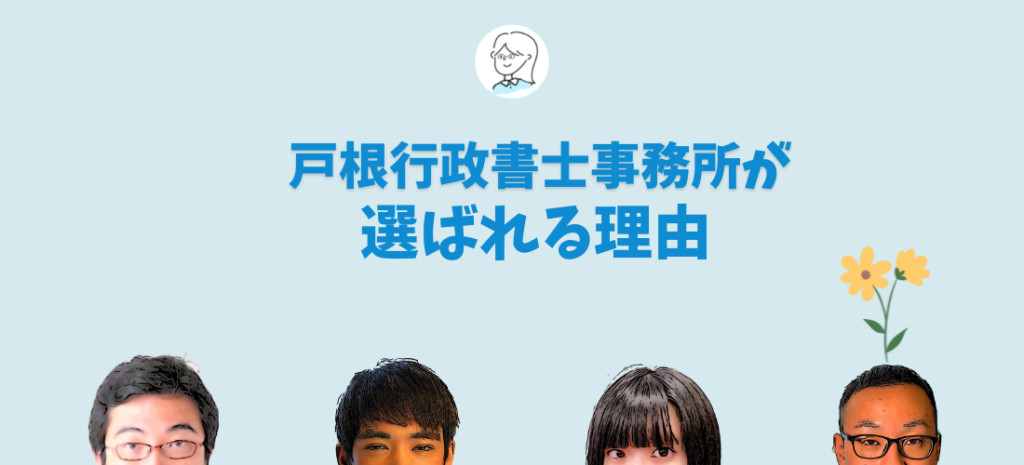
<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ
・【まとめ】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から注意点まで解説
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
<減算について>
・【基本】人員欠如の減算とは?計算方法や注意点も解説
・【詳解】人員欠如の減算:基準や緊急対応・防止策をご説明
・【詳解】サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算とは?
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題点と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【注意】一つの建物に複数の共同生活住居を設置する条件とは?
・【基本】「一体型」と「多機能型」の違いとは?事業拡大のチャンス!
<夜間支援の加算等>
・【基本】夜勤職員加配加算の要件とは?注意点やオススメ活用事例あり
・【基本】重度障害者支援加算とは?注意点や活用事例あり
・【最新版】夜間支援等体制加算とは?注意点・活用事例も紹介
・【注意】グループホームの夜間支援体制のスタッフ配置:注意点も解説
・【要点】「夜間支援等体制加算」の利用者数の計算とは?
<医療/入院関係の加算等>
・【基本】看護職員配置加算とは?要件・活用事例も解説
・【基本】医療連携体制加算とは?要件・注意点・おすすめ活用も解説
・【注意点】個人単位で居宅介護は利用できるの?要件や注意点を説明
・【基本】強度行動障害者体験利用加算とは?取得条件や活用事例も紹介
・【基本】長期入院時支援特別加算とは?基準や注意点を解説
・【基本】入院時支援特別加算とは?基準や注意点を解説
・【基本】医療的ケア対応支援加算とは?加算条件や活用方法も解説
・【基本】「帰宅時支援加算」とは?取得条件や間違えやすいポイントを解説
・【基本】「長期帰宅時支援加算」とは?取得条件や間違えやすい点を解説
<利用者さんとのトラブルを避ける対策>
・【まず知りたい】グループホーム運営は何が難しいの?
・【注意】グループホーム利用者との金銭トラブルについて
・【質問】「通院時も付き合って欲しい」と言われたら?通院支援の対策を解説
・【注意】グループホームの費用設定はどのように?利用者負担も解説
<実地指導のトラブルにならないための対策>
・【まず知りたい】実地指導とは?チェックリストもお教えします
・【直前対策】実地指導を受ける時の対応の注意点!
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【トラブル多発】グループホームの土日祝の支援とは?基本や注意点も解説
・【よく間違える】日中支援加算とは?基準や注意点を解説
・【基本】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から徹底解説
・【注意】生活支援員を外部業者に委託する際の注意点とは?
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【注意】大規模住居等減算とは?あえて減算になるメリットも解説
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】サービス管理責任者を配置する注意点とは?間違いやすい例も解説
・【注目】生活支援員の配置の注意点とは?外部の業務委託も解説
・【基本】勤務体制一覧表の注意点は?間違えやすいシフト例も解説
・【注意】定員増加の注意点とは?報酬額や人員配置の問題解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】障害者グループホームに短期入所を併設して収益を上げる方法とは?
<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり
・【注意】処遇改善加算等の社会保険料の計算の仕方とは?改善額の組み入れ












































