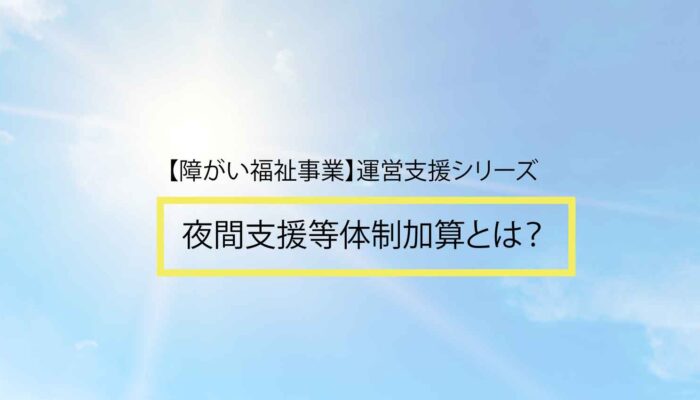
「共生型」の放課後等デイサービスに適用できる「共生型サービス体制強化加算」とは何でしょうか?
「共生型」の障がい福祉事業とは、介護保険事業所が現存のスタッフや設備を転用し、介護事業と共に行うモデルです。
そこでこの「共生型」のポイントは、本来ならばその障がい福祉サービスで必要な要件を満たさなくていいという点にあります。
例えば放課後等デイサービスは、児童発達支援管理責任者や保育士の配置は必要ですが、「共生型」では必ずしもその要件を満たす必要はありません。
けれども、そのような最低条件の状態に加えて本来の障がい福祉事業に近く体制を整えると追加の給付がもらえるのです。
まさにそれが「共生型サービス体制強化加算」です。
この記事を読むと、「共生型サービス体制強化加算」の種類や取得条件が分かります
これまで弊所も「共生型」を採用する事業所さまとお付き合いする中で、やはり「障がい福祉事業のことが分からないので新しくスタッフを入れたい」という声を度々聞きます。
しかし新しいスタッフを入れると人件費も付加されるので、この「共生型サービス体制強化加算」をしっかり理解し、人員追加の検討をすることが大切です。
目次
「共生型サービス体制強化加算」とは?
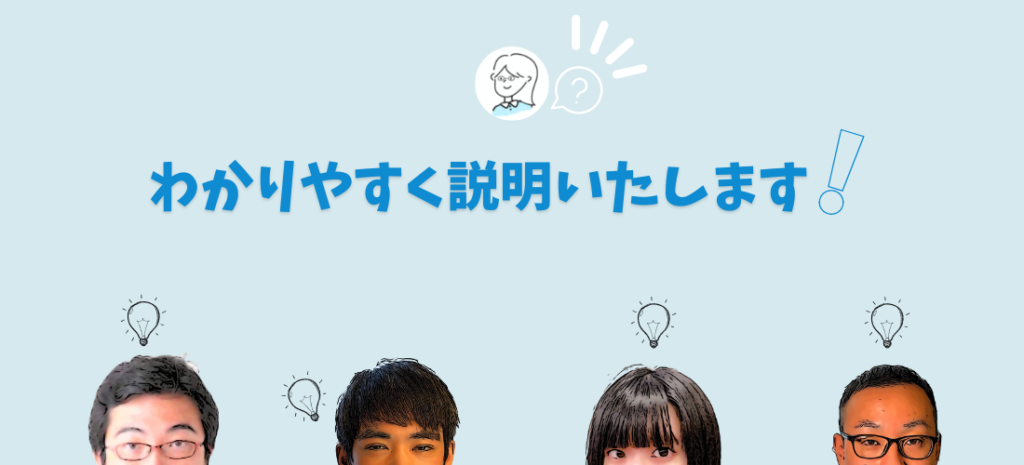
「共生型」の放課後等デイサービスは、普通の障がい福祉サービスより報酬単位の設定が低くなっております。
それは本来の放課後等デイサービスで必要とされている要件を満たしていないからでしょう。
そこで次のような疑問が浮かぶでしょう。
本来の放課後等デイサービスに必要な条件を満たすと、どれくらいの加算がもらえるのか?
こうした「共生型サービス体制強化加算」のポイントをまとめたいと思います。
加算の報酬単位

「共生型サービス体制強化加算」のパターンごとの報酬単位は次の通りです。
| (パターン) | (報酬単位) |
| 児発管and保育士or児童指導員:それぞれ1名以上 | 181 |
| 児発管:1名以上 | 103 |
| 保育士or児童指導員:1名以上 | 78 |
このようなパターンごとの配置をしていると、「共生型」の放課後等デイサービスの基本報酬に、上記の加算が付加されます。
| (パターン) | (基本報酬) | (体制強化加算) | (合計) |
| 児発管:1名以上 | 427 | 103 | 530 |
つまり放課後等デイサービスの利用者が月に80回あれば、
| 「共生型」のみ | 「共生型」+体制強化加算 | |
| 427×10円(地域単価)×80回 | → | 530×10円(地域単価)×80回 |
というような差異が明らかになります。
つまり月額にして82,400円も異なるのです。
これは仮に児童発達管理責任者の給与を月額30万円と仮定してみると、約三分の一弱もの額が算定されると分かります。
通常の放デイとの報酬単位の比較

通常の放課後等デイサービスの場合と比較してみましょう。
| 「共生型」+体制強化加算 | (大小) | 通常の放デイ(区分I) | 通常の放デイ(区分II) |
| 530 | > | 529 | 426 |
すると「共生型」の基本報酬単位が、通常の放課後等デイサービスの報酬単位より高くなっていることが分かります。
ただし、このような結論は、児童発達支援管理責任者を1人以上配置したという条件だからという点に留意ください。
仮に保育士を1名以上配置しても78単位の加算にしかならないので、通常の放課後等デイサービスの加算単位の方が多くなります。
従って「共生型」を採用した場合、通常の放課後等デイサービスより基本報酬の単位を上回るには、
児童発達支援管理責任者を1人以上配置する
必要があります。
戦略的なオススメの活用事例とは?
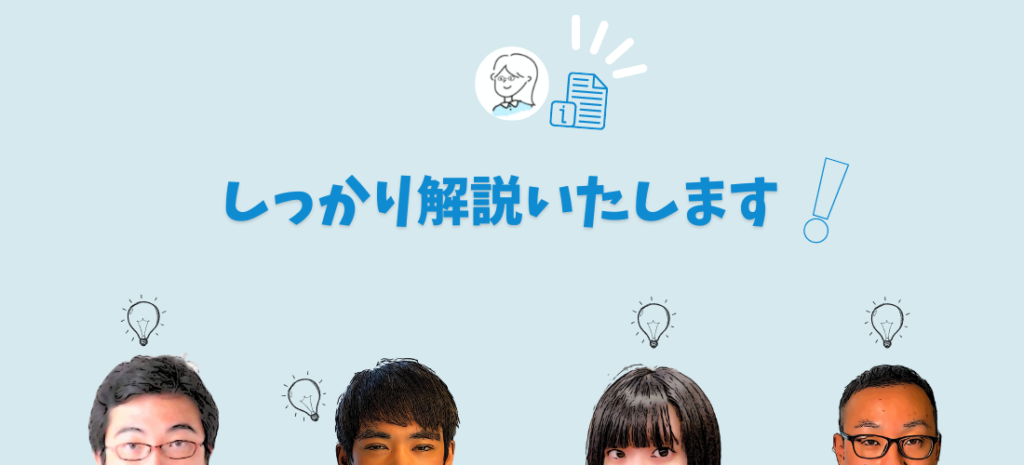
「共生型」の障がい福祉事業は、介護保険事業のスタッフや施設を転用して、障がい福祉サービスを担える点にありました。
ポイントは新たにスタッフを雇う必要もなく、施設も別に用意しなくていい点にあります。
けれども基本報酬単位を上げる「共生型サービス体制強化加算」を取得するには、介護保険事業に関係ない保育士等を雇う必要があります。
そこで気になるのは、
どのような条件に達すれば、「共生型サービス体制強化加算」を取得するメリットがあるのでしょうか?
という点でしょう。
そこで「共生型サービス体制強化加算」を戦略的に活用するオススメ事例を紹介いたします。
児童の5人以上の利用の需要があるか(目安)

「共生型サービス体制強化加算」の適用は、新たに介護事業所に保育関連のスタッフを雇用しなければなりません。
放課後等デイサービスに通う児童が1人につき12回も月に通う場合で計算すると、児発管を雇用しても黒字になるのは5人以上と考えられます
| (加算込みの基本報酬) | (児発管の経費) | |
| 5人×530(基本報酬単位)×10円(地域単価)×12回=318,000 | > | 300,000円 |
そして介護保険事業所側の人員配置で、利用者人数によって変動する配置数に注目いたしましょう。
そうすると仮に児童が5人から6人になった場合、既存の介護職員だけでは対応できませんが、そこはこの加算のための児発管の人員1人が担います。
つまりこの児発管の1人分がいることで、20名までの利用者に対応できるようになるのです(※定員数を変更します)。
すると仮に介護事業の利用者が10名に加え、放課後等デイサービスの利用者が10名になれば、
| (加算込みの基本報酬) | (児発管の経費) | |
| 5人×530(基本報酬単位)×10円(地域単価)×12回=636,000 | > | 300,000円 |
となり、月額にして大幅の黒字が見込めます。
反対に近隣地域で障がい児の需要が見込めない場合は、加算も取得せず、追加人員も雇わず、従来の「共生型」の対応で十分だということです。
ただ地域の障がい福祉の需要を戦略的に調べれば、現在の介護事業以上の事業規模に容易に達することができるのです。
地域に開かれた福祉事業の形成
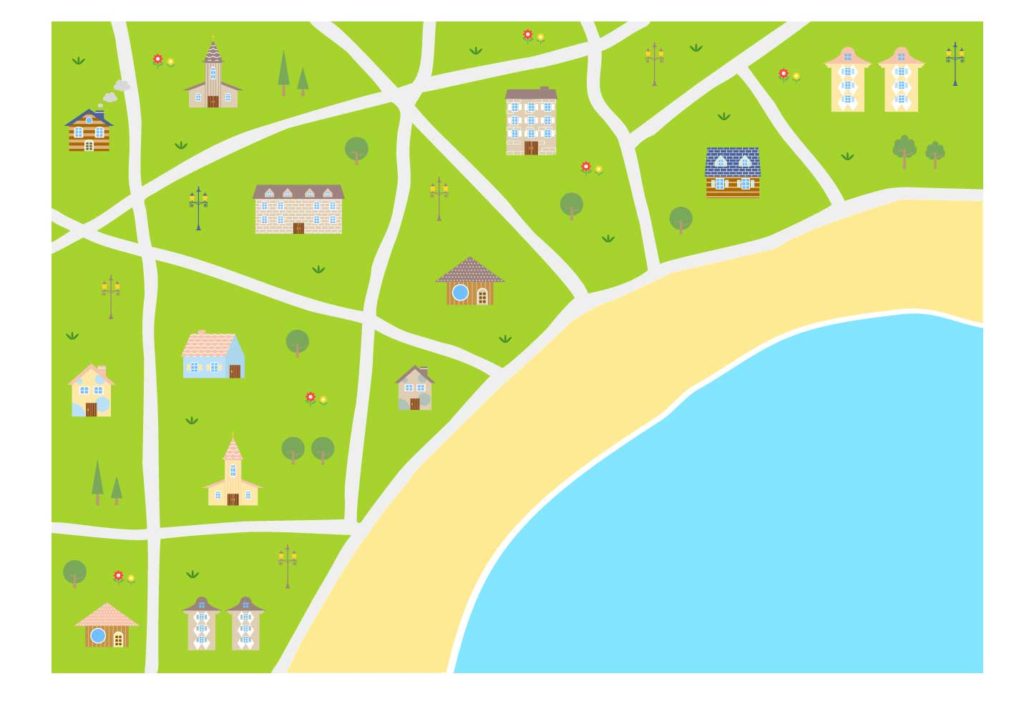
そもそも「共生型」として介護事業と障がい福祉事業を組み合わせる理念は、
・地域の需要に根ざして、限られた人材で福祉を維持し、
・年代により途切れることのないサービスを提供すること
にありました。
それゆえに「共生型サービス体制強化加算」を取得するために、「地域に貢献する活動をすること」という要件が課せられています。
「地域に貢献する活動をすること」とは、次のような活動です。
・地域の祭りへ参加
・健康関連や予防関連のイベントの開催
・子供食堂などを開催
これら課せられた要件を別の側面から考えれば、こうした地域活動の積み重ねが、
これまでの高齢者専門だった介護事業所から、世代を超えた地域福祉の拠点へと変わっていく契機
になるのです。
このような地域に貢献する活動に参加すれば、自ずと「共生型」の事業所の存在も認知され、利用者が増えていくきっかけにもなるでしょう。
それゆえに「共生型サービス体制強化加算」の要件を満たしていけば、着実に地域に開かれた福祉事業の新しい形が形成されていくのです。
まとめ:人件費とのバランス
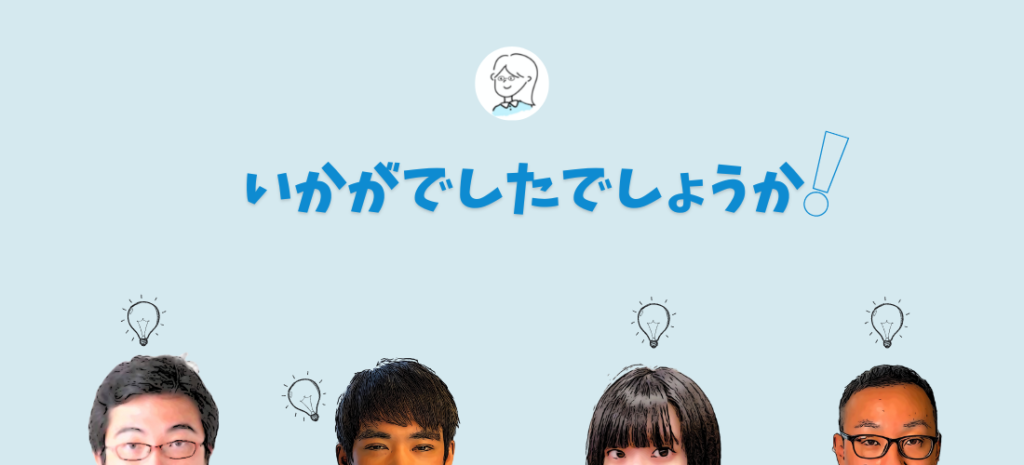
介護事業書の「共生型」障害福祉サービスにおいて、障害福祉専門の人材を雇えば事業は一層安定しますが、人件費がかかります。
ただ「共生型サービス体制強化加算」が取得でき、事業の収益にプラスになります。
それゆえ、「共生型サービス体制強化加算」を活用する際は雇用する人件費とのバランスに注意いたしましょう。
戸根行政書士事務所からのお知らせ
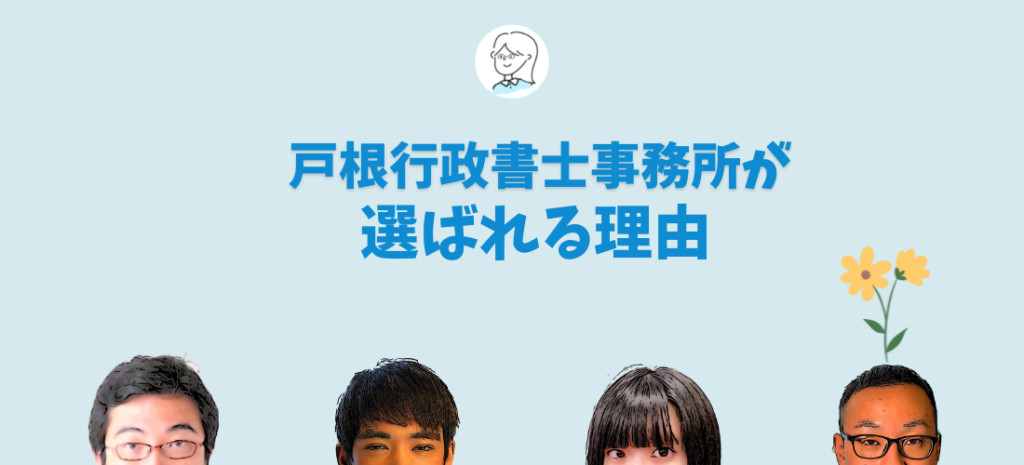
※まとめ:児発・放デイの相談支援系の加算の一覧
1 事業所内相談支援加算:事業所内で個別/グループに相談援助を行う(月に1回)
2 家庭連携加算:自宅訪問をして本人/家族に相談援助を行う(月に4回)
3 関係機関連携加算:関係機関と連携して相談援助を行う(月に1回)
<スタッフ配置のパターンを解説>
・【基本】これだけは覚えておきたい!児童系の人員配置の基本
・【基本】基準職員「営業時間を通じての配置」とは?
・【必見】児童系多機能型の人員配置について
・【確認】児童指導員等加配加算と適正なスタッフの配置について
<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ
<スタッフ配置に関する加算>
・【基本】児童指導員等加配加算とは?取得条件や注意点も解説
・【注意】児童指導員等加配加算と従業員シフト配置の可否について解説
・【確認】特別支援加算とは?条件やおすすめ活用法も解説
・【お勧め】専門的支援加算とは?条件や注意点も解説
<配慮を必要とする児童支援の加算>
・【新設】個別サポート加算とは?条件や注意点を解説
・【基本】「事業所内相談支援加算」とは?取得条件やミス防止もしっかり解説
・【基本】「家庭連携加算」とは?取得条件やミス防止もしっかり解説
・【基本】「関係機関連携加算」とは?取得条件や間違えやすいポイントも解説
・【応用】「強度行動障害児支援加算」とは?取得条件やトラブル事例も解説
<監査指導のトラブルにならないための対策>
・【注意】開所時間減算とは?ポイントや注意点を解説
・【注意】定員超過利用減算とは?条件や気を付ける点を解説
・【基本】延長支援加算について徹底解説!条件や注意点など
・【まとめ】放デイ特有の送迎加算とは?学校送迎の注意点も解説
・【注意】放デイ限定の欠席時対応加算とは?利用時間30分以内でもOK
・【基本】放デイの学校休日等の支援の注意点!トラブル回避のポイント
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
<実地指導のための対策>
・【基本】実地指導、ここがチェックされる!間違えない対策を解説
・【基本】実地指導、ここがチェックされる!②気になる論点の解説
<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり
・【注意】処遇改善加算等の社会保険料の計算の仕方とは?改善額の組み入れ
<事業所管理の健全化に努める>
・【基本】勤務体制一覧表の注意点は?間違えやすいシフト例も解説
・【注意】定員増加の注意点とは?報酬額や人員配置の問題解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】サービス提供時間の適正な設定とは?人件費や報酬単位とのバランス
<年度ごとの義務化への対応>
・【令和3年度】障害福祉のハラスメント防止の対策とは?運営規程の変更案
・【令和4年度】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説










































