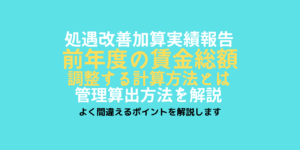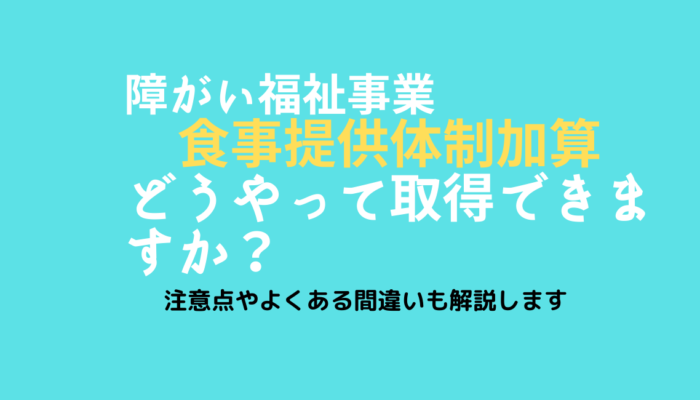

悩み
障がい者福祉事業を経営していて、朝から来てくれる利用者さんには昼食を提供したいと考えています。
ただ費用や人件費がかかるので、事業所にとって何か役に立つ加算はありますでしょうか?
障がい福祉サービス事業所で食事を提供しているところは利用者さんから人気があります。
お一人で食事することが難しい方には計画相談支援者も、食事提供がある事業所を探していることが多いです。
「利用者さんを胃袋で掴む」とも聞いたことがあるので、食事提供でつく加算があれば便利ですよね。
この記事では事業者様の理解の一助になるように以下のような内容がわかるように説明いたします。
- 「食事提供体制加算」の条件がわかります
- 「食事提供体制加算」の種類がわかり選びやすくなります
- 「食事提供体制加算」の算定における注意点がわかります
目次
- 1 食事提供体制加算とは?
- 2 食事提供体制加算の算定で気を付ける点
- 3 よくある質問
- 3.1 出前や市販のお弁当を購入し提供した場合は加算されますか?
- 3.2 一部外部の惣菜を購入して、その他を調理して提供する場合は加算の対象になりますか?
- 3.3 就労継続支援A型で調理された弁当を提供した場合は加算の対象になりますか?
- 3.4 「調理員等」は非常勤でも可能でしょうか?
- 3.5 「調理員等」は業務委託でも可能でしょうか?
- 3.6 生活指導員でも「調理員等」を兼業できますか?
- 3.7 利用者が事業所には来たが食事を取らなかった場合でも加算はできますか?
- 3.8 利用者が事業所を休んだ時は、食事を既に調理していても加算はできますか?
- 3.9 調理業務を受託している場合に営業許可は必要になりますか?
- 3.10 HACCP届出が必要のない食事提供回数に従業員への食事はカウントします?
- 3.11 調理員が配食しながら、他方で、調理や食事提供を利用者さんが関わる場合は算定できますか?
- 3.12 加算の届出をした時から委託業者が変更になった場合、再度加算の届出をする必要がありますか?
- 3.13 施設外就労を実施する際に、施設外先で食事を提供する場合、加算を取得できます?
- 3.14 施設外就労を実施する際に、事業所本体に戻って先食事を提供する場合、加算を取得できます?
- 4 まとめ
食事提供体制加算とは?
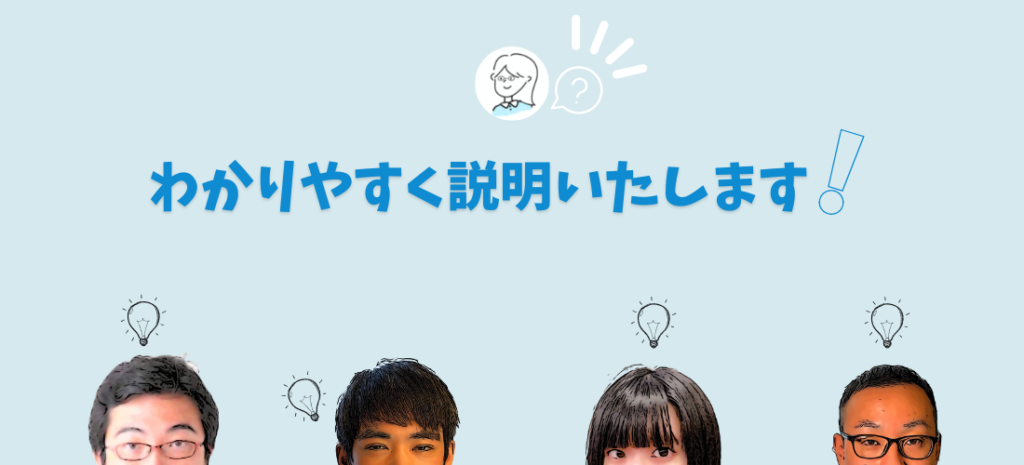
特に通所系の障がい福祉サービスでしたら出来る限り利用者さんに通所して欲しいので、まず「食事提供体制加算」を取得し昼食の準備を進めるのが重要です。
<食事提供体制加算とは?>
:特定の利用者(※受給者証に記載)に対して食事を提供できる体制を整えている時に1日につき所定の単位数をカウントします
※食事提供をできる特定の利用者とは?
・低所得者等であって就労の計画等により食事の提供を行うことになっている利用者
・低所得者等である利用者
「食事提供体制加算」は誰でも利用者に対して適用できると思っていたので違うとわかり驚きました。
加算の取得で自治体とトラブルになりたくないのですが、「食事提供体制加算」を取得する上でどのようなポイントに気をつければいいでしょうか?
「食事提供体制加算」は儲けるための加算ではなく、利用者支援を充実させ万全なサービス体制を築くためのものです。
食事提供という名前から安易に取得してしまうとトラブルになりかねません。
「食事提供体制加算」の取得の条件や注意点など説明していきますのでご参考になれば幸いです。
条件:調理員等を配置する

「食事提供体制加算」を算定するための条件は、勤務体制一覧表の中で「調理員等」を配置する必要があります。
<「調理員等」とは>
・管理栄養士
・栄養士
・調理師
・調理員
「調理員等」には他のサービス提供者を兼務させても問題はありません。
ただし「調理員等」の勤務時間は指定基準に必要な常勤換算の時間に含まれないのでご注意ください。
また「調理員等」は業務委託でも可能ですが、業務委託契約書の保管を忘れないようにしてください。
令和6年度報酬改定による追加条件
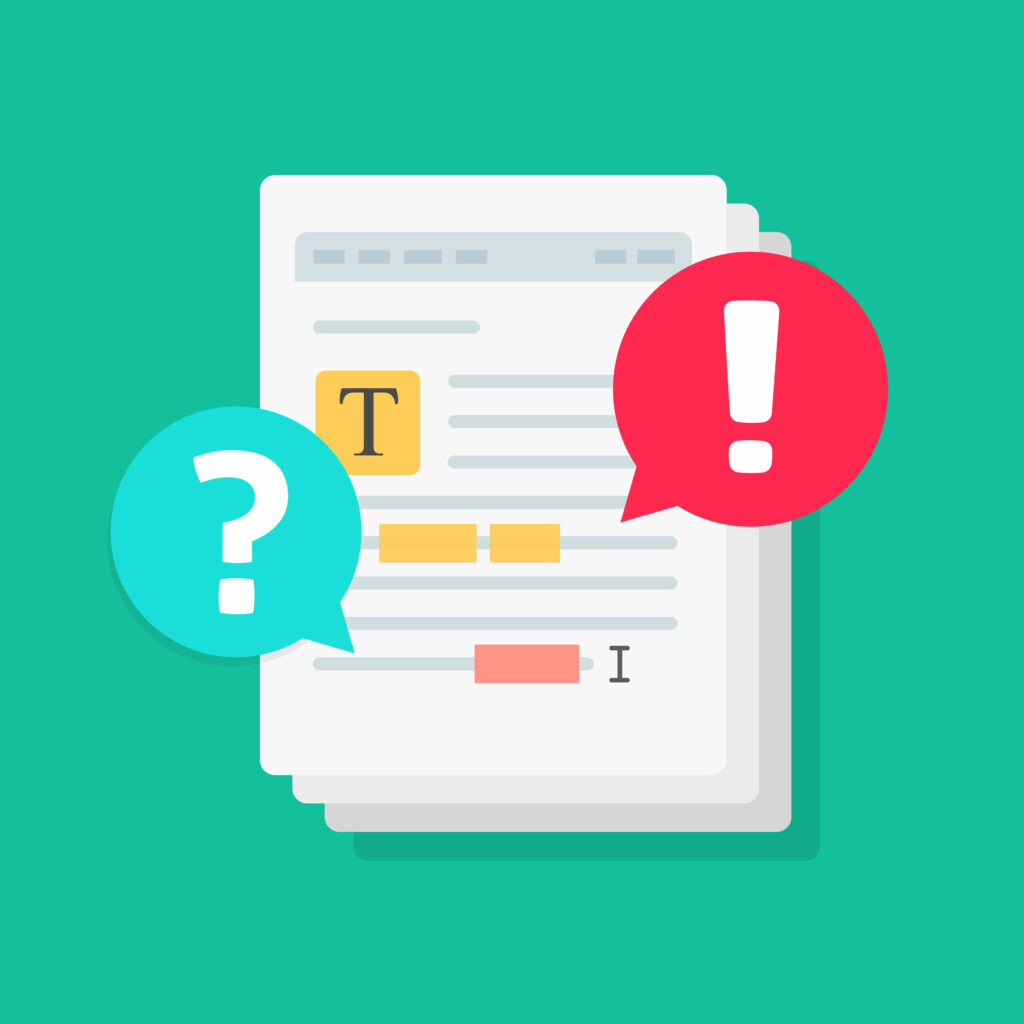
令和6年度の報酬改定により「食事提供体制加算」を算定するためには、①栄養面の保証/②利用者献立の摂取量の記録/③体重やBMIを6ヶ月に1度を実施しなければならなくなりました。
<令和6年度報酬改定による変更のポイント>
①栄養面の保証:栄養士等が献立作成に関わり、また栄養面の確認が必要になります
②利用者献立の摂取量の記録:どれくらい食べられたかサービス提供記録に書きましょう
③体重やBMIを6ヶ月に1度:フェイスシートに経過を記しましょう
※上記「①栄養面の保証」の栄養士の栄養面の確認について
・献立作成から関わることが望ましいとされていますが、確認だけでも問題ありません
・確認内容は、給与栄養目標量の達成度と、その内容を踏まえた献立になっているか
・確認対象は、毎日の実際の食事ではなくサイクルメニューでも認められます
・頻度は年に1回以上行う
(☝︎参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.5)
※上記「③体重やBMIを6ヶ月に1度」の確認留保について
・体重を知られたくないという利用者の意向があった場合は、体重やBMIの測定をしなくても良いです
・ただその利用者の意向があった旨を、個別支援記録等に書いておいてください。
令和6年度の報酬改定により「食事提供体制加算」を取得する条件がより厳しくなりました。
栄養士等による献立管理を開始するには時間がかかるので、急いで準備して証明書を発行してもらってください。
グループホーム等以外で体重の管理はあまり実施しないので、体重計の購入をして消毒にも気を使いましょう。
加算のパターン全解説

障がい福祉事業所で「食事提供体制加算」を算定するには、3つのパターンの中から適した1種類を選び自治体に届出を行う必要があります。
<パターン1:自ら作り→自ら提供>
食事提供体制が整備されている同一法人の他施設において調理され,当該施設に搬入されている場合
※自ら食事を提供する時の注意点
・調理員または利用者さんの衛生管理は徹底いたしましょう
・事業所ごとに衛生管理のマニュアルを作成し利用者さんに同意をもらいましょう
<パターン2:外部の人が作り→外部の人が提供>
調理業務を外部委託し,委託業者の調理員等が当該施設内の調理室において利用者のための食事を作り提供している場合
※業者委託の場合の注意点
・献立は事業所・施設がどれくらい関与するのか
・委託先からどのように運搬するのか
・食事の適時適温へどのように配慮するのか
<パターン3:外部で作り→自ら提供>
調理された食事を搬入し,利用者に提供している場合。ただしクックチル・クックフリーズ・真空パック等により解凍して提供するものに限ります。
※出前/市販の弁当は認められません。一部市販の惣菜を提供することは要確認ください。
例1:
クックチル,クックフリーズ,真空調理(真空パック)により,調理を行う過程において急速に冷却・冷凍したものを再度加熱して提供するもの(※3度以下で運搬し75度以上で1分間加熱して提供)。
例2:
クックサーブによる徹底した温度管理により速やかに提供するもの(※調理から喫食まで2時間を超えず中心温度は65度以上)。
よく間違えるポイントは出前や市販の弁当の提供では「食事提供体制加算」を取得できない点です。
「食事提供体制加算」を算定するには必ず1〜3のパターンのどれかに該当しないといけません。
そしてどの「食事提供体制加算」のパターンであっても最近は衛生管理の徹底が指摘されるので、事業所のスタッフ間でも気をつけておきましょう。
<「食事提供体制加算」を取得できない事例>
・出前の方法や市販の弁当を購入し、利用者に提供している場合
・利用者の行う生産活動の一環として作成された食事や弁当を利用者に提供されている場合
・外出行事で外食した場合
食事提供体制加算の算定で気を付ける点
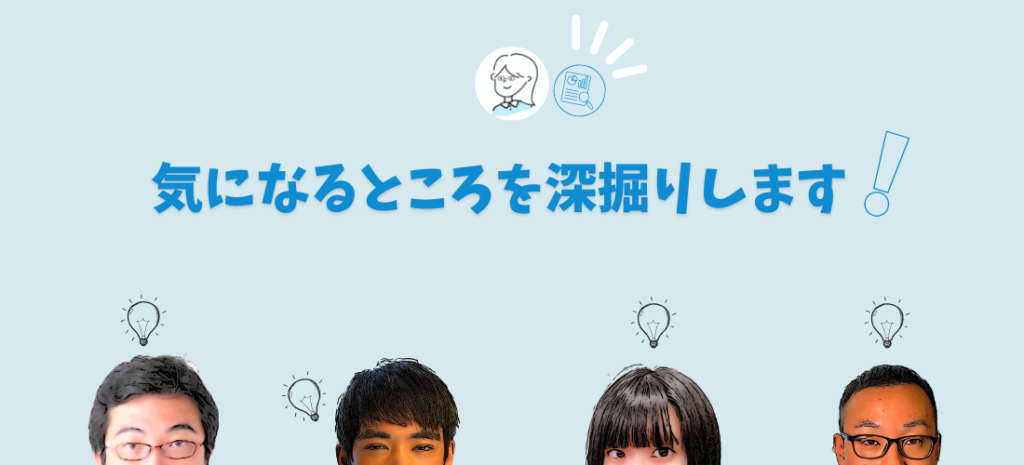
これまでの説明で「食事提供体制加算」の条件やパターンも理解してもらったかと思いますが、実はこの基本的情報だけでは加算の算定にてトラブルが発生するかもしれないのです。
<「食事提供体制加算」に対する自治体の指導>
食事提供体制加算を算定している時の食事の徴収や営業届出制度に関して実地指導の時に指摘が頻繁にあります。
条件とパターンの説明だけで「食事提供体制加算」のことを分かった気になっていたので、トラブルが頻繁に発生するとは驚きました。
「食事提供体制加算」を算定する時に実務上、どのようなポイントに気をつければいいか教えてもらえるでしょうか?
「食事提供体制加算」の算定で特に多いトラブルは利用者さんからの食費の徴収です。
誤った徴収の仕方で利用者さんの負担を増やしては大きな問題になってしまいます。
「食事提供体制加算」の取得時における食費の徴収の基本から、近年の法改正に対応した届出制度のことまで詳しく説明いたします。
加算額を除いた残りの食費のみ

「食事提供体制加算」を算定している場合の食費の徴収の基本は、食事の提供の費用のうち、加算額を差し引いた残りの食費のみを徴収することです。
<「食事提供体制加算の目的」>
低額所得者等への食事提供の人件費相当分を公費で負担することにあります。それゆえに人件費が加算相当額を上回る場合、その差を利用者に負担させることは認められません。
ただし利用者さんからのキャンセルがあった場合、その食費負担は契約書次第になるので、利用者負担でも問題ありません。
利用者さんとの間で食費に関してトラブルがないように、重要事項説明書で加算と費用の関係を説明しておくことが大切です。
食事の提供とHACCPの届出の関係

「食品衛生法等の一部を改正する法律」により全ての食品等事業者は,HACCPに沿った衛生管理を実施することにより、営業届出の制度が必要になります。
※障がい福祉サービス事業者も集団給食施設として対象になります。
<HACCP届出が必要でない例外とは?>
1回の提供食数が20食程度未満の場合には、「少数特定の者を対象とする給食施設」として届出は必要ではありません。
提供回数が20回未満でHACCPの届出が必要でなくても、自主的な衛生管理の徹底及び向上の努力は必要です。
ただ注意すべきは20回の提供の回数のカウントに職員への提供も含まれることです。
他にも調理業務を作業として受託している場合は営業許可を取っていないとトラブルになります。
個別支援計画等に位置付ける

「食事提供体制加算」に関する食事の提供は、障害福祉サービスの支援の一環なので、利用者への「個別支援計画」や「重要事項説明書」または「運営規程」や「サービス提供記録」の中で位置付けておきましょう。
<個別支援計画に記載する注意点>
・利用者の栄養状態に必要な食事を提供する
・食べられないものを分けて給仕し、食堂まで同行して連れてくる
・食べすぎないよう量を制限する
<重要事項説明書または運営規程に記載する注意点>
・食費について額を明示する
・食材費について額を明示する
<サービス提供記録に記載する注意点>
・当日に食事をして加算対象になったかどうか
・食事提供の有無はその都度、利用者に確認してもらう
・修正液や修正テープで修正することをしない
よく忘れがちなのが「食事提供体制加算」を取得する際に、個別支援計画の中に記すことです。
「食事提供体制加算」の算定対象となる方は公的に食事提供が必要と認められた方なので、その現状を踏まえて支援の一部として食事提供をするようにいたしましょう。
施設外就労の実施時の注意点について
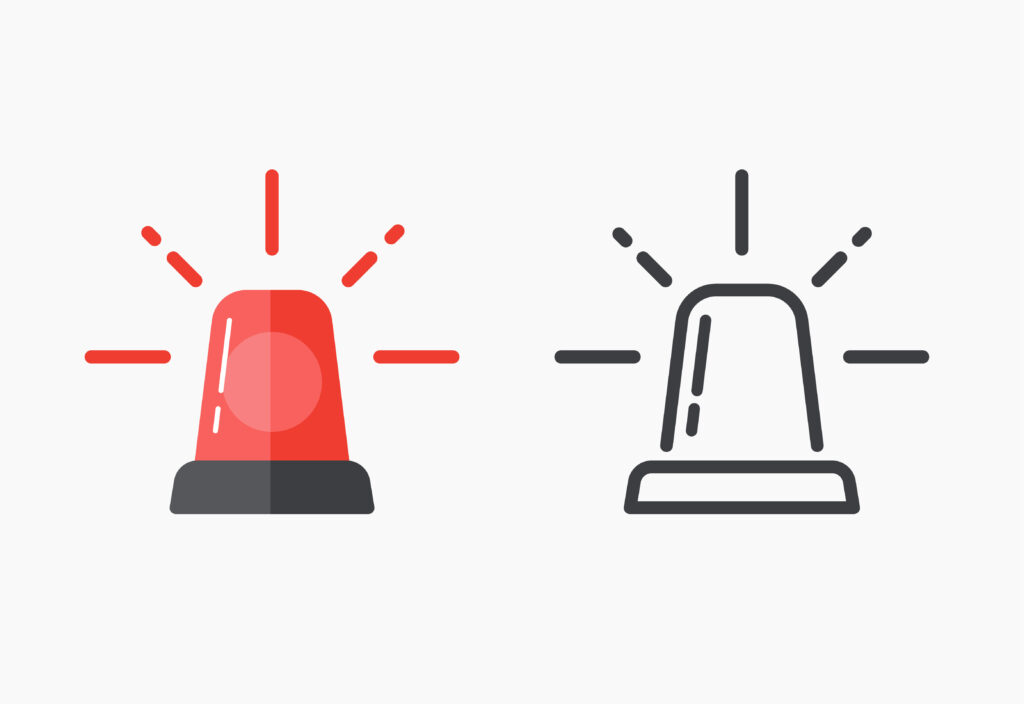
就労継続支援A型やB型で施設外就労を実施している場合でも「食事提供体制加算」を算定することは可能ですが、食事提供の場所や施設外先の設備や提供方法等により困難なケースがあるのでご注意ください。
<○:施設外先で「食事提供体制加算」が認められる場合>
・施設外就労者が事業所本体に戻ってきて食事提供する
・施設外先の会社の調理員の人件費を事業所が負担する
・施設外先の調理場等を事業所職員が使用して食事提供する
<✖️:施設外先で「食事提供体制加算」が認められない場合>
・施設外先の会社の調理員が食事提供をする(※事業所が人件費を負担しない場合)
・施設外先に事業所職員が使用できるキッチン等がない
就労継続支援A型B型では利用者さんの労働時間を稼ぎたいので、お昼の食事提供をした方が基本報酬単位が上がる可能性があります。
ただ売上に繋がりやすい施設外就労を実施する際は、どのように食事提供すれば加算として認められるか、施設外の委託先とよく相談することが大切です。
よくある質問

出前や市販のお弁当を購入し提供した場合は加算されますか?
答:できません。
一部外部の惣菜を購入して、その他を調理して提供する場合は加算の対象になりますか?
答:自治体によって異なるので要確認ください。
就労継続支援A型で調理された弁当を提供した場合は加算の対象になりますか?
答:加算の対象になる自治体もあるので要確認ください。
「調理員等」は非常勤でも可能でしょうか?
答:非常勤でも問題ありません。
「調理員等」は業務委託でも可能でしょうか?
答:業務委託でも問題ありません。
生活指導員でも「調理員等」を兼業できますか?
答:できます。ただし調理員として勤務する時間は、生活指導員としての常勤換算に含まれないのでご注意ください。
利用者が事業所には来たが食事を取らなかった場合でも加算はできますか?
答:できます。
利用者が事業所を休んだ時は、食事を既に調理していても加算はできますか?
答:できません。ただし利用者から食費を徴収できるかどうかは、利用者と事業所の契約によります。
調理業務を受託している場合に営業許可は必要になりますか?
答:営業許可は必要です。
HACCP届出が必要のない食事提供回数に従業員への食事はカウントします?
答:カウントいたします。
調理員が配食しながら、他方で、調理や食事提供を利用者さんが関わる場合は算定できますか?
答:算定することは出来ません。食事提供の対象にかかわらず利用者さんが関わった食事提供は算定対象になりません。訓練作業がレストランの調理でも、利用者さんが関われば加算は算定できません。
加算の届出をした時から委託業者が変更になった場合、再度加算の届出をする必要がありますか?
答:再度、加算の届出をする必要はありません。
施設外就労を実施する際に、施設外先で食事を提供する場合、加算を取得できます?
答:請負契約において就労支援事業者がキッチン等を利用できる旨の記述があるれば取得可能です。食事提供を第三者に委託する場合はその人件費を事業所が支払えば加算の算定は可能です。
施設外就労を実施する際に、事業所本体に戻って先食事を提供する場合、加算を取得できます?
答:加算を取得することができます。
まとめ
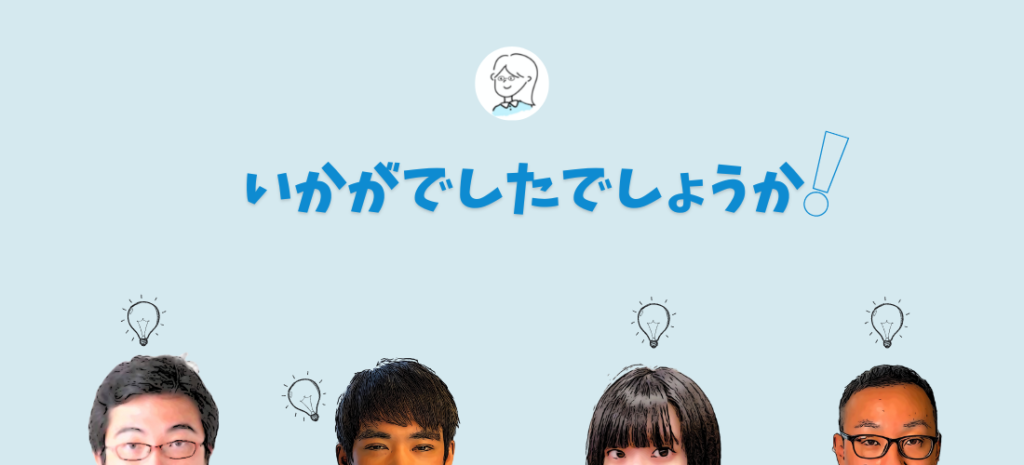
本日は「食事提供体制加算」の条件から実務上の注意点までしっかりと理解することができました。ありがとうございます。
事業所で昼食を出すことは利用者集めの基本なので、しっかりと準備し「食事提供体制加算」を算定したいと思います。
「食事提供体制加算」を取得するにはまず3つのパターンから、利用者さんの様子や事業所の余裕を考慮して適切なパターンを選びましょう。。
弊所の経験では、負担が少なく安価なのでパターン3のクックフリーズで食事を提供される事業所さんが多い印象です。
「食事提供体制加算」の届出には業務委託契約書や運営規程も必要になるので意外と時間がかかるので、余裕を持って準備しましょう。
戸根行政書士事務所からのお知らせ
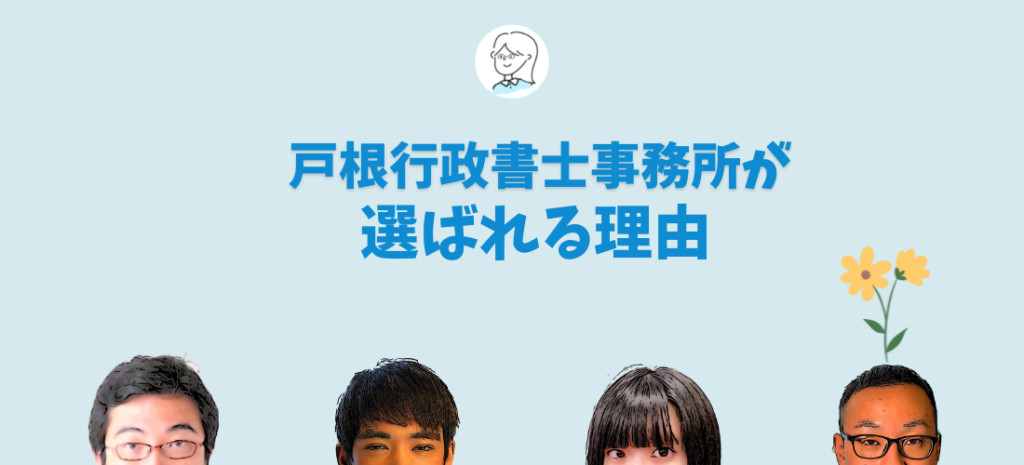
<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ
・【まとめ】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から注意点まで解説
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
<減算について>
・【基本】人員欠如の減算とは?計算方法や注意点も解説
・【詳解】人員欠如の減算:基準や緊急対応・防止策をご説明
・【詳解】サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算とは?
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題点と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【必見】就労支援事業会計とは?会計区分や按分処理のポイント解説
・【注意】就労支援事業の積立金とは?余剰金を発生させない会計処理
・【注意】サービス管理責任者の更新研修の条件とは?
・【基本】サービス管理責任者の実務経験おすすめルートとは?
・【基本】「一体型」と「多機能型」の違いとは?事業拡大のチャンス!
・【大注目】令和5年サービス管理責任者の実務経験が6ヶ月に変更!
・【大注目】令和5年サービス管理責任者不在の猶予期間が2年に!
<工賃上昇のための体制づくり>
・【高収入】施設外就労支援の注意点とは?基本から間違えやすいミスまで説明
・【推奨】就労移行連携加算とは?オススメ活用事例あり
・【注目】就労移行支援体制加算とは?オススメ活用事例あり
・【注目】就労継続支援事業所に計画相談支援事業所を併設して収益アップ!
<工賃支払いを適正に管理する>
・【基本】就労継続支援B型:工賃支払いの注意点は?月ごとの手続き解説
<現状に応じた適切な事業所体制を作る>
・【基本】平均工賃月額の計算の仕方は?解説と注意点とは
・【重度】「重度者支援体制加算」とは?よくある間違いも解説
<工賃支払以外の参加・共感型の新体制を目指す>
・【令和3年】ピアサポート体制・実施加算とは?オススメ活用事例あり
・【令和3年】地域協働加算とは?オススメ活用事例あり
<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
・【義務化】身体拘束適正化委員会と「身体拘束廃止未実施減算」とは
<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援A型編>
・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説
・実地指導、ここがチェックされる②!間違えやすいポイント解説
<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援B型編>
・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説