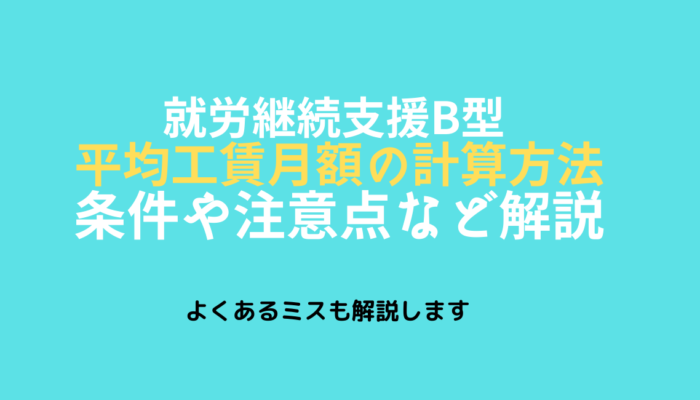
★★★記事執筆者のご紹介★★★
この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております。多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました。
戸根行政書士事務所のプロフィールはこちらですので、よろしければ弊社の支援方針や独自の強みなどご覧ください。

就労継続支援B型を運営しているのですが、実績が1年できたので基本報酬算定区分を変更しようと思いますが計算が難しいです。
もし間違えた区分を選んでしまうと返金するかもしれず怖いです。
そこで基本報酬算定区分を求めるために必要な平均工賃月額の計算の仕方を教えてもらえるでしょうか?
就労継続支援B型で基本報酬単価を上げるには平均工賃月額を上げることが近道です。
平均工賃月額の計算は難しくありませんが、計算のデータを日々適切に把握するにはコツがあります。
この記事では事業者様の理解の一助になるように平均工賃月額に関して以下のような内容がわかるように説明いたします。
- 平均月額工賃の計算方法が基本からわかります
- 平均月額工賃の計算における注意点がわかります
- 平均月額工賃の疑問や不安が解消される
<※令和3年度の報酬改定から基本報酬単位を平均工賃以外から決めるパターンもあります>
・【新制度】ピアサポート体制・実施加算とは?オススメ活用事例あり
・【新制度】地域協働加算とは?オススメ活用事例あり
目次
平均工賃月額の計算の仕方とは?
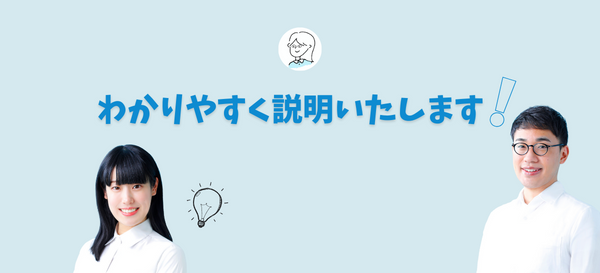
就労継続支援B型の事業所の1年間の基本報酬は、前年度の平均工賃額によって変わり、利用者さんへ支払う平均工賃月額が高ければ、それに連動して基本報酬単価も高くなる仕組みです。
※基本報酬の選択を(I)または(II)を選んだ場合です。
<「平均工賃月額」の計算上の注意点>
・基本的には、「年間の支払工賃額の合計額」 ÷ 「年間の平均利用者数(=年間総利用者数÷年間総開所日数)/小数点第二位切り上げ」÷12ヶ月で計算します(←令和6年報酬改定変更点です)。
・開業年度または1年実績のない2年度目は「1万円未満」のカテゴリーで算定します(※半年実績で1万円を超える場合は届出をすれば実績で請求できます)。
・重度者支援体制加算(I)を算定している場合は、算出した平均工賃月額に2千円を加えた額で基本報酬単位を決めることができます。
・原材料の高騰等で8割の事業所の工賃実績が低下した場合は前々年度で基本報酬を決めることができます。
・施設外就労を実施している場合はその実績と人数も入れてください。
<「平均工賃月額」の算出期間の数え方について>
かたや「サービス提供月の連続した12ヶ月」(4〜3月)でも、また「支払い月の連続した12ヶ月」(5〜4月)でも、どちらを選択しても問題はありません。
平均月額工賃の計算はよくわかるのですが、この「支払工賃額の合計」にお渡し分をどこまで含めるのか悩んでしまいます。
また「対象者数」ですが、例えば入院した利用者さんの扱いなど分かりません。平均工賃月額の計算の具体的な注意点も教えてもらえるでしょうか?
平均工賃月額の計算はシンプルですが、それ故に時に間違えてしまい、過大な又は過小な基本報酬単位で請求してしまうトラブルが生まれます。
総工賃の計算や対象者の特定にも失敗しやすいポイントがあります。
以下では具体的な例を示しつつ平均工賃月額についてわかりやすく説明いたします。
1年の総工賃額を間違えない

平均工賃月額を計算するには1年の総工賃額を求めることは勿論、計算ミスなく必要な額を選んできて合計することが大切です。
<年間の支払工賃額の合計額とは>
同意を得た工賃規定に基づき、正しく計算した工賃の支払い合計額のことを言います
<※よくある間違い>
・工賃規定に同意を得ずに不適切に計算して支払っていた
・生活費を工賃に含めていた
・工賃明細書の額と支払額が一致していなかった
・皆勤賞など特別な金銭の授与を含めていた
年間の支払工賃の合計の算出ですが、意外と計算ミスがあり、自治体から指摘された例も伺います。
特に工賃以外のものを工賃と見なしていた場合、基本報酬単位を上げるために虚偽の記載をしたと疑われるのでご注意ください。
エクセルで計算する場合は打ち間違えに気づかないこともあるのでお気をつけいただければと思います。
分母の前年度平均利用者を正しく計算する

平均工賃月額を算定するには、令和6年度の報酬改定により前年度平均利用者数を求めるだけで良くなり、月毎の工賃支払い者の合計を計算する必要がなくなりました。
※低い工賃額の者が1人増えるだけで全体の平均はガクンと下がってしまいます
<前年度平均利用者数の求め方>
・4月から3月の間に利用者が通所した全ての回数(=A)を計算いたします(※在宅支援も含みます/施設外は含みません)
↓
・4月から3月の間に事業所を開所した日数(=B)を計算いたします(※台風等で閉所した日やレクリエーションの日など生産活動を実施しない日は入れません)
↓
・上記 A ÷ B = 前年度平均利用者数
↓
・年間工賃支払総額 ÷ 前年度平均利用者数 ÷ 12ヶ月 = 平均工賃月額
※前年度平均利用者数の計算例
・4月340回/5月370回/6月433回/7月411回/8月399回/9月432回/10月340回/11月370回/12月433回/1月411回/2月399回/3月432回⇨全て足すと4770回(=A)
↓
・4月20日/5月20日/6月20日/7月20日/8月20日/9月20日/10月20日/11月20日/12月20日/1月20日/2月20日/3月20日⇨全て足すと240日(=B)を計算いたします
↓
・上記 A ÷ B ⇨ A4770÷ B240 =19.875人(→19.9人/小数点第二位切り上げ)
平均工賃月額を算定する計算に、前年度平均利用者数を正確に計算することが大切です。
特に間違えやすいのは施設外の人数を入れてしまい、実態以上の平均利用者数を算定してしまうことです。
他方で在宅支援をする利用者の数は前年度平均利用者数に入れるので注意いたしましょう。
<支払対象利用者について>
※令和5年度までの考え方です
1ヶ月間サービス利用の契約をしていて定期的に通所している利用者さんのことです
※低い工賃額の者が1人増えるだけで全体の平均はガクンと下がってしまいます
<支払対象の利用者にならない事例1(非病気)>
※令和5年度までの考え方です
・月の途中において、利用の開始または終了した者(※工賃の支払い総額からも除きます)
<支払対象の利用者にならない事例2(病気)>
※令和5年度までの考え方です
・初めから毎週1回以上(※通年)通院する必要がある方
・サービス利用途中に毎週1回以上(※通年)通院する必要が生じた方
・月の途中で通院/退院することになった方
・全治1ヶ月以上のケガで連続して1ヶ月以上利用できなくなった方
・インフルエンザやコロナウイルスで連続して1ヶ月以上利用できなくなった方
平均工賃月額の計算方法の注意点と対策とは?

就労継続支援B型の基本報酬単位を的確に算定するポイントは、工賃額を間違いなく月毎に把握しておき、計算対象にあたる利用者を月毎にピックアップしておく点です。
<平均工賃月額を適正に計算するための書類>
・工賃規定
・工賃明細書
・利用者一覧表
基本報酬単位を適正に設定して運営するには、平均工賃月額を算定するための準備を常にしておく必要があると思います。
平均工賃月額を算定するための書類や管理のポイントを教えてもらえるでしょうか?
平均工賃月額を適正に計算するためには、日頃から書類を適正に整えておくことが肝心です。。
工賃規定/工賃明細書/利用者一覧など必要な書類を日毎から管理しておくと、平均工賃月額の計算を間違うことなくすることができます。
それではこれから平均工賃月額を間違えないように算定するポイントをご説明します。
工賃規程と工賃明細書を整える

平均工賃月額を適正に算定するには、工賃規定に記された計算方法に即して、工賃明細書と数字を合わす工夫をしておくと安心です。
| (利用者名) | (時間数) | (工賃単位) | (工賃額) |
| Aさん | 20 | 500 | 10,000 |
| Bさん | 15 | 600 | 90,00 |
| Cさん | 25 | 700 | 17,500 |
<気をつけるポイント>
・利用者によって工賃額を変える場合は合理的な理由を用意いたしましょう(※同意をもらってください)
・お一人ごとの月額工賃総額を求める時は計算式を簡明にいたしましょう
できれば月毎の支払工賃の額と利用者一覧は一つのファイルにまとめると計算ミスが少なくなります。
利用者さんにお渡しする工賃明細書にも支払額の根拠が明確になっていれば安心です。手書きのメモやバラバラの明細書だけで管理していると計算ミスや数え忘れがあるのでご注意ください。
前年度平均利用者数を間違いなえないポイント

令和6年度報酬改定より平均月額工賃を計算するための前年度平均利用者数を正しく算出するため、特に施設外就労の利用者の取り扱いについて間違いが多く注意が必要です。
<前年平均利用者数と「施設外就労の利用者」の関係>
・施設外就労を1日中行った利用者は前年平均利用者数の計算に入れません
・施設外就労を行うと同時に、同日のどこかで事業所本体でも両方作業した利用者は前年平均利用者数の計算に入れます
<「施設外就労の利用者」を把握しやすい書類整理>
・業務日誌やサービス提供記録で当日は誰が施設外に出たのか明白にいたしましょう
・施設外就労を行った時間数を何時から何時までか記し、本当に戻って作業した有無を忘れずに残しましょう
施設外就労の労働者を平均利用者数に加えてしまい、必要以上に前年度平均利用者数が多くなったミスをを時々伺います。
1日施設外就労を行い利用者は計算に入れませんが、数時間でも本体で作業した利用者は前年度平均利用数の計算に入れるのでご注意ください。
毎月ルーティンとして本体平均利用者数と施設外利用者数を分けて計算する習慣をつけましょう。
まとめ
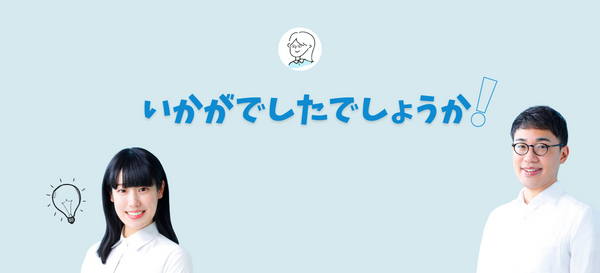
就労継続支援B型の基本報酬単位を算定するための平均工賃月額について、詳しく計算の仕方から説明していただきありがとうございました。
正しく平均工賃月額を計算をするためにしっかり記録を整えることの大事さを理解することができました。ありがとうございます。
平均工賃月額は基本的に就労継続支援B型の基本報酬単位を決め、それ以降の毎日の基本サービスの給付額に影響する重要なポイントです。
ですが意外と平均工賃月額の計算を間違えることもあるので、どのような手順で何に気をつければ良いのか改めてご確認ください。。
忙しいと計算ミスも起こるので平均工賃月額は出来れば複数人で計算していただけると安心です。
戸根行政書士事務所からのお知らせ

<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ
・【まとめ】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から注意点まで解説
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
<減算について>
・【基本】人員欠如の減算とは?計算方法や注意点も解説
・【詳解】人員欠如の減算:基準や緊急対応・防止策をご説明
・【詳解】サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算とは?
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題点と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【必見】就労支援事業会計とは?会計区分や按分処理のポイント解説
・【注意】就労支援事業の積立金とは?余剰金を発生させない会計処理
・【注意】サービス管理責任者の更新研修の条件とは?
・【基本】サービス管理責任者の実務経験おすすめルートとは?
・【基本】「一体型」と「多機能型」の違いとは?事業拡大のチャンス!
・【大注目】令和5年サービス管理責任者の実務経験が6ヶ月に変更!
・【大注目】令和5年サービス管理責任者不在の猶予期間が2年に!
<工賃上昇のための体制づくり>
・【高収入】施設外就労支援の注意点とは?基本から間違えやすいミスまで説明
・【推奨】就労移行連携加算とは?オススメ活用事例あり
・【注目】就労移行支援体制加算とは?オススメ活用事例あり
・【注目】就労継続支援事業所に計画相談支援事業所を併設して収益アップ!
<工賃支払いを適正に管理する>
・【基本】就労継続支援B型:工賃支払いの注意点は?月ごとの手続き解説
<現状に応じた適切な事業所体制を作る>
・【基本】平均工賃月額の計算の仕方は?解説と注意点とは
・【重度】「重度者支援体制加算」とは?よくある間違いも解説
<工賃支払以外の参加・共感型の新体制を目指す>
・【令和3年】ピアサポート体制・実施加算とは?オススメ活用事例あり
・【令和3年】地域協働加算とは?オススメ活用事例あり
<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
・【義務化】身体拘束適正化委員会と「身体拘束廃止未実施減算」とは
<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援A型編>
・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説
・実地指導、ここがチェックされる②!間違えやすいポイント解説
<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援B型編>
・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説













































