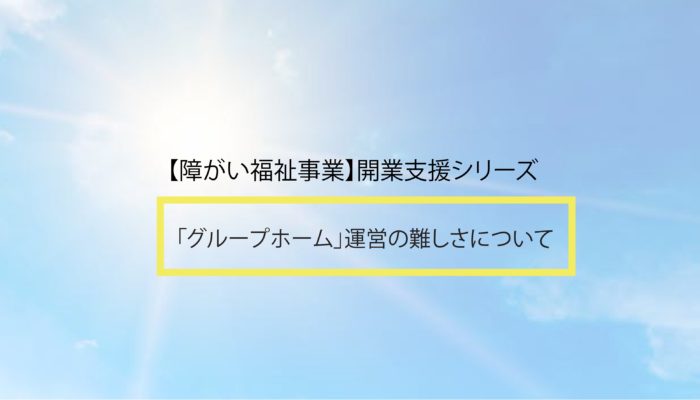
障がい福祉事業の中でグループホーム運営はどこが難しいでしょうか?
近年は障がい福祉事業の中で、「共同生活援助」(=「グループホーム」)が注目を集めてきました
グループホームは国による給付で成り立っていて潰れず、潜在的なニーズもあるので「グループホーム」は儲かるなど言われることもあります。
しかし「グループホーム」の運営上の難点を知らずに開業してしまうと大変なリスクを抱えてしまいます。
そこで本日は「グループホーム」運営の一般的な難しさについて簡単にご紹介いたします。
グループホーム経営の難しさとは

従業員が定着しない

グループホームは基本的に泊まり勤務の場合も多く、夜間の仕事も少なくありません。
グループホーム利用者は障がいをお持ちの方なので、夜中に行動したり、騒音を立てて隣人とトラブルを起こすことなどもあり得ます。
しかし民間の事業とは違って、こうした障がい福祉のグループホームは、必要なスタッフが足りない場合、国からの給付を減らされてしまいます。
またこのような労働環境の厳しさから、講習受講などによる従業員の能力向上の機会が失われる危険もあります。
共同生活に慣れない利用者さまのお世話
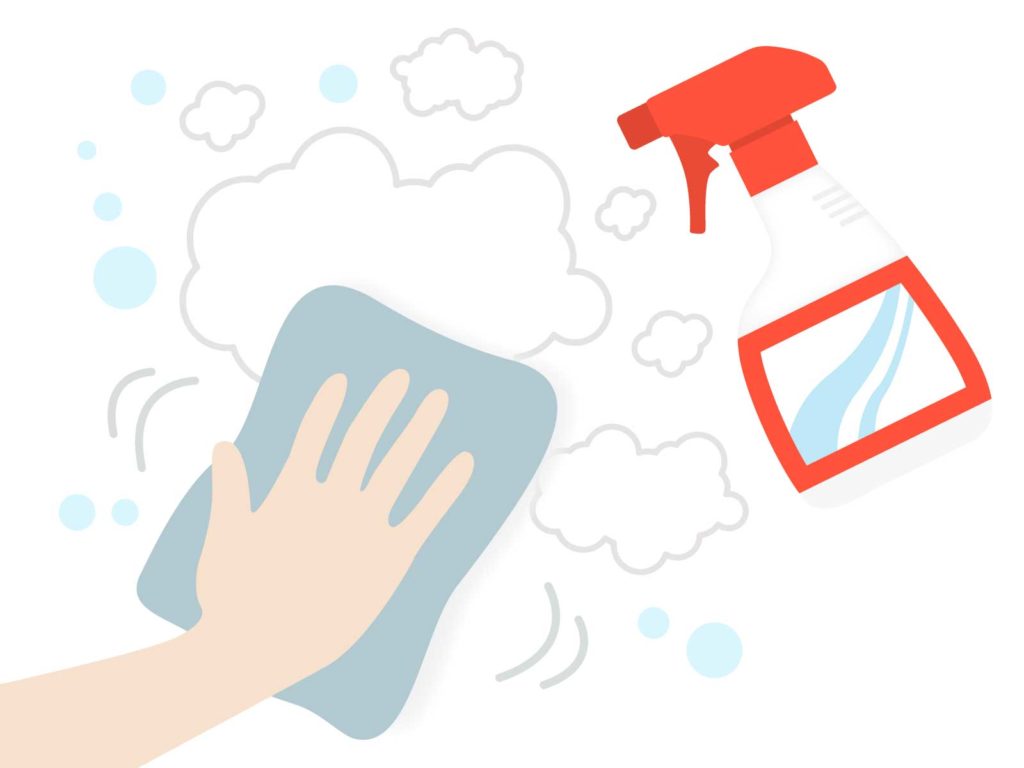
グループホームの利用者さまは日常生活丸ごとの支援が必要だからという理由で入ってこられることもありますが、共同生活が苦手な方も少なくありません。
またスタッフに対しても自分への扱いが乱暴だと怒って暴れ、場合によっては行政などに通告され大きなトラブルに発展する可能性もあります。
利用者さまの金銭管理

グループホームでは利用者さまの日常用品の購入は、お預かりしたお金から支払うことが少なくありません。
・また事業所側では適正に処理していると思っても、例えば保護者やご家族への報告が不十分であった場合、利用者の支援者との間で諍い事に発展しがちです。
グループホーム含め障がい福祉事業は行政の指導の下、国の給付によって成り立っているので、たとえ何の落ち度がなくても、誤解であれ行政に通報されると、「実地指導」などの時に厳しい対応をされることもあります。
おわりに
・「グループホーム」は共同生活する利用者さまの扱いが難しい
戸根行政書士事務所からのお知らせ
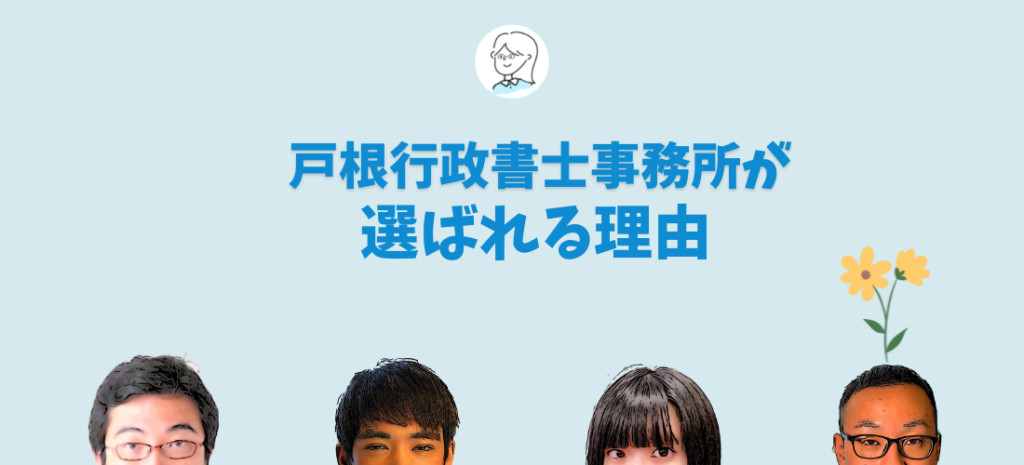
<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ
・【まとめ】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から注意点まで解説
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
<減算について>
・【基本】人員欠如の減算とは?計算方法や注意点も解説
・【詳解】人員欠如の減算:基準や緊急対応・防止策をご説明
・【詳解】サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算とは?
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題点と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
<夜間支援の加算等>
・【基本】夜勤職員加配加算の要件とは?注意点やオススメ活用事例あり
・【基本】重度障害者支援加算とは?注意点や活用事例あり
・【最新版】夜間支援等体制加算とは?注意点・活用事例も紹介
・【注意】グループホームの夜間支援体制のスタッフ配置:注意点も解説
・【要点】「夜間支援等体制加算」の利用者数の計算とは?
<医療/入院関係の加算等>
・【基本】看護職員配置加算とは?要件・活用事例も解説
・【基本】医療連携体制加算とは?要件・注意点・おすすめ活用も解説
・【注意点】個人単位で居宅介護は利用できるの?要件や注意点を説明
・【基本】強度行動障害者体験利用加算とは?取得条件や活用事例も紹介
・【基本】長期入院時支援特別加算とは?基準や注意点を解説
・【基本】入院時支援特別加算とは?基準や注意点を解説
・【基本】医療的ケア対応支援加算とは?加算条件や活用方法も解説
・【基本】「帰宅時支援加算」とは?取得条件や間違えやすいポイントを解説
・【基本】「長期帰宅時支援加算」とは?取得条件や間違えやすい点を解説
・【基本】「地域生活移行個別支援特別加算」とは?取得条件や活用法を解説
<利用者さんとのトラブルを避ける対策>
・【まず知りたい】グループホーム運営は何が難しいの?
・【注意】グループホーム利用者との金銭トラブルについて
・【質問】「通院時も付き合って欲しい」と言われたら?通院支援の対策を解説
・【注意】グループホームの費用設定はどのように?利用者負担も解説
・【基本】グループホーム体験利用の注意点とは?利用者負担の設定に留意
<実地指導のトラブルにならないための対策>
・【まず知りたい】実地指導とは?チェックリストもお教えします
・【直前対策】実地指導を受ける時の対応の注意点!
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【トラブル多発】グループホームの土日祝の支援とは?基本や注意点も解説
・【よく間違える】日中支援加算とは?基準や注意点を解説
・【基本】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から徹底解説
・【注意】生活支援員を外部業者に委託する際の注意点とは?
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【注意】大規模住居等減算とは?あえて減算になるメリットも解説
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】サービス管理責任者を配置する注意点とは?間違いやすい例も解説
・【注目】生活支援員の配置の注意点とは?外部の業務委託も解説
・【基本】勤務体制一覧表の注意点は?間違えやすいシフト例も解説
・【注意】定員増加の注意点とは?報酬額や人員配置の問題解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】障害者グループホームに短期入所を併設して収益を上げる方法とは?
<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり
・【注意】処遇改善加算等の社会保険料の計算の仕方とは?改善額の組み入れ










































