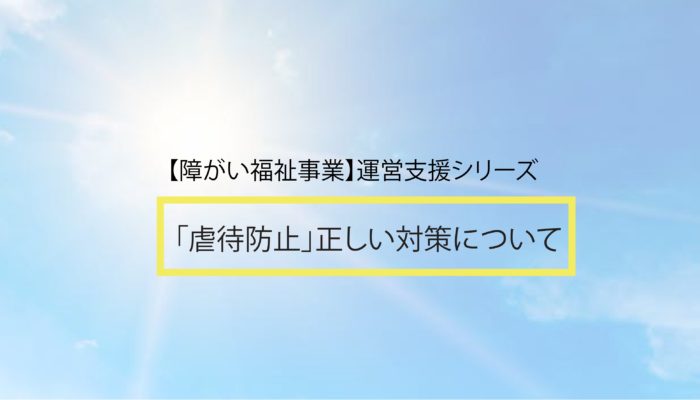
最近、行政から最も注意が求められるのは「虐待防止」ですが、その正しい対策とは?
近年、障がい福祉事業所における虐待事件のニュースが絶えません。
「虐待防止」は法律上、防止の措置が義務付けられていますが、対策不足の事業所のトラブルを多く見かけます。
これまで事業所さまからの依頼で行政による「実地指導」にだけ立ち会った時でも、「虐待防止」対策のミスを指摘される様子をお見かけいたしました。
そのような行政書士としての経験を活かし、適切な「虐待防止」の対策をご説明いたします。
目次
「虐待防止」の適切な対策とは
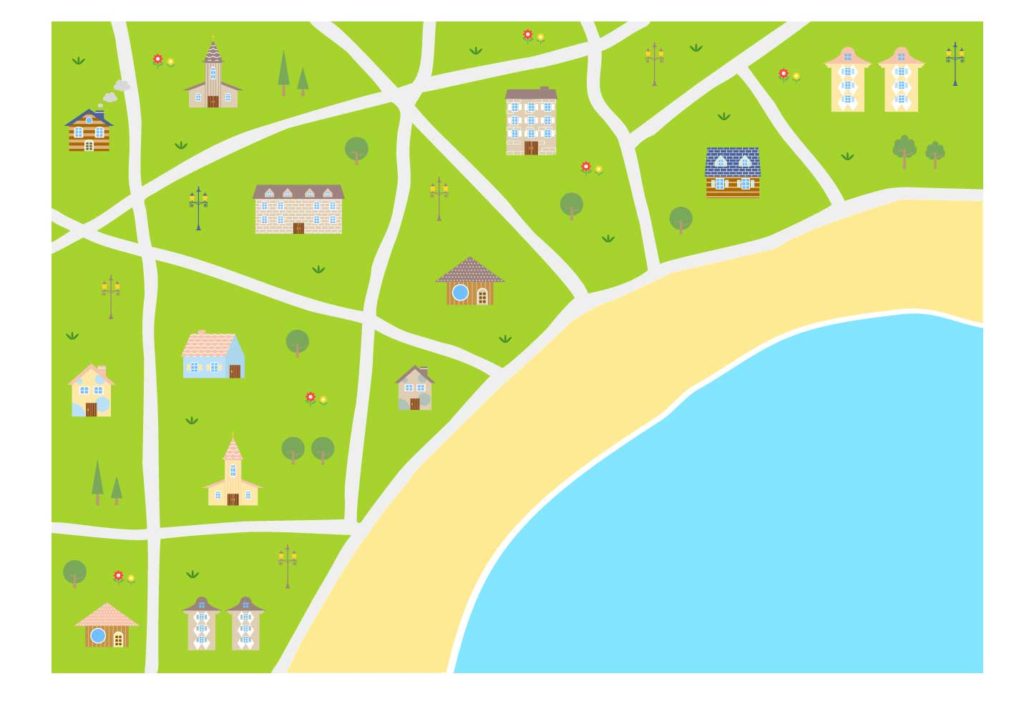
責任者・解決者の明確化
障がい福祉事業所ごとに、「虐待防止」の責任者と解決者を定めましょう。
そして「虐待防止」専用の窓口を設定し、電話番号等を記します。
こうした事業所ごとの「虐待防止」体制の徹底を利用契約書に記し、利用者さまに説明いたします。
マニュアルの作成と周知
障がい福祉事業所ごとに、「虐待防止」のマニュアルを作成いたしましょう。
そしてその「虐待防止」のマニュアルを利用者の手の届くところに設置し、また壁などに要旨を掲示するようにいたしましょう。
従業員の意識の徹底
障がい福祉事業所ごとに、少なくとも年に1回は、「虐待防止」の研修を従業員向けに行いましょう。
そうした研修の記録を作成し保存しておくことは「実地指導」でも有効です。
「虐待」の学びは様々な事例を通して初めて理解できるので、外部講師を活用するのも有効です。
適正なアセスメント の実施
障がい福祉事業所ごとに、個別支援計画を作成する時に、利用者の心身の状態を細かく聞き取り、その人の傾向などを把握するようにいたしましょう。
そして従業員の間で支援者会議を適時開催し、「利用者一人ひとりの特徴を共有する体制」を作りましょう。
開かれた情報発信
障がい福祉事業所ごとにホームページやSNSなどで、どのような日々の支援を行い、どのようなスタッフがいるのか情報発信をしましょう。
「いつも不特定多数の人に見られている」という従業員の意識は「虐待防止」のために有効です。
従業員用の相談体制の構築
障がい福祉事業所の従業員が気軽に利用できる相談体制を作りましょう。
「虐待」は支援者本人が気づかない内に発生していることも頻繁にあります。
「虐待行為」に自分で気付いたり、また同僚の目から見てきになることがあれば、「迅速にトラブルを発見できる体制」を整えましょう。
苦情相談の記録
事業所ごとに、少なくとも月に1度、苦情相談などの記録をつけるようにいたしましょう。
ほんの少しのトラブルでも「苦情相談」として記録に残し、それへの対応を迅速に行い、少しでも早期に「虐待」に発展する可能性を潰しましょう。
「虐待行為」の分類

障がい者虐待防止法
②性的虐待:わいせつな発言、トイレ等を覗く又は撮影
③心理的虐待:怒鳴る、悪口、侮辱
④放棄・放置:汚れた服を着せる、掃除しない、虐待を無視
⑤経済的虐待:日常生活に必要な金銭を渡さない
刑法
②性的虐待: わいせつ罪、強制性交等罪等、監護者性交等罪
③心理的虐待:脅迫罪、強要罪、名誉毀損罪、侮辱罪
④放棄・放置:保護責任者遺棄罪
⑤経済的虐待:窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪
まとめ
①虐待防止の責任者の明確化、②マニュアルの作成と周知徹底、③従業員の意識改革、④人権意識を高める研修等
⑤個別支援計画の作成、⑥開かれた運営、⑦従業員への相談体制の確保、⑧苦情処理体制の確立
戸根行政書士事務所からのお知らせ
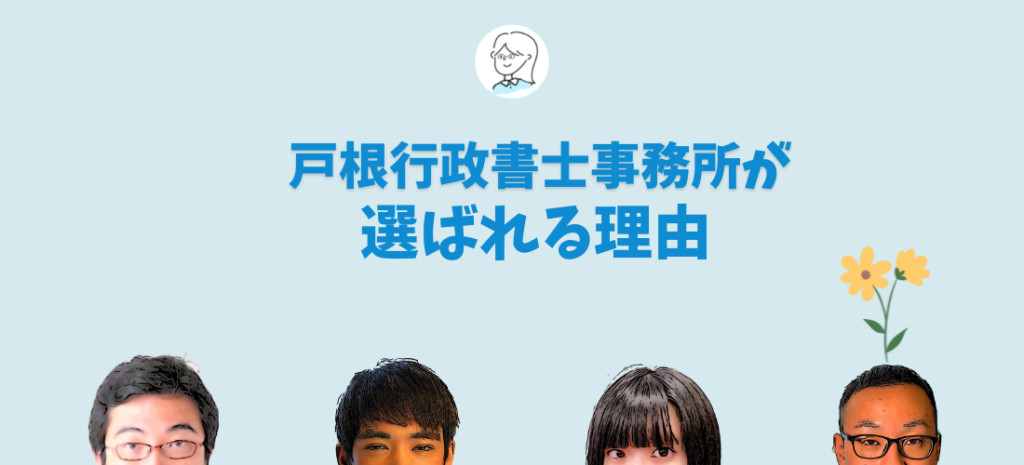
<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ
・【まとめ】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から注意点まで解説
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
<減算について>
・【基本】人員欠如の減算とは?計算方法や注意点も解説
・【詳解】人員欠如の減算:基準や緊急対応・防止策をご説明
・【詳解】サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算とは?
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題点と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【必見】就労支援事業会計とは?会計区分や按分処理のポイント解説
・【注意】就労支援事業の積立金とは?余剰金を発生させない会計処理
・【注意】サービス管理責任者の更新研修の条件とは?
・【基本】サービス管理責任者の実務経験おすすめルートとは?
・【基本】「一体型」と「多機能型」の違いとは?事業拡大のチャンス!
・【大注目】令和5年サービス管理責任者の実務経験が6ヶ月に変更!
・【大注目】令和5年サービス管理責任者不在の猶予期間が2年に!
<工賃上昇のための体制づくり>
・【高収入】施設外就労支援の注意点とは?基本から間違えやすいミスまで説明
・【推奨】就労移行連携加算とは?オススメ活用事例あり
・【注目】就労移行支援体制加算とは?オススメ活用事例あり
・【注目】就労継続支援事業所に計画相談支援事業所を併設して収益アップ!
<工賃支払いを適正に管理する>
・【基本】就労継続支援B型:工賃支払いの注意点は?月ごとの手続き解説
<現状に応じた適切な事業所体制を作る>
・【基本】平均工賃月額の計算の仕方は?解説と注意点とは
・【重度】「重度者支援体制加算」とは?よくある間違いも解説
<工賃支払以外の参加・共感型の新体制を目指す>
・【令和3年】ピアサポート体制・実施加算とは?オススメ活用事例あり
・【令和3年】地域協働加算とは?オススメ活用事例あり
<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
・【義務化】身体拘束適正化委員会と「身体拘束廃止未実施減算」とは
<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援A型編>
・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説
・実地指導、ここがチェックされる②!間違えやすいポイント解説
<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援B型編>
・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説










































