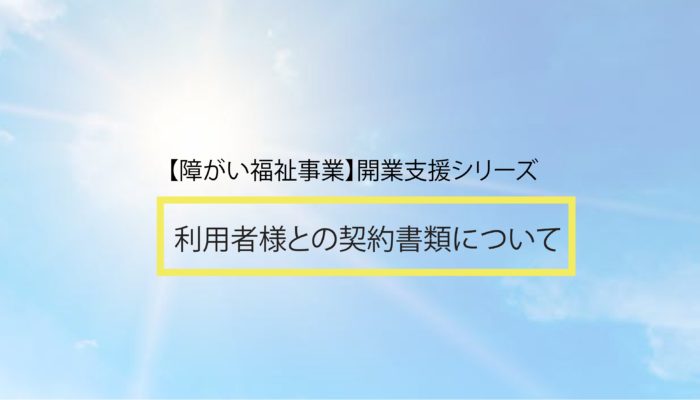
障がい福祉事業で、まず用意すべき利用者様との契約書類とは?
利用者様との契約書類は行政による「実地指導」の時に必ずチェックされます。
もし契約書類を適切に用意しておかないと、行政による指導が入ってトラブルの危険があります。
これまで多くの障がい福祉事業のサポートに関わる中で、多くの事業所様は契約書等はきちんと作成・保存をされていました。
ただ保存形式に問題があり、「実地指導」の時に迅速に提示できずトラブルになったことも見かけました。
そこで本日はこうした書類の中身だけでなく、保存形式についてもオススメをご説明いたします。
目次
利用契約書

利用契約書のテンプレートは、各行政の障がい福祉課等のホームページに設置されていると思いますので、そちらをご覧ください。
記載事項の注意
・「利用者から徴収する費用」はその根拠を踏まえて合理的に定めてください(※特に給食費等を請求する場合、注意が必要です)
・「苦情対応」は窓口を「直接支援員」等ではなく、「管理者」に設定するようにいたしましょう。
交付時の注意
利用者又はご家族から押印をいただき、必ず2部作成し、事業所で保管する1部と、もう1部はお渡しいたしましょう。
その時に「受取書」など記名してもらうとトラブル予防になります。
保存時の注意
利用者ごとにファイルを作り、その冒頭に収納するよう心がけましょう。
重要事項説明書

同じく、利用契約書のテンプレートは、各行政の障がい福祉課等のホームページに設置されていると思いますので、そちらをご覧ください。
記載事項の注意
・「苦情対応」や「緊急時対応」を記載する時、あわせてマニュアルと掲示用の要旨も作成すると合理的です。
・日用品など「その他負担額」はできるだけ細かく、具体的に記しましょう。
交付時の注意
利用者又はご家族から押印をいただき、必ず2部作成し、事業所で保管する1部と、もう1部はお渡しいたしましょう。
その時に「受取書」など記名してもらうとトラブル予防になります。
保存時の注意
利用者ごとにファイルを作り、「利用契約書」の次に収納するよう心がけましょう。
個人情報使用同意書

多くの障がい福祉事業所で「利用契約書」と「重要事項説明書」は作成していましたが、この「個人情報の同意書」に関して未作成の事業所を見かけることがあります。
障がい福祉サービスを提供するのに、利用者からその家族構成含め身体のこと年金のことなど個人的な情報を受け取ります。
そこから利用者の意向・希望・課題などを聞き取って、「個別支援計画」を作成して障がい福祉サービスをいたします。
つまり利用者様の極めて個人的な情報を事業所のスタッフの間で共有することになりますので、個人情報の取り扱いが厳しい時代、同意書は必ず得ておいていただきたいです。
・個人情報使用同意書はインターネットでテンプレートが落ちています
その他
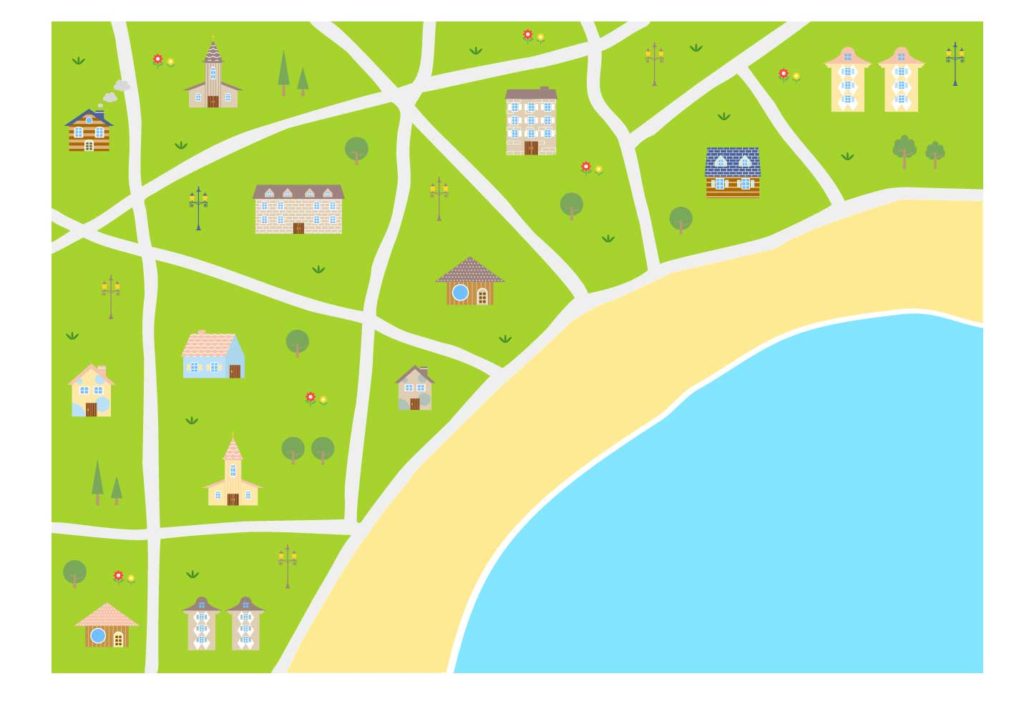
消毒等同意書
新型コロナ感染拡大の影響により、事業所内の感染対策は徹底する必要があります。
その中で利用者に通所ごとに検温・消毒はして頂くことは大切です。
預かり金管理契約書
障がい福祉サービスの種類によっては、利用者さまからお金を預かることがあります。
その時に、どのように管理し、どのように使用するか、契約書で記して同意を得ていくと、トラブルを避けられるでしょう。
法定代理受領同意書
利用者様へサービスした対価は、一部の利用者負担を除いて、国から給付金として支払われます。
これは原則、利用者に対するサービスから得ているので、利用者に代わって国に支払ってもらうことの代理受領の同意を得ておきましょう。
よくある質問
これらの契約書類は実地指導でチェックされますか?
答:されます。特に「重要事項説明書」と「利用契約書」は必ずチェックされます。
「重要事項説明書」の保存で気をつけることはありますか?
答:指定時に作成した「運営規定」の変更に気をつけてください。「運営規定」を変更したら「重要事項説明書」も変更しなければなりません。
「重要事項説明書」は普通の文字の大きさだけのバージョンを揃えておけばいいですか?
答:ルビ版と拡大版もご用意ください。様々な障がい者に対して配慮があるということで、行政の印象もよくなります。
まとめ
・署名印鑑の後は事業者と利用者双方による割印をしてください
戸根行政書士事務所からのお知らせ
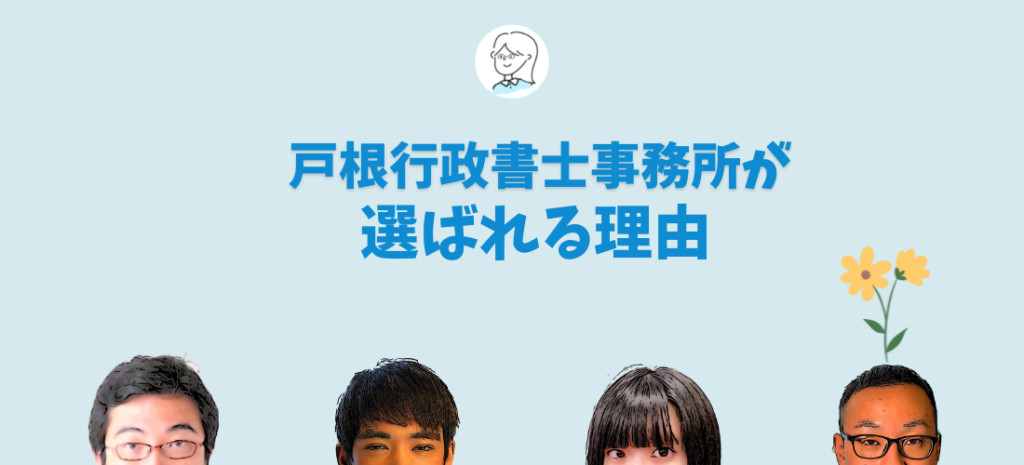
<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ
・【まとめ】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から注意点まで解説
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
<減算について>
・【基本】人員欠如の減算とは?計算方法や注意点も解説
・【詳解】人員欠如の減算:基準や緊急対応・防止策をご説明
・【詳解】サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算とは?
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題点と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【必見】就労支援事業会計とは?会計区分や按分処理のポイント解説
・【注意】就労支援事業の積立金とは?余剰金を発生させない会計処理
・【注意】サービス管理責任者の更新研修の条件とは?
・【基本】サービス管理責任者の実務経験おすすめルートとは?
・【基本】「一体型」と「多機能型」の違いとは?事業拡大のチャンス!
・【大注目】令和5年サービス管理責任者の実務経験が6ヶ月に変更!
・【大注目】令和5年サービス管理責任者不在の猶予期間が2年に!
<工賃上昇のための体制づくり>
・【高収入】施設外就労支援の注意点とは?基本から間違えやすいミスまで説明
・【推奨】就労移行連携加算とは?オススメ活用事例あり
・【注目】就労移行支援体制加算とは?オススメ活用事例あり
・【注目】就労継続支援事業所に計画相談支援事業所を併設して収益アップ!
<工賃支払いを適正に管理する>
・【基本】就労継続支援B型:工賃支払いの注意点は?月ごとの手続き解説
<現状に応じた適切な事業所体制を作る>
・【基本】平均工賃月額の計算の仕方は?解説と注意点とは
・【重度】「重度者支援体制加算」とは?よくある間違いも解説
<工賃支払以外の参加・共感型の新体制を目指す>
・【令和3年】ピアサポート体制・実施加算とは?オススメ活用事例あり
・【令和3年】地域協働加算とは?オススメ活用事例あり
<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
・【義務化】身体拘束適正化委員会と「身体拘束廃止未実施減算」とは
<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援A型編>
・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説
・実地指導、ここがチェックされる②!間違えやすいポイント解説
<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援B型編>
・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説










































