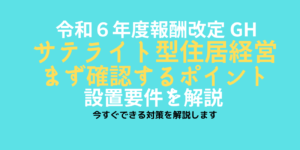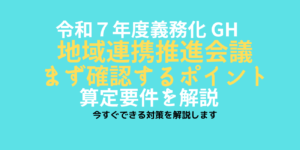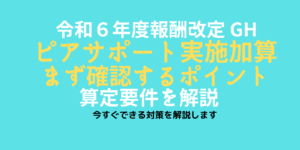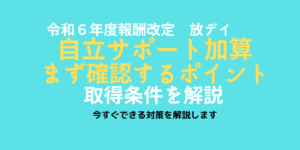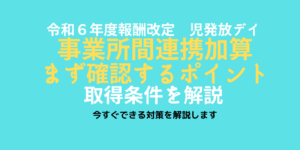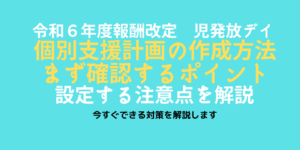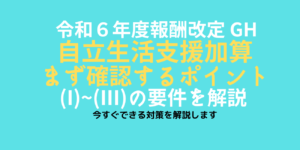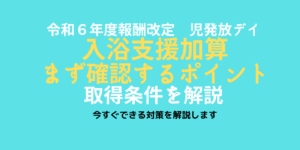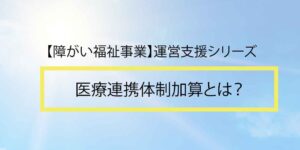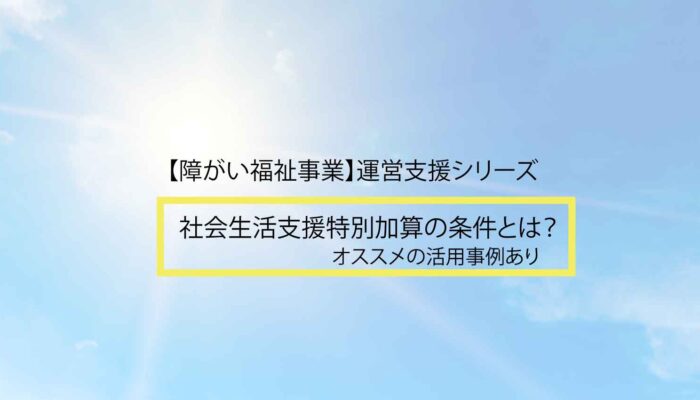
「社会生活支援特別加算」の条件とは何で、どのように活用すれば良いでしょうか?
「社会生活支援特別加算」は、次の方の社会生活復帰を支援するための加算です。
・心神喪失により加害行為を行なった刑務所出所者
「社会生活支援特別加算」は、
この記事を読めば、社会生活支援特別加算を取得するための条件や手順がわかり、事業所経営に活かすヒントが得られます
これまで多くの障がい福祉事業所様のサポートをしている中で、「他の事業所との差が出にくい」、「利用者がなかなかきてくれない」と言った声をお聞きします。
加算というは、ただ給付にプラスになるだけでなく、加算を取得できる特色ある体制を整えているということを意味し、事業所の個性になります。
そこでポイントになるのは、地域においてどのような連携を構築するかという点です。
「社会生活支援特別加算」を算定することは、
自分の事業所で地域福祉に貢献できるユニークなプログラムを作ることにもなります
ので、ぜひご検討ください。
目次
社会生活支援特別加算の条件とは?
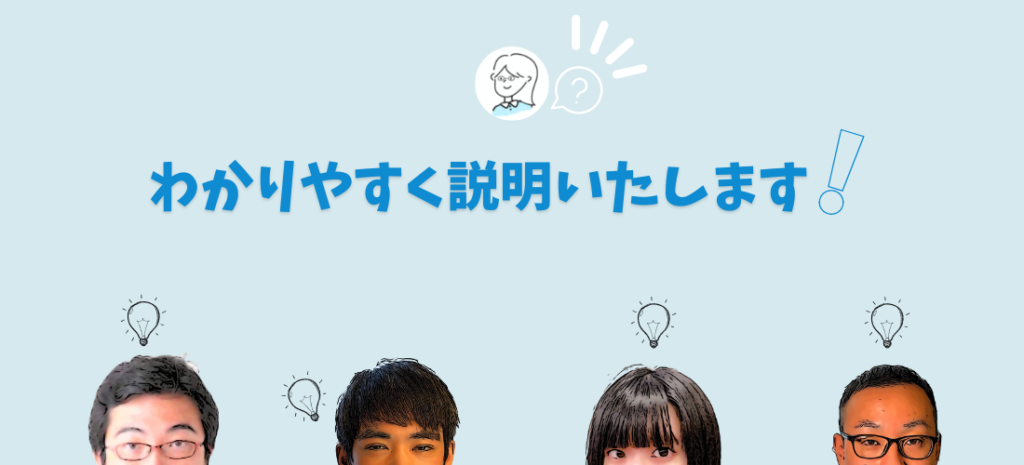
「社会生活支援特別加算」を算定するためには届出が必要になります。
それでは届出をするために、事業所でどのような条件を満たしていればいいのでしょうか。
人員配置基準以上の生活支援員

各種障がい福祉サービスに必要な数より多くの「生活支援員」が必要です。
それは加害行為を行なった方々へ、特別な一層細やかな生活面のケアが必要になるからです。
加えて社会復帰を必要とする対象者が通所する日は、担当する「生活支援員」が勤務する日に合わせる工夫も必要です。
有資格者による指導

加害行為を行なった出所者や治療者は、生活面でのケアだけではなく、心身の専門家による特別の配慮が必要になります。
そして、それらの者が事業所に「配置されている」か、もしくは「訪問させているか」が確認されます。
ポイントは必ずしも事業所に配置する必要はないということです。
従って地域医療機関との連携のもの、定期的に訪問してもらう体制を整えておけば大丈夫です。
これらの地域医療機関との連携体制に関しては契約書を交わしておいてください。
従業員への研修の開催

出所者や加害行為を犯して治療を受けている者への社会復帰の支援は、通常の障がい者支援だけでは分からない細やかな配慮が求められます。
それらを担当する従業員だけでなく事業所全員で共有するため、定期的な研修の実施は欠かせません。
また社会復帰を目指す対象者などに対して対応を誤れば再犯のリスクにもなってしまうことにもご注意ください。
他機関との連携

通院治療決定者や刑務所出所者への支援は事業所だけでなく、地域の他機関と連携する必要があります。
対象者のアセスメント に関してもこれら他機関の担当者からの聞き取りが不可欠でしょう。
特に重要なのは、対象者の支援において情報共有をできる限りすることです。
そして支援対象者の状態に不可解なところがあれば素早く報告し、トラブルになる芽を未然に防ぐことが肝心です。
社会生活支援特別加算のオススメ活用事例とは?
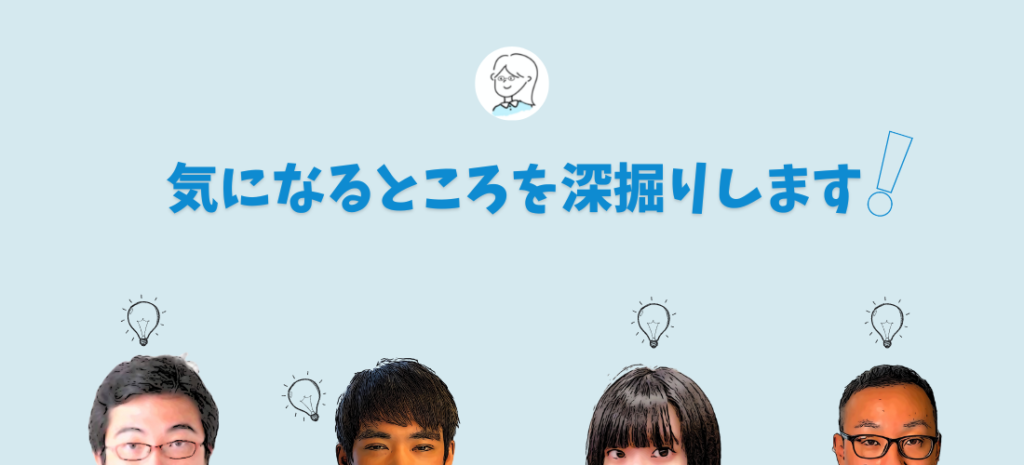
これまで「社会生活支援特別加算」の条件などをお伝えしてきましたので、諸条件が整えば加算を取得することはできるでしょう。
けれども「社会生活支援特別加算」を取得してどのような事業所づくりを目指していけばいいのでしょうか?
刑務所出所者や通院治療決定者を受け入れることは、時として事業所のリスクにもなります。
そこでオススメの活用事例を考えてみましょう。
地域連携を目指す事業所さま
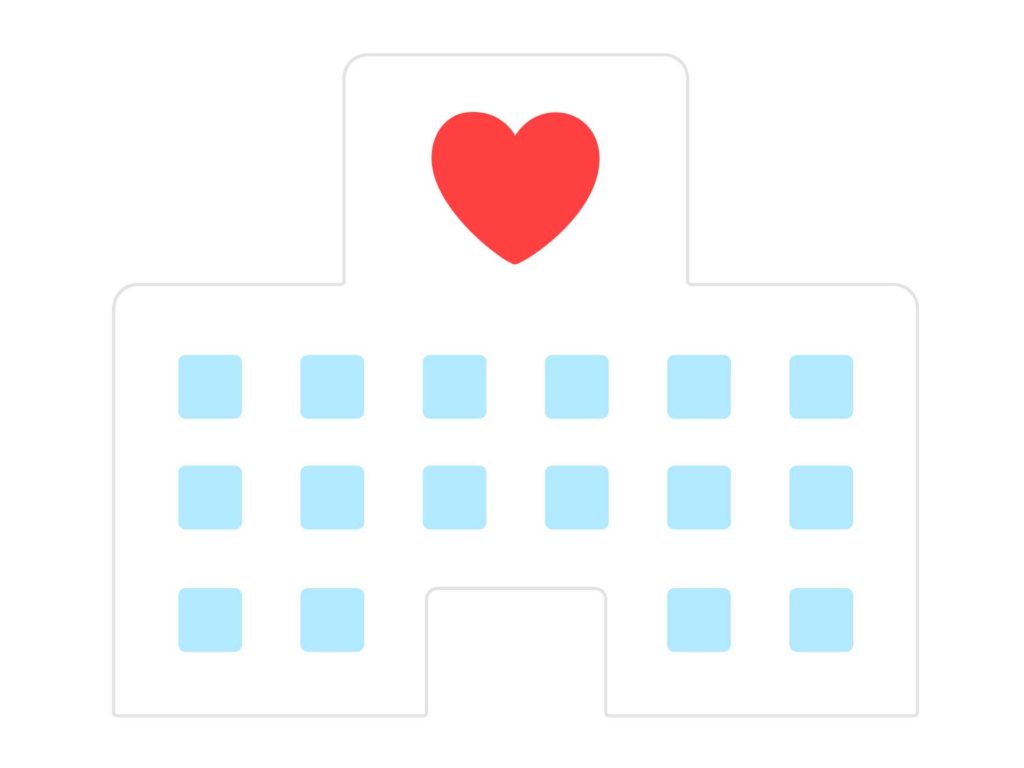
まず障がい福祉サービスを提供するにあたって、地域連携に力を入れていきたい事業所さまがオススメです。
またこのような出所者の方々を事業所に受け入れるということは、町会などの地区の機関とも連携する可能性が出てきます。
それゆえに障がい福祉サービスを提供するだけの事業所が、その役割を拡大して地域福祉の中核に変化する可能性があります。
そうすると競合の多事業所との差別化にも成功し、地域で頼られる存在になるでしょう。
社会更生を目指す事業所さま
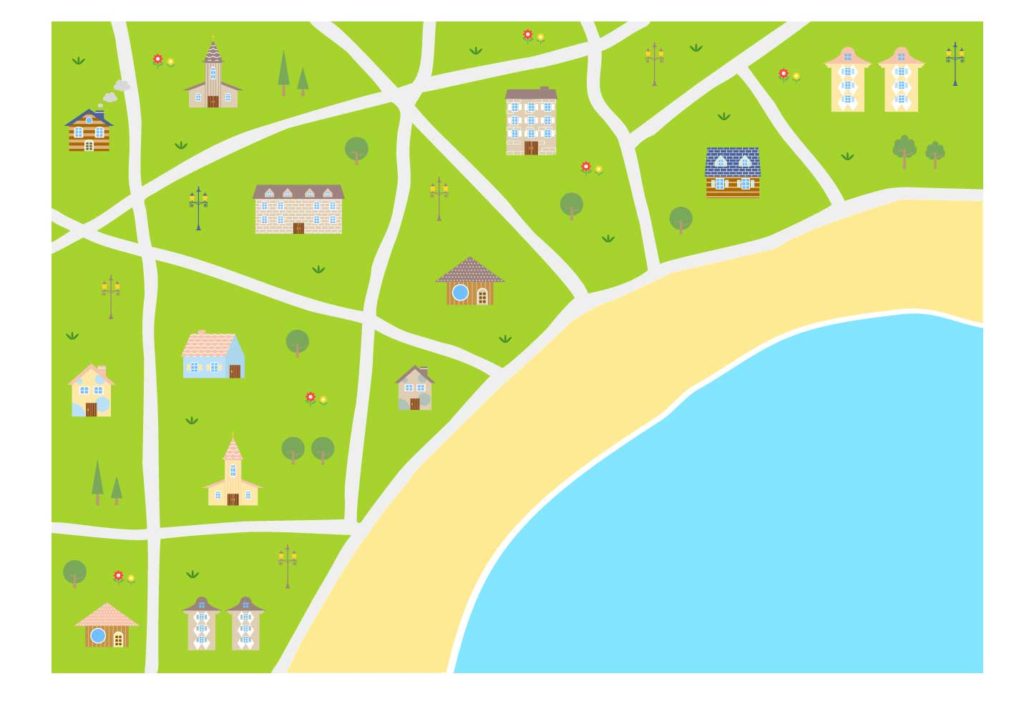
そのままですが、社会更生に力を入れる事業所さまは「社会生活支援特別加算」がオススメです。
そこで特に力を入れていただきたいのが、障がい福祉サービスとの組み合わせです。
これは対象者の出所後の、これからの生活を安定させる上で欠かせない機会となります。
また障がい福祉事業所を通して、社会福祉士や精神保健福祉士などのケアを受けられる体制になっているのも大事なことです。
出所後の継続的支援は、保護観察所や更生保護施設では限界があるので、そこを障がい福祉サービスと組み合わせて、柔軟に対応できれば社会更生に大きく貢献できるでしょう。
まとめ
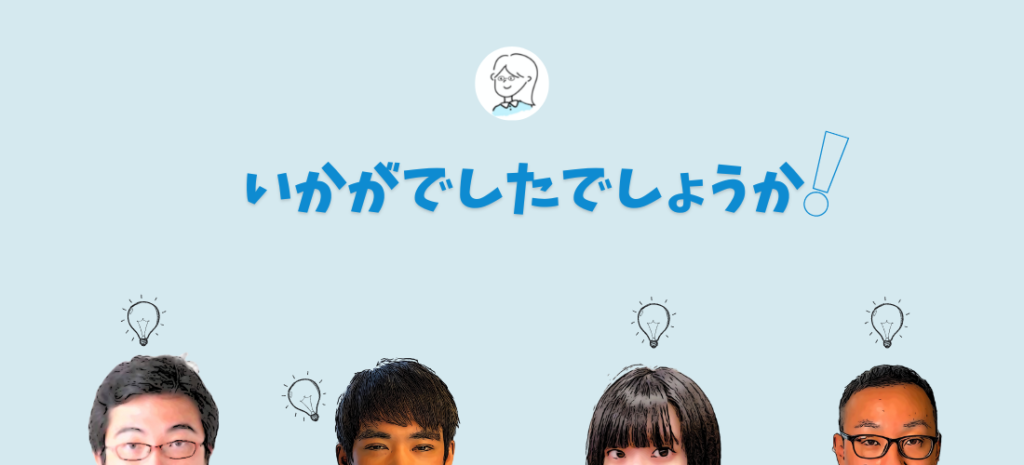
・「社会生活支援特別加算」の加算取得オススメの事業所様は、地域連携を目指したり、社会更生を支援プログラムに入れたりしているところです
戸根行政書士事務所からのお知らせ
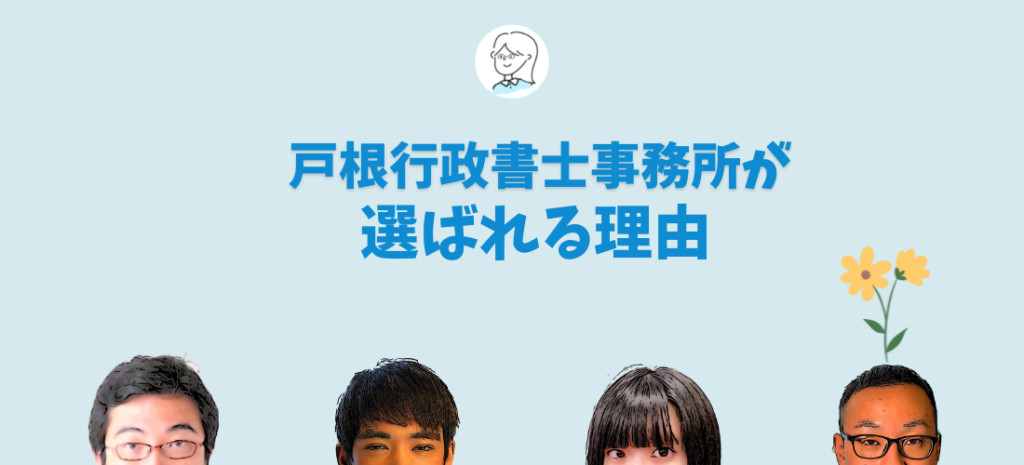
<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ
・【まとめ】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から注意点まで解説
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
<減算について>
・【基本】人員欠如の減算とは?計算方法や注意点も解説
・【詳解】人員欠如の減算:基準や緊急対応・防止策をご説明
・【詳解】サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算とは?
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題点と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【必見】就労支援事業会計とは?会計区分や按分処理のポイント解説
・【注意】就労支援事業の積立金とは?余剰金を発生させない会計処理
・【注意】サービス管理責任者の更新研修の条件とは?
・【基本】サービス管理責任者の実務経験おすすめルートとは?
・【基本】「一体型」と「多機能型」の違いとは?事業拡大のチャンス!
・【大注目】令和5年サービス管理責任者の実務経験が6ヶ月に変更!
・【大注目】令和5年サービス管理責任者不在の猶予期間が2年に!
<工賃上昇のための体制づくり>
・【高収入】施設外就労支援の注意点とは?基本から間違えやすいミスまで説明
・【推奨】就労移行連携加算とは?オススメ活用事例あり
・【注目】就労移行支援体制加算とは?オススメ活用事例あり
・【注目】就労継続支援事業所に計画相談支援事業所を併設して収益アップ!
<工賃支払いを適正に管理する>
・【基本】就労継続支援B型:工賃支払いの注意点は?月ごとの手続き解説
<現状に応じた適切な事業所体制を作る>
・【基本】平均工賃月額の計算の仕方は?解説と注意点とは
・【重度】「重度者支援体制加算」とは?よくある間違いも解説
<工賃支払以外の参加・共感型の新体制を目指す>
・【令和3年】ピアサポート体制・実施加算とは?オススメ活用事例あり
・【令和3年】地域協働加算とは?オススメ活用事例あり
<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
・【義務化】身体拘束適正化委員会と「身体拘束廃止未実施減算」とは
<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援A型編>
・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説
・実地指導、ここがチェックされる②!間違えやすいポイント解説
<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援B型編>
・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説