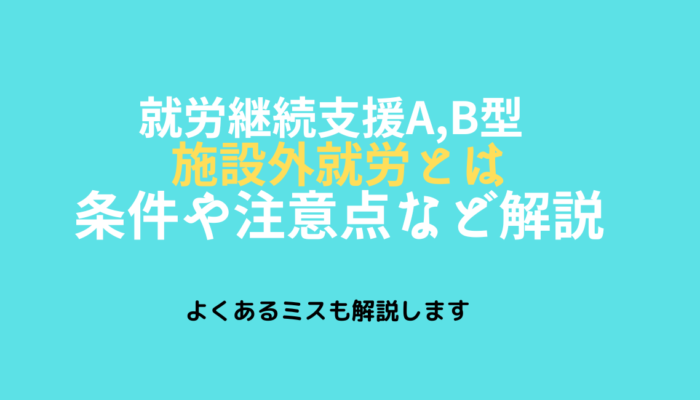
就労継続支援のA型を開業していて賃金を高めるために施設外就労の受注を検討しています。
就労継続支援は基本的に事業所への通所を基本としているサービスだと思いますが、そのように事業所外の施設で支援する時の注意点はどのような点でしょうか??
事業所側で記録する書類など体制管理についても教えてもらえると嬉しいです
施設外就労は就労継続支援の事業所にとって、賃金や工賃を上げるために重要な支援です。
従来あった加算は現在廃止されていますが、通所外の場所での支援は報告書等の必要な書類を無視しているとトラブルになります。
この記事では事業者様の理解の一助になるように以下のような内容がわかるように説明いたします。
- 施設外就労のスタッフの人員配置の要件がわかります
- 施設外就労の個別支援計画の作成のポイントがわかります
- 施設外就労の請求に関する注意点がわかります
目次
- 1 就労系サービスの「施設外就労」の注意点とは?
- 2 よくある質問
- 2.1 施設外就労の際の、就労先と事業所本体のスタッフの配置ですが、1月全体で基準を満たしていればいいですか?
- 2.2 施設外就労の実施の時に、事業所本体でスタッフの基準が満たされない場合、請求することはできますか?
- 2.3 2時間施設外就労を行い、4時間事業所本体で就労を行なった利用者は、どちらの利用人数としてカウントしますか?
- 2.4 施設外就労の人員配置基準を満たしていれば、スタッフがいない時間帯があっても大丈夫ですか?
- 2.5 施設外就労先に同行するスタッフの職種は、どのような職種でもいいでしょうか?
- 2.6 就労継続支援の利用者の前年度実績を計算する時に、施設外就労の利用者は含みますか?
- 2.7 就労外就労先の企業と就Aの企業が同一の場合、施設外就労を実施することができますか?
- 2.8 就労外就労先が個人事業主の場合、施設外就労を実施することができますか?
- 2.9 施設外就労を実施する際に、施設外先で食事を提供する場合、加算を取得できます?
- 2.10 施設外就労を実施する際に、事業所本体に戻って食事を提供する場合、加算を取得できます?
- 2.11 施設外就労を実施する際に、事業所本体に戻って食事を提供する場合、加算を取得できます?
- 2.12 施設外就労を実施する際に、就労事業の実施会社と別会社ですが、両会社の代表が同じ場合は施設外就労は可能でしょうか?
- 2.13 賃金向上達成指導員配置加算または目標工賃達成指導員配置加算を算定している場合、施設外に出る利用者に対しても6:1で配置する必要がありますか?
- 3 まとめ
就労系サービスの「施設外就労」の注意点とは?
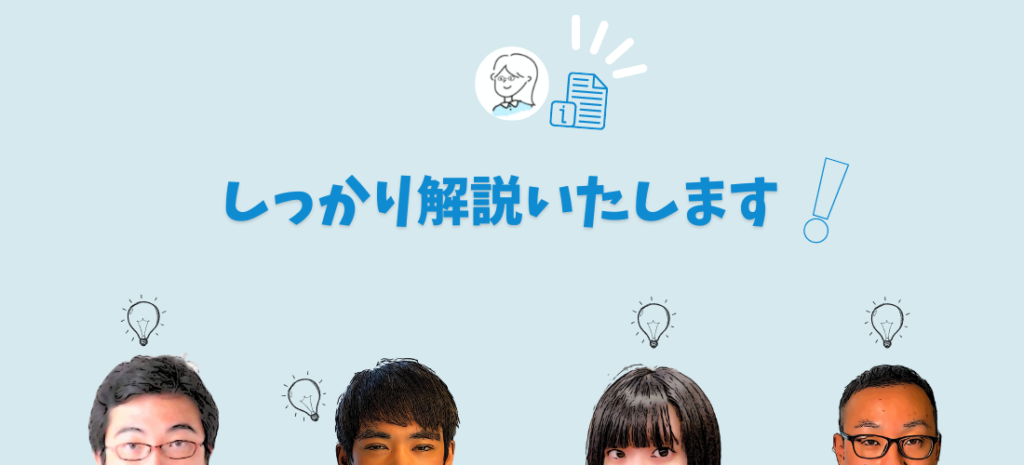
指定を受けた場所以外で実施でる「施設外就労」とは、加算みたいに事前に届出をする必要はありませんが報告書(=施設外就労実施報告書)を翌月自治体に提出する必要があります。
※運営規程にも施設外就労の実施内容を記載する必要があります
<施設外就労実施報告書のポイント>
・就労先の企業ごとに作成する
・作業日/作業時間/作業内容など契約内容をまとめる
・同行する支援者のシフト表を記載する
施設外就労に関して事前の届出も必要でなく実績の報告のみでいいなら簡単そうでいいですね。
ただそれでも施設外就労の実施で就労継続支援の事務所が自治体とトラブルになったという話を聞いたことがあるのですが、施設外就労を提供する上でどのような点に注意すればよろしいでしょうか?
施設外就労は用紙1枚を提出するだけのようですが、通所系サービスの例外的な措置のために様々な点に配慮する必要があります。
気をつけなければ人員配置の減算や定員超過という大きなトラブルに発展してしまいます。
それでは就労継続支援の実施を行う上での注意点をしっかり説明したいと思います。
基本:施設外就労における職員の配置
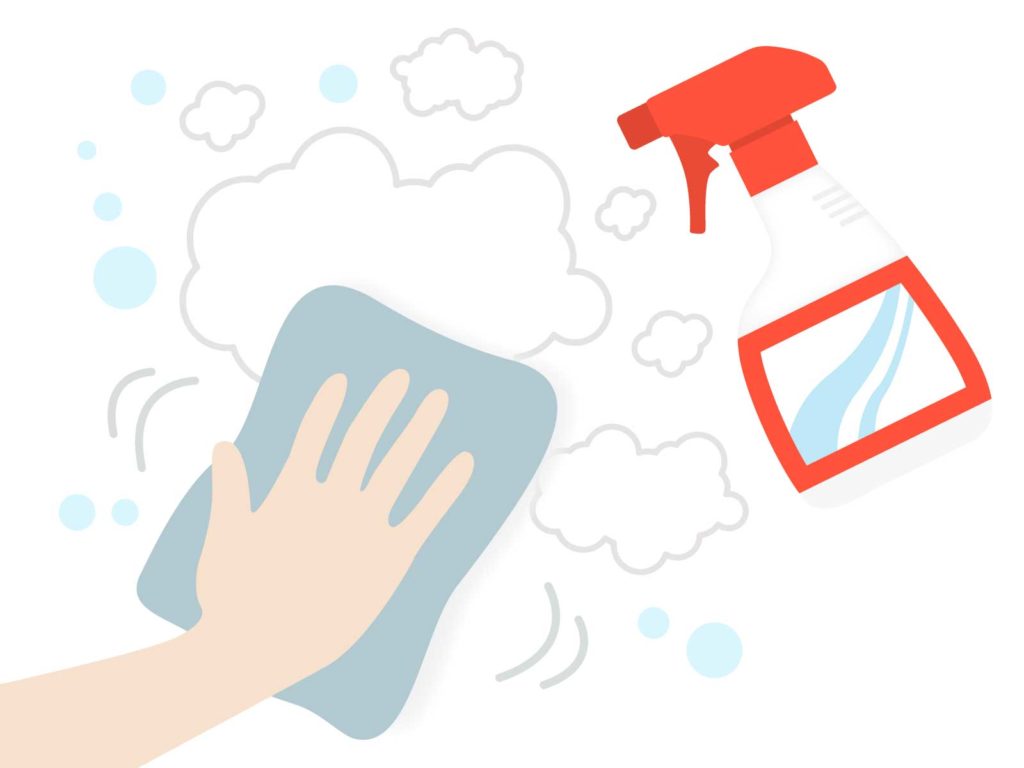
施設外就労を行う日の利用者数に対して、報酬算定上必要とされる人数の職員を配置する必要があります。事業所内の人員配置は自治体によって異なるので必ず問い合わせましょう。
※人数の算出は常勤換算の方法によります。
<就B(10:1;1日8時間勤務):施設外利用者4名>
必要な職員数 = 4 ÷ 10 = 0.4
→ 8時間 × 0.4 = 3.2時間
※注意点1:常時の職員1人配置
施設外において3.2時間配置する必要があるが、そもそも常時に職員を1人配置しなければいけません。
例えば5時間の施設外就労の契約なら3.2時間だけでなく5時間通して配置する必要があります。
※注意点2:事業所内の人員配置の適正化(パターン1の自治体)
昨年度の平均利用者数を根拠に、報酬請求のための人員配置を行う必要があります。
例えば昨年度平均19人なら、
19(昨年平均) ÷ 10 = 1.9
→ 8時間 × 1.9人 = 15.2時間
※注意点3:事業所内の人員配置の適正化(パターン2の自治体)
事業所本体で残された利用者数を根拠に、報酬請求のための人員配置を行う必要があります。
例えば昨年度平均19人なら、
{19(昨年平均) - 4(施設外)} ÷ 10 = 1.5
→ 8時間 × 1.5人 = 12時間
施設外就労を実施する事業所で、計算ミスが多発しているのでご注意ください。特に利用者だけの時間を作っているパターンや、事業所本体の人員配置の計算をしていないパターンを多く見かけます。
また施設外の就労先のスタッフに指導させているケースも見られますが、このケースは支援として認められないのでご注意ください。
<施設外の人員配置の注意点>
・事業所本体や施設外のどちらかで人員配置の基準を満たさない場合は,施設外就労の利用者全員の基本報酬の算定ができない
・施設外就労に従事する利用者は,従事時間に関係なく当該日は施設外就労となる(※自治体により見解が異なるのでご注意ください。)
・施設外の職員に賃金向上達成指導員や目標工賃達成指導員は含まれない
・管理者やサービス管理責任者は事業所本体に配置する必要あり
応用:施設外と本体の職員勤務時間の配分
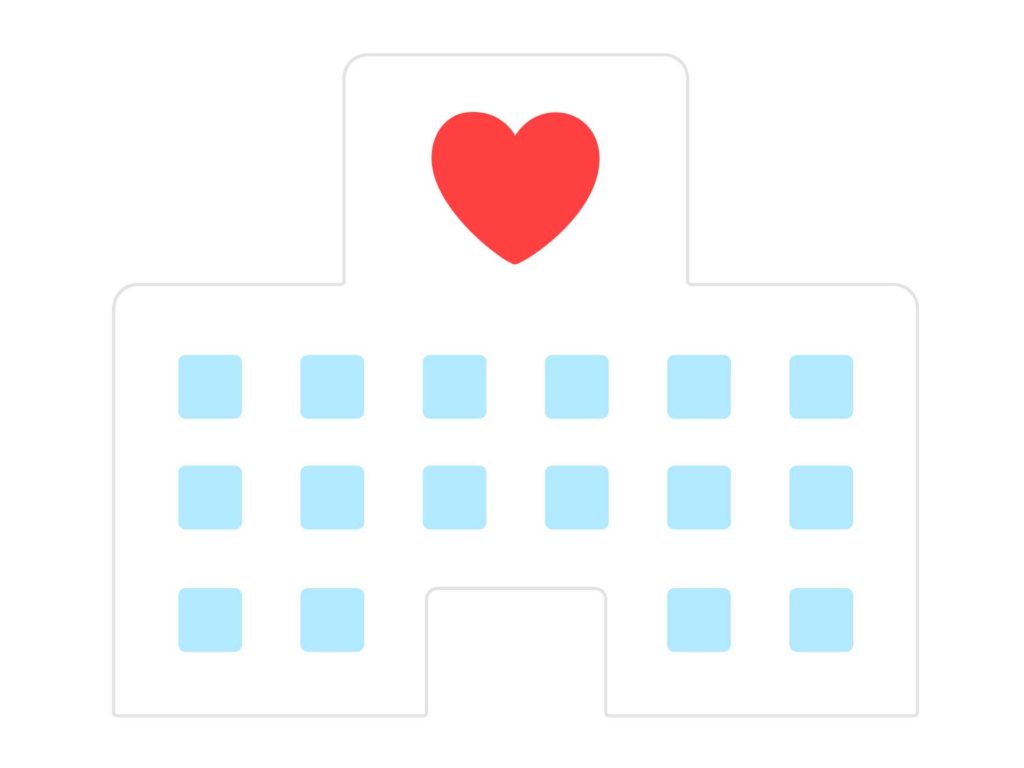
施設外就労の利用者は勤務時間に関係なく当該日は「施設外就労利用者」とみなされるのに対して、他方で事業所の職員は施設外と事業所本体の従業時間を配分することが可能です。
例:就B(10:1;1日8時間勤務):施設外利用者4名 :施設外10〜12時(2時間)
4 ÷ 10 = 0.4 → 0.4 × 8時間 =3.2時間(施設外の人員配置)
| 時間 | 9~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 合計 |
| 本体 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4時間 | ||||
| 施設外 | ○ | ● | ● | ○ | 4時間 |
(解説)
契約上は2時間の施設外就労ですが、人員配置の計算上で3.2時間の配置が必要なので、配置の記録として実態の2時間ではなく4時間(>3.2時間)などにする必要があります。
従ってこの職員は当該日の本体の常勤換算に含まれる時間数は、2時間の施設外契約であっても4時間だけになります。
例2:就B(10:1;1日8時間勤務):施設外利用者3名 :施設外9〜18時(8時間)
3 ÷ 10 = 0.3 → 0.3 × 8時間 =2.4時間(施設外の人員配置)
| 時間 | 9~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 合計 |
| 本体 | 休 | 0時間 | ||||||||
| 施設外 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8時間 |
(解説)
必要なスタッフの人員配置が2.4時間ですが、契約上は8時間の施設外就労なので、8時間の間は誰か1人のスタッフを配置する必要があります。
従ってこの職員は当該日の本体の常勤換算に含まれる時間数は0時間で、残り8時間全ては施設外の人員配置に数えられます。
上記の例は1人のスタッフが施設外支援を行う例ですが、一日中配置が必要な場合は午前と午後で別のスタッフが対応することも可能です。
ただし複数のスタッフで施設外支援を行う場合、交代時などで利用者さんだけの時間が発生しないようにお気をつけください。
※(応用)施設外就労の実施時間の設定について
施設外の実施時間の設定のおすすめは、自治体が施設外利用者全員を本体利用者として見做さないか否かに左右されます。もし施設外利用者が1時間でも本体事業所で働いた時、本体利用者に計上すると見做す自治体でしたら、人員配置に響く出来るだけ利用者数を抑えるために、本体に戻る必要のない時間数、つまり契約上の時間数を設定いたしましょう。
事業所本体の利用者の増加
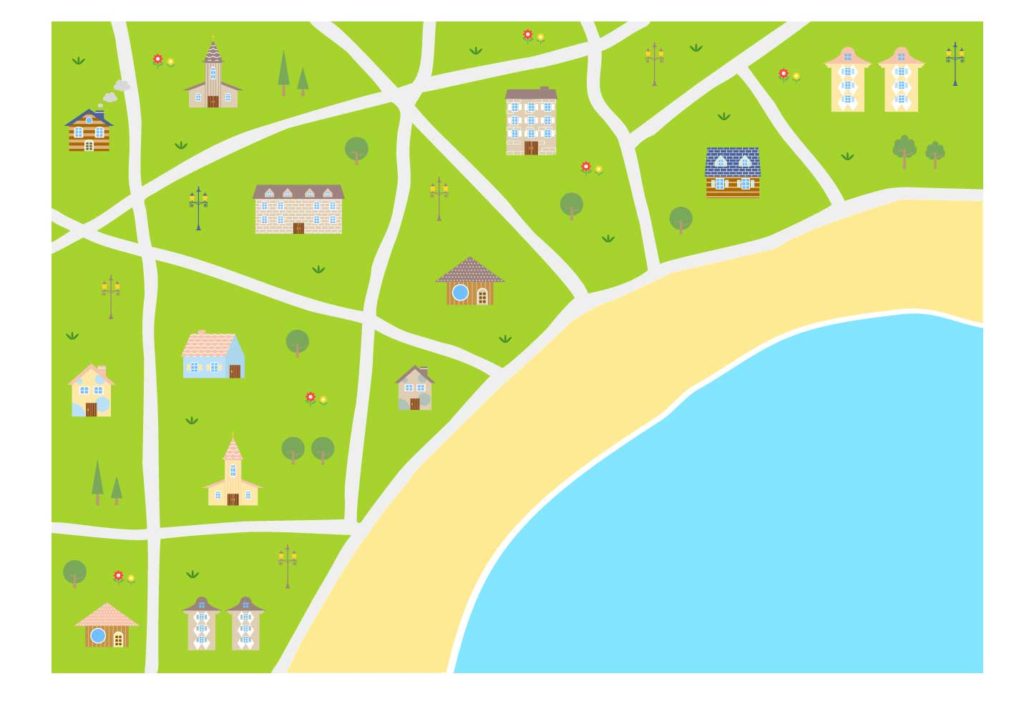
就労継続支援の事業所において、施設外就労によって事業所本体に空きが生じた分は「空きの分だけ増員可能」することができます。
<就B(10:1;1日8時間勤務):定員10名 :施設外利用者4名>
施設外 4名 :スタッフは0.4×8=3.2時間
事業所本体 6名 + 4名 :スタッフは1×8=8時間
つまり施設外就労を利用する日に限れば、就労支援系の事業所の定員を超過して支援をすることが可能になるとも言えます。 しかし施設外就労に従事する利用者を増加させるために,不必要に請負契約を細分化したり交代制にすることは不適切なので避けましょう。
また施設外で就労させることができる上限は定員数なのでご注意ください。
施設外就労を個別支援計画の中へ
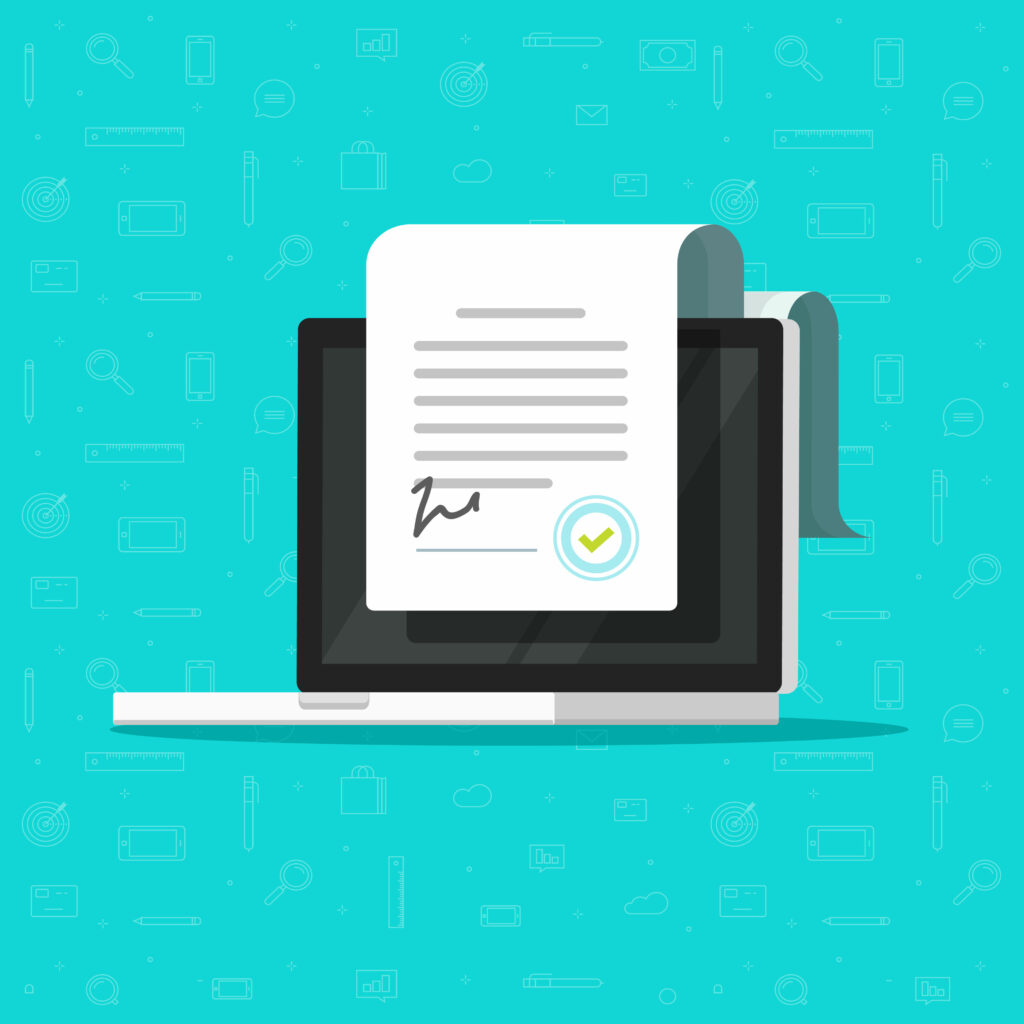
施設外就労を行う利用者さんに対しては、個別支援計画の中で施設外就労を実施する位置付けを記す必要があります。
<施設外就労を個別支援計画で位置付けるポイント>
・施設外就労が、「能力・工賃(賃金)の向上」「一般就労への移行」に資すると認められるようにすること
・訓練目標に対する達成度の評価等を行った結果、 必要と認められる場合には、施設外就労の目標の見直しを行うこと
施設外就労を開始する前に利用者さんにヒアリングし、効果・目標・適性について入念に検討いたしましょう。
施設外就労を個別支援計画の中で位置付けていない事業者さんも散見されます。
施設外就労は例外的な措置なので、その支援が必要であるという理由をしっかり説明できるように計画を立てましょう。
施設外就労の訓練評価を定期的に行う

就労支援系の事業所で施設外就労を実施した場合、月に2回は事業所本体で施設外就労の実績に対する評価を行いましょう。
<施設外就労の評価のポイント>
・施設外就労の実施内容や体調について記す
・施設外就労の課題を達成できていたか否かの評価を下す
・施設外就労に対する利用者の感想を記す
・施設外就労における個別支援計画の達成度を記す
・今後も施設外就労を実施し続けるのか評価を下す
施設外就労の評価は個別支援計画のモニタリングと類似しているものとお考えください。
施設外就労は例外的な措置なので、本当に利用者さんに対してい必要かどうか定期的に判断する必要があります。
必要がないのに施設外に利用者を派遣し、事業所本体に代わりの利用者を入れて請求を水増ししていると皆漁れないように注意致しましょう。
請負契約に即して実施する

就労継続支援の事業所が施設外就労を行う際に、事業所と施設外就労先の会社との間で請負契約を結び、その請負契約に即して支援を行う必要があります。
<請負契約のポイント>
・報酬は施設外就労の成果に対して支払うこと
・施設外就労の作業の完成は事業所側が全ての責任を負うこと
・施設外就労先から材料を受け取る、もしくは機材等を借りる場合はその費用を明確に規定しておくこと
※施設外就労としてポスティングを実施する場合
・作業中は支援員が必ず同行するようにいたしましょう
・施設外作業開始前に、委託先企業と連絡を取り業務内容を確認する作業が必要です
・上記2点をサービス提供記録に記載する必要があります
施設外就労を実施する時に、作業の責任は事業所が負うので現場での指導も事業所側が全て行う必要があります。
作業を施設外就労先のスタッフが指導したり、共同作業をしたりすることは認められません。
請負契約ですのであくまでも施設外就労の作業はその元会社より独立している必要があるのでご注意ください。
送迎の実施の効率化をする

就労継続支援の事業所が施設外就労を行う際に、一度事業所に集まった利用者さんたちが如何に効率よく施設外就労先に集まることができるかが、施設外就労の収益アップのカギとなります。
<施設外先への送迎のポイント>
・「送迎加算」は算定することができない
・利用者さんに従業者を送迎も同行させましょう
・送迎時間は労働時間に含まれません
施設外就労先への送迎に時間がかかれば、その分、労働時間が少なくなり、結果として生産活動の売り上げも上がりません。
4人ワンユニットの仕事を作り、ワンボックスの車での送迎が効率的でしょう。
施設外先の就労場所が事業所の徒歩圏内にあるか、または同じビル内にあればスムーズに施設外就労を実施することも可能です。
よくある質問

施設外就労の際の、就労先と事業所本体のスタッフの配置ですが、1月全体で基準を満たしていればいいですか?
答:いいえ。施設外就労を行う1日毎に基準を満たしている必要があります。
施設外就労の実施の時に、事業所本体でスタッフの基準が満たされない場合、請求することはできますか?
答:いいえ。事業所本体と施設外就労を行うユニットのいずれか一方でも職員配置基準を満たさない場合は,施設外就労を行った利用者全員の基本報酬の算定ができません。
2時間施設外就労を行い、4時間事業所本体で就労を行なった利用者は、どちらの利用人数としてカウントしますか?
答:自治体により見解が異なります。施設外就労の利用者としてカウントすると見なす自治体もあります。その場合、施設外就労に従事する利用者は,従事時間に関係なく当該日は施設外就労となります。これらは就A/就Bの基本報酬単位に関わる事柄なので自治体に問い合わせるなど慎重に対応いたしましょう。
施設外就労の人員配置基準を満たしていれば、スタッフがいない時間帯があっても大丈夫ですか?
答:施設外就労先でスタッフがいない時間があってはいけません。職員交代時などにスタッフ不在の時間ができないようご注意ください。
施設外就労先に同行するスタッフの職種は、どのような職種でもいいでしょうか?
答:基本は生活支援員か職業指導員に限られます。就労支援員や賃金向上達成指導員や目標工賃達成指導員は認められません。
就労継続支援の利用者の前年度実績を計算する時に、施設外就労の利用者は含みますか?
答:含みません。事業所本体の利用者のみで前年度実績は計算いたします。
就労外就労先の企業と就Aの企業が同一の場合、施設外就労を実施することができますか?
答:できません。請負契約を結ぶことができないからです。ただし自治体によって例外的に認める場合がありますので個別にお問い合わせください。
就労外就労先が個人事業主の場合、施設外就労を実施することができますか?
答:可能です。
施設外就労を実施する際に、施設外先で食事を提供する場合、加算を取得できます?
答:請負契約において就労支援事業者がキッチン等を利用できる旨の記述があるれば取得可能です。食事提供を第三者に委託する場合はその人件費を事業所が支払えば加算の算定は可能です。
施設外就労を実施する際に、事業所本体に戻って食事を提供する場合、加算を取得できます?
答:加算を取得することができます。
施設外就労を実施する際に、事業所本体に戻って食事を提供する場合、加算を取得できます?
答:加算を取得することができます。
施設外就労を実施する際に、就労事業の実施会社と別会社ですが、両会社の代表が同じ場合は施設外就労は可能でしょうか?
答:基本的には可能ですが、代表が同じ場合は審議の対象になる可能性があります。
賃金向上達成指導員配置加算または目標工賃達成指導員配置加算を算定している場合、施設外に出る利用者に対しても6:1で配置する必要がありますか?
答:いいえ。施設外に出る利用者への配置は基本報酬単位の配置と同じです。
まとめ
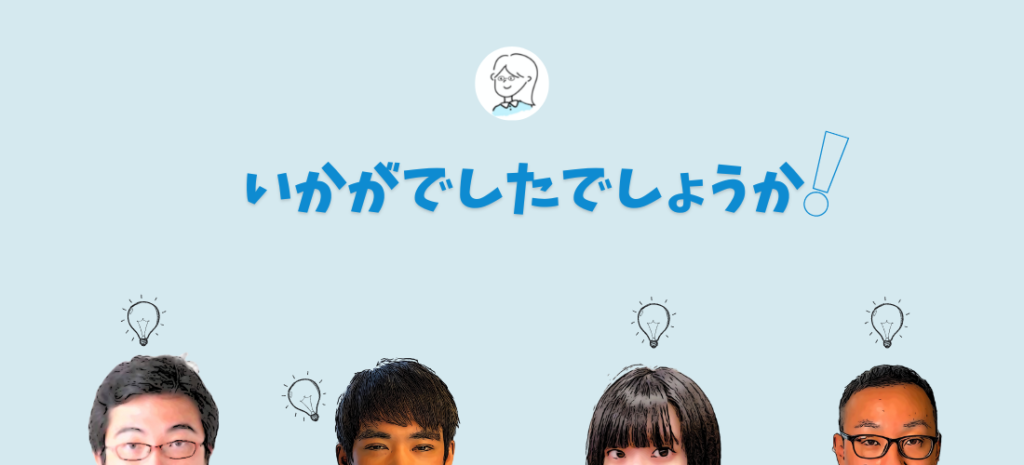
本日は施設外就労の実施について、かなり詳しいところまでご説明いただきありがとうございました。
特にスタッフの配置について計算ミスがないように注意したいと思います。
施設外就労先のスタッフの配置について特に不在の時間がある場合が散見されますのでご注意ください。
また事業所本体で受け入れられる人数も、施設外就労の人数を超えないように管理することが大切です。
施設外就労は利用者の工賃・賃金を高め、そして事業所の基本報酬単位も上げる重要な支援なので、しっかりとルールを守った上で活用していただければ嬉しいです。
戸根行政書士事務所からのお知らせ
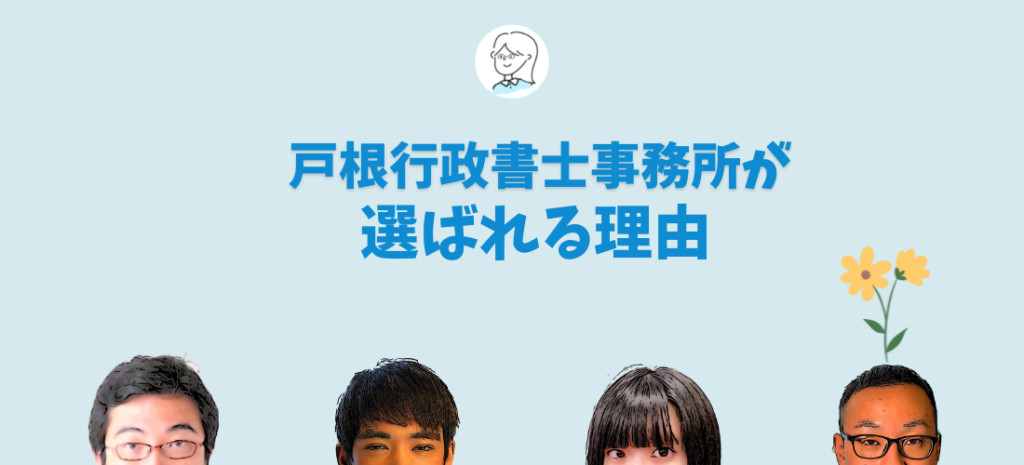
<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ
・【まとめ】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から注意点まで解説
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
<減算について>
・【基本】人員欠如の減算とは?計算方法や注意点も解説
・【詳解】人員欠如の減算:基準や緊急対応・防止策をご説明
・【詳解】サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算とは?
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題点と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【必見】就労支援事業会計とは?会計区分や按分処理のポイント解説
・【注意】就労支援事業の積立金とは?余剰金を発生させない会計処理
・【注意】サービス管理責任者の更新研修の条件とは?
・【基本】サービス管理責任者の実務経験おすすめルートとは?
・【基本】「一体型」と「多機能型」の違いとは?事業拡大のチャンス!
・【大注目】令和5年サービス管理責任者の実務経験が6ヶ月に変更!
・【大注目】令和5年サービス管理責任者不在の猶予期間が2年に!
<工賃上昇のための体制づくり>
・【高収入】施設外就労支援の注意点とは?基本から間違えやすいミスまで説明
・【推奨】就労移行連携加算とは?オススメ活用事例あり
・【注目】就労移行支援体制加算とは?オススメ活用事例あり
・【注目】就労継続支援事業所に計画相談支援事業所を併設して収益アップ!
<工賃支払いを適正に管理する>
・【基本】就労継続支援B型:工賃支払いの注意点は?月ごとの手続き解説
<現状に応じた適切な事業所体制を作る>
・【基本】平均工賃月額の計算の仕方は?解説と注意点とは
・【重度】「重度者支援体制加算」とは?よくある間違いも解説
<工賃支払以外の参加・共感型の新体制を目指す>
・【令和3年】ピアサポート体制・実施加算とは?オススメ活用事例あり
・【令和3年】地域協働加算とは?オススメ活用事例あり
<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
・【義務化】身体拘束適正化委員会と「身体拘束廃止未実施減算」とは
<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援A型編>
・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説
・実地指導、ここがチェックされる②!間違えやすいポイント解説
<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援B型編>
・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説












































