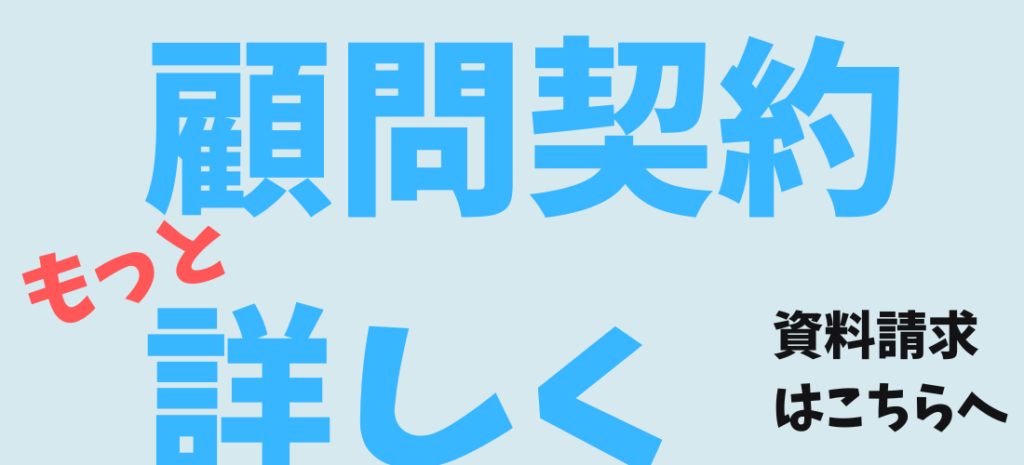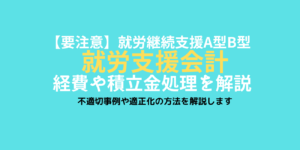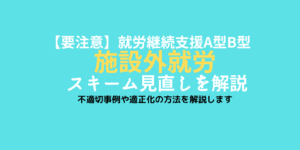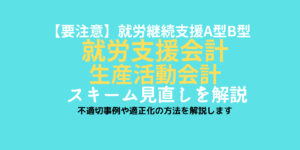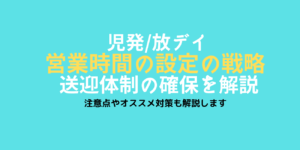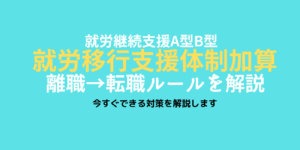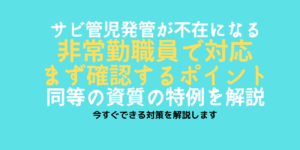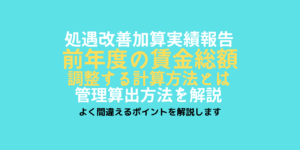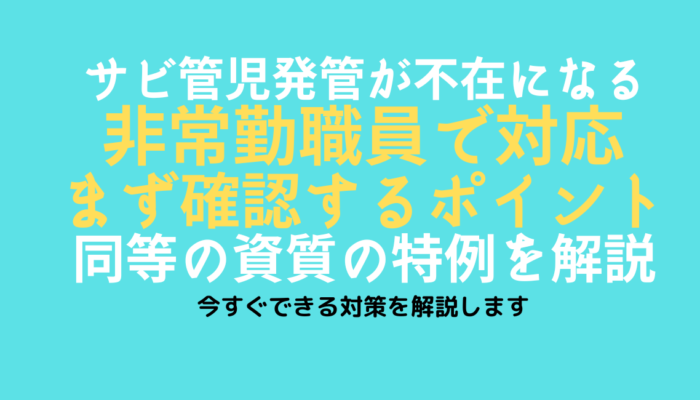
★★★記事執筆者のご紹介★★★
この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております。多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました。
戸根行政書士事務所のプロフィールはこちらですので、よろしければ弊社の支援方針や独自の強みなどご覧ください。

障害福祉事業を運営していて、サビ管と児発管が辞めそうで困っています。サビ管児発管が不在になると減算のリスクが高くなると思いますが、特例により回避できる場合があると聞きました。
そこでお尋ねしたいのですが、サビ管児発管が不在になった時に、減算にならないために、どのような対策が必要でしょうか?
障害福祉事業でサビ管児発管の配置は必須であり、もしサビ管児発管が不在になるとペナルティとして報酬の30%減額にある減算が待っています。
この減算を回避するために、いくつかの方法があるのですが、発動条件が限定的で注意が必要です。
この記事では事業者様の理解の一助になるように以下の内容を説明いたします。
- サビ管児発管が不在になった時の特例の活用一覧がわかります
- 非常勤職員を活用して不在による減算を避ける方法がわかります
- 非常勤職員のキャリアアップ戦略の再考のポイントがわかります
目次
【注意】サビ管・児発管が不在になる対策?非常勤職員を使った解決策を解説

障害福祉事業ではサビ管や児発管が不在になると、翌月末まで替わりのスタッフが見つからなければ欠如減算(請求30%)になりますが、それを防ぐ対策として「1:やむを得ない配置の活用」や「2:常勤30時間の設定」がありますが、今回は「3:非常勤職員の複数名配置」を解説いたします。
<1:やむを得ない配置の活用>
・事業所側で予測することができな事態でサビ管・児発管が不在になった場合は、実務経験ある者が1年間(基礎研修修了者だと2年間)の期間、「みなし配置」できる可能性があります。
・「事業所側で予測することができな事態」とは、突然の退職/失踪/死亡などが想定されています。
・指定権者と協議を行なって許可をもらう必要があります。
・指定権者ごとによって許可をもらうハードルが異なります(※厳しい自治体だと死亡による不在しか認めません)。
<2:常勤30時間の設定>
・障害福祉事業では常勤時間の設定は32時間以上ですが、育児/介護/病気の方は例外的に30時間以上の設定ができます。
・病気の方は、ガイドラインに従って医師による証明書があれば比較的30時間=常勤の設定が簡単です。
・つまり30時間出勤できれば、サビ管児発管減算は避けることができます。
・ただし、指定権者に対して変更届を提出し、30時間で配置する証明を行なってください。
<3:非常勤職員の複数名配置 👈今回のコラムで解説>
・非常勤職員を複数名、配置して常勤時間を満たせばサビ管児発管減算は避けることができます。
・ただし、サビ管児発管が育児/介護で休職している場合に限ります。
・またその非常勤職員は、「同等の資質を有する者」でなければなりません。
・「同等の資質」とは、サビ管児発管と同等の勤続年数や研修修了実績が求められます。
サビ管児発管不在の時の3つの対策についてわかりました。
特に3の「非常勤職員の複数名配置」で対応することは、有効活用できそうなのですが、どのような点に注意すれば良いでしょうか?
サビ管児発管の代わりを常勤職員で探すのは大変なので、「3:非常勤職員の複数名配置」という解決策は魅力的に感じるでしょう。
ただ「3:非常勤職員の複数名配置」が発動できる条件は限定的で、非常勤職員の選定も注意が必要です。
以下では、しっかりと「3:非常勤職員の複数名配置」のポイントをわかりやすく説明いたします。
ポイント:「同等の資質を有する者」がいるか否か
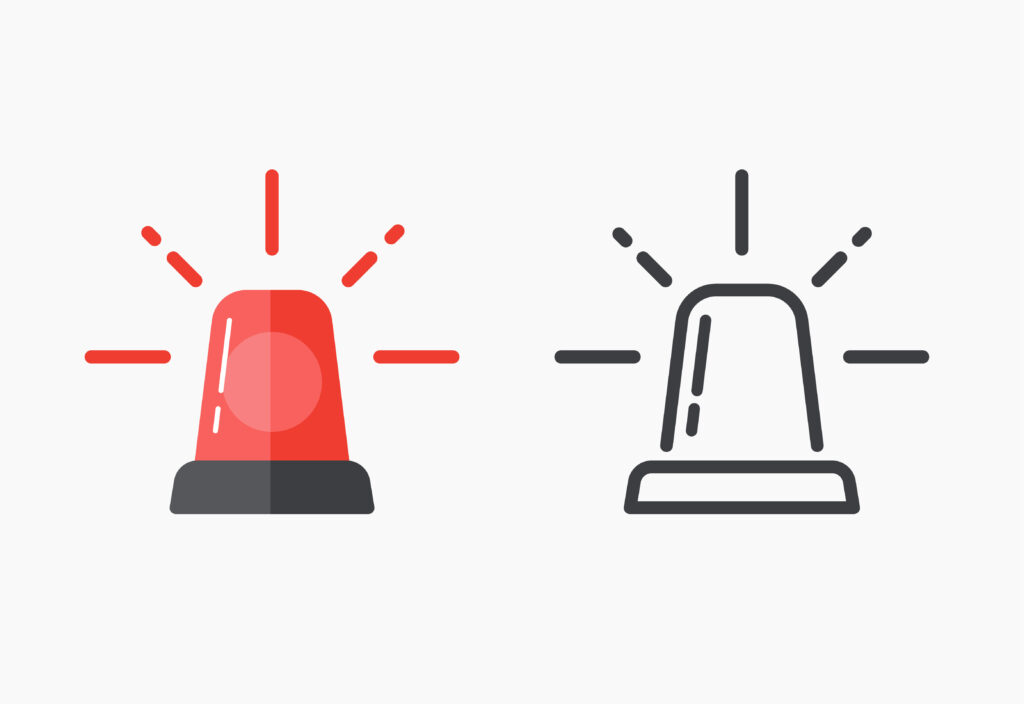
サビ管児発管が不在の場合に対する解決策として、「3:非常勤職員の複数名配置」が令和3年3月31日の報酬改定等のQandA問20(以下で引用)で記されていますが、非常勤職員を活用できるものの、条件と設定が限定的であることにご注意ください。
| 問20 | 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断するのか |
| 答 | ・障害福祉の現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取扱いを認める。 ・<常勤の計算> 育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加え、同法による介護の短時間勤務制度や、男女雇用機会均等法による母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等を利用する場合についても30時間以上の勤務で、常勤扱いとする。 ・<常勤換算の計算> 職員が、育児・介護休業法による短時間勤務制度や母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等を利用する場合、週30時間以上の勤務で、常勤換算上も1と扱う。 <同等の資質を有する者の特例> ・ 「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業、育児休業に準ずる休業、母性健康管理措置としての休業を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算するこで、人員配置基準を満たすことを認める。 ・ なお、「同等の資質を有する」とは、当該休業を取得した職員の配置により満たしていた、勤続年数や所定の研修の修了など各施設基準や加算の算定要件と して定められた資質を満たすことである。 |
<「3:非常勤職員の複数名配置」のポイントについて>
・発動できる条件は、不在になるサビ管児発管が産休/育休/介護休暇の場合に限ります。
・しかも配置できる非常勤職員は、「同等の資質を有する者」に限ります。
・サビ管児発管の「同等の資質を有する者」とは、実務経験(3〜8年)や基礎研修/実践研修の修了と考えられます。
サビ管児発管が不在になる場合、非常勤職員を複数名配置することで、サビ管児発管の不在を防ぐことが出来るのは魅力的でしょう。
しかし不在となるサビ管児発管が退職の場合は活用できず、またサビ管児発管と同等でない非常勤職員は上手く使うこともできません。
そもそもサビ管児発管の資格者が非常勤で事業所に存在すること事態、稀有なことかもしれないので、「3:非常勤職員の複数名配置」の活用は限定的になってしまいます。
今から出来ること:人材育成戦略を見直す
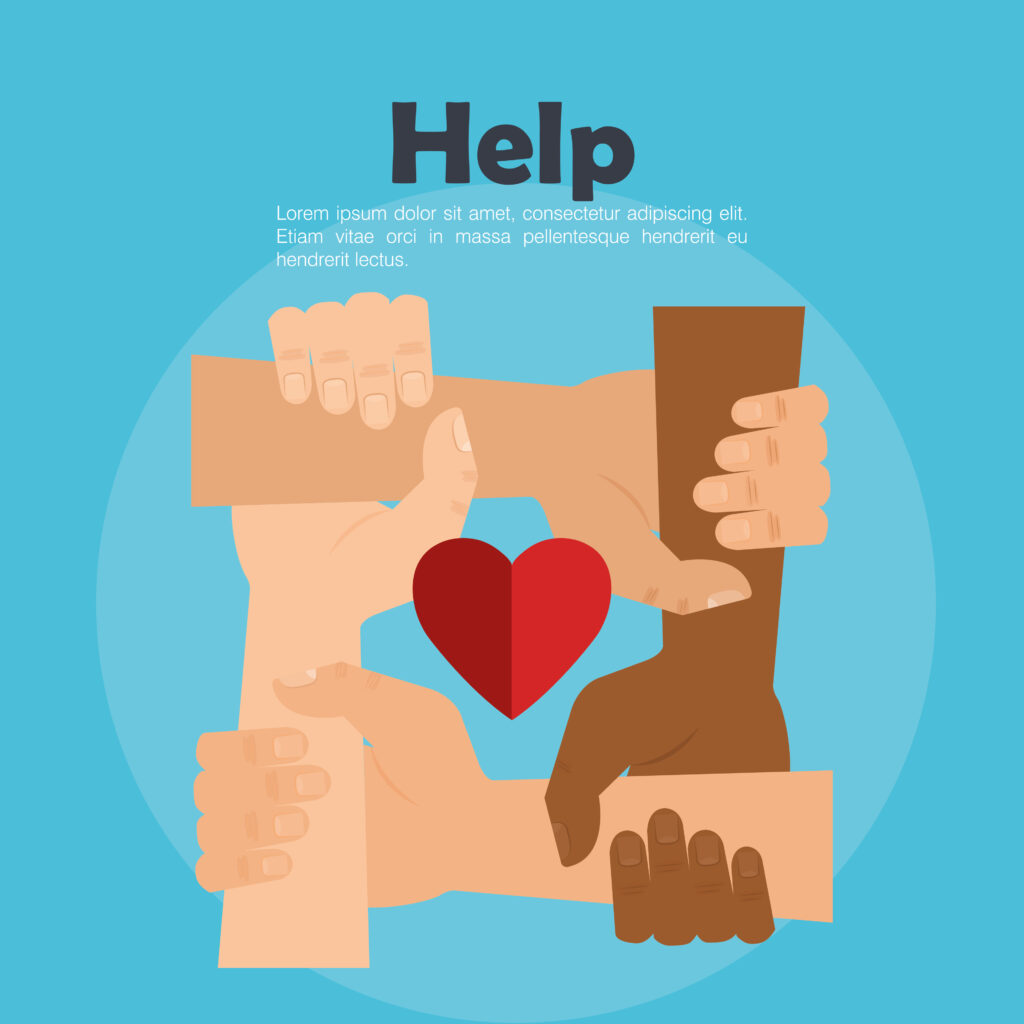
サビ管児発管が不在の時に「3:非常勤職員の複数名配置」を活用できるのは限定的で人を選ぶことがわかりましたが、この条件を踏まえて職員の人材育成戦略を見直し、非常勤であってもサビ管児発管の資格を持てるよう整えましょう。
<人材育成戦略のポイントについて>
・常勤でサビ管児発管配置をする予定がなくても、以前の職場の実務経験証明書を集めておき、時期が来ればサビ管児発管の研修を受けてもらいましょう。
・サビ管児発管の研修はオンライン受講(東北福祉カレッジなど)もできるので、職員の負担を減らすことも出来ます。
・「職場環境等改善要件」も満たすことができ、処遇改善加算も安定して取得できます。
・非常勤職員にもキャリアアップの意識を持ってもらうために、実務経験や研修修了の可否によって時給をあげるのも良いです。
・時給を上げる際は処遇改善加算だけでなく、キャリアアップ助成金を活用することも検討いたしましょう。
サビ管児発管が不在の時の「3:非常勤職員の複数名配置」の活用を想定すれば、非常勤職員のキャリアアップ支援の方向性が変わってくるでしょう。
常勤職員にならないからと言って、待遇改善に消極的になるのは得策ではないです。
非常勤職員の職場環境等改善を意識することが、結果的にサビ管児発管の不在の対策にもなるのです。
まとめ
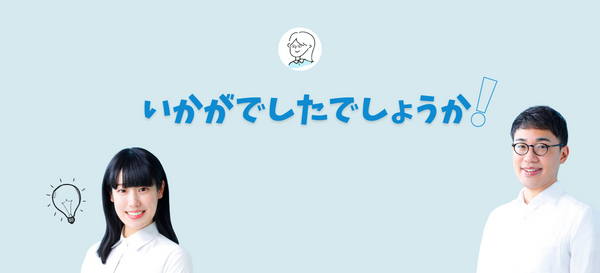
サビ管児発管が不在になった時の対策について詳しく分かりました。ありがとうございます。
「3:非常勤職員の複数名配置」のポイントもしっかり守って、法令に準拠した組織づくりに早く着手したいと思います。
サビ管児発管が不在になると、欠如減算や個別支援計画未作成減算の可能性も出てきて、事業所運営のリスクが高まります。
サビ管児発管が不在になった対策として、非常勤職員を配置する解決策もありますが、発動条件が同等の資質の職員のみ発動できると限定的です。 そこで非常勤職員のキャリアアップ戦略を見直して、非常勤職員にも「サビ管児発管と同等の資質の者」になってもらう準備が大切です。
しっかりとサビ管児発管配置のルールを守って、自治体や利用者さんから信頼される組織を作ってください。
戸根行政書士事務所からのお知らせ
<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ
・【まとめ】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から注意点まで解説
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
<減算について>
・【基本】人員欠如の減算とは?計算方法や注意点も解説
・【詳解】人員欠如の減算:基準や緊急対応・防止策をご説明
・【詳解】サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算とは?
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題点と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【必見】就労支援事業会計とは?会計区分や按分処理のポイント解説
・【注意】就労支援事業の積立金とは?余剰金を発生させない会計処理
・【注意】サービス管理責任者の更新研修の条件とは?
・【基本】サービス管理責任者の実務経験おすすめルートとは?
・【基本】「一体型」と「多機能型」の違いとは?事業拡大のチャンス!
・【大注目】令和5年サービス管理責任者の実務経験が6ヶ月に変更!
・【大注目】令和5年サービス管理責任者不在の猶予期間が2年に!
・【注意】利用者の契約終了の注意点とは?解雇や助成金の関係解説
<工賃上昇のための体制づくり>
・【高収入】施設外就労支援の注意点とは?基本から間違えやすいミスまで説明
・【推奨】就労移行連携加算とは?オススメ活用事例あり
・【注目】就労移行支援体制加算とは?オススメ活用事例あり
・【注目】就労継続支援事業所に計画相談支援事業所を併設して収益アップ!
<工賃支払いを適正に管理する>
・【基本】就労継続支援B型:工賃支払いの注意点は?月ごとの手続き解説
<現状に応じた適切な事業所体制を作る>
・【基本】平均工賃月額の計算の仕方は?解説と注意点とは
・【重度】「重度者支援体制加算」とは?よくある間違いも解説
<工賃支払以外の参加・共感型の新体制を目指す>
・【令和3年】ピアサポート体制・実施加算とは?オススメ活用事例あり
・【令和3年】地域協働加算とは?オススメ活用事例あり
<スコア表についての解説>
・【基本】スコア表(I)の解説!「労働時間」の要件と根拠資料は?
・【基本】スコア表(II)の解説!「生産活動」の要件と根拠資料は?
・【基本】スコア表(III)の解説!「多様な働き方」の要件と根拠資料は?
・【基本】スコア表(IV)の解説!「支援力の向上」の要件と根拠資料は?
・【基本】スコア表(V)の解説!「地域連携活動」の要件と根拠資料は?
・【注意】自己評価未公表減算」とは?公表時の注意点を解説
<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
・【義務化】身体拘束適正化委員会と「身体拘束廃止未実施減算」とは
<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援A型編>
・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説
・実地指導、ここがチェックされる②!間違えやすいポイント解説
<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援B型編>
・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説
<年度ごとの義務化への対応>
・【令和3年度】障害福祉のハラスメント防止の対策とは?運営規程の変更案
・【令和4年度】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
・【令和5年度】身体拘束適正化委員会と「身体拘束廃止未実施減算」とは
・【令和6年度】感染対策委員会とは?運営規定の書き方から記録書類まで
・【令和6年義務】業務継続計画(BCP)とは?書き方から研修・訓練実施方法まで
<令和6年報酬改定のサービスごとの概要>
・【ここから】就労継続支援A型、まず確認するポイント
・【ここから】就労継続支援B型、まず確認するポイント
・【ここから】障がい者グループホーム、まず確認するポイント
・【ここから】児童発達支援/放課後等デイサービス、まず確認するポイント