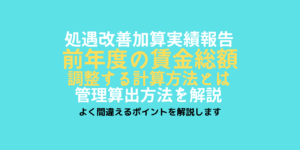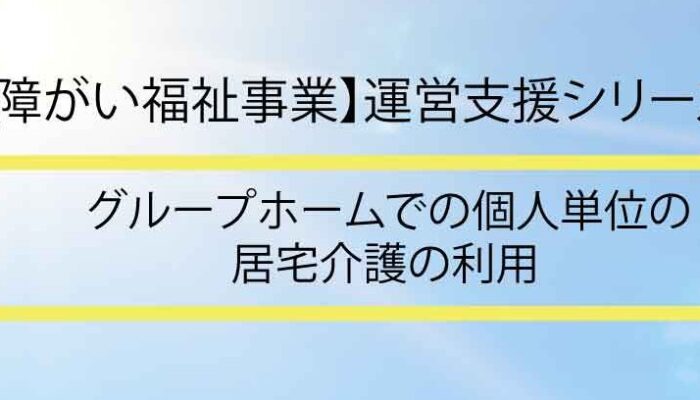
グループホームにおいて個人単位で居宅介護を利用する時の要件や注意点とは何でしょうか?
共同生活援助(グループホーム)の利用者へ、介護サービスを提供する場合は、
・生活支援員による介護
・外部の居宅介護事業所への委託による介護
のいずれかの形態になっています。
そして原則として、
- この2種類以外による介護等を受けさせてはならないと
されています。
しかし個人単位でその例外が認められる措置があるのです。
この記事を読めば、グループホームにおける個人単位の居宅介護の利用の要件や注意点、それに活用事例がわかります
これまで多くのグループホーム事業所のサポートをしてきた中で、「利用者に対して共同住宅内で重度の介護サービスを行いたい」と言った相談を度々受けました。
こうした相談は実現可能ですが、あくまで特例措置の範囲内ですので注意が必要です。
そこで本日はグループホームにおける個人単位の居宅介護の利用について解説していきます。
目次
グループホームでの個人単位の居宅介護の利用の要件とは?
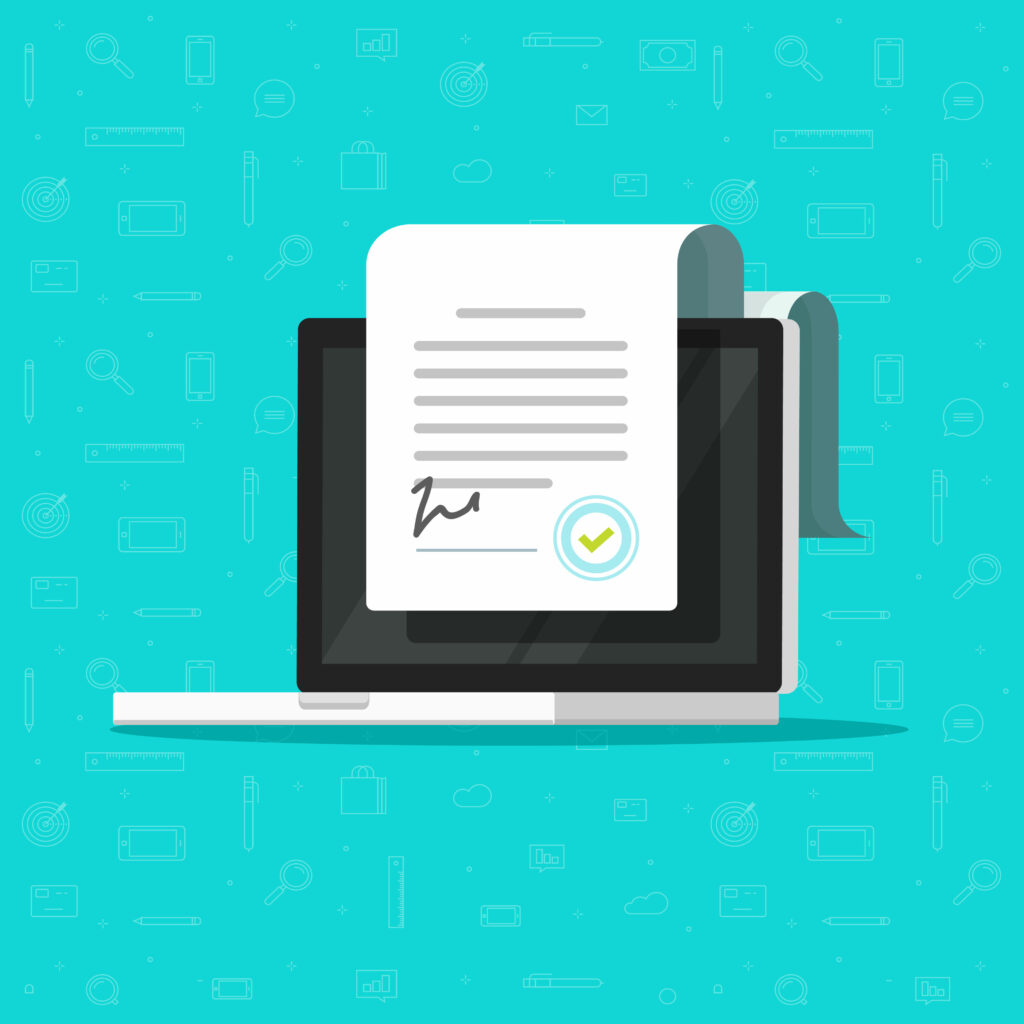
まず気になるのが、
どのような要件を満たせば、グループホームでの個人単位の居宅介護の利用をすることができるのか?
ということではないでしょうか。
令和3年度の報酬改定でも引き続きこのような経過措置を続けることが決まったので本日はその要件についてお伝えいたします。
対象者

グループホームでの個人単位の居宅介護の利用の対象者は次の2パターンに分かれています。
対象者パターン1
- 障害支援区分4以上
かつ - 重度訪問介護/同行援護/行動援護の対象者
対象者パターン2
- 障害支援区分4以上
かつ - 次の A 及び B の要件をいずれも満たす者
B :グループホームでの居宅介護の利用について市町村が必要を認めていること
つまり基本的には障害支援区分の4以上が必要で、ある程度特別な支援を必要とするほどの重度の方ということがわかります。
利用可能サービス

利用可能サービスについても対象者のパターンごとに定められており、
対象者パターン1: 居宅介護または重度訪問介護
対象者パターン2: 居宅介護(※身体介護にかかわるものに限る)
とされています。
注意点としては障害支援区分の4以上の方でも、身体介護に関わる支援を受けないとこの特例は認められないという点です。
報酬

基本的には、普通のグループホーム事業と同じように、障害支援区分や世話人の配置に応じて決まります。
介護サービス包括型
| (世話人配置) | 介護サービス包括型 |
| 4人に1人 | 区分6 444 区分5 398 区分4 364 |
| 5人に1人 | 区分6 393 区分5 346 区分4 314 |
| 6人に1人 | 区分6 359 区分5 313 区分4 281 |
日中サービス支援型
| (世話人配置) | 共同生活住居で過ごす | 共同生活住居で過ごさない |
| 3人に1人 | 区分6 698 区分5 651 区分4 617 | 区分6 605 区分5 558 区分4 525 |
| 4人に1人 | 区分6 612 区分5 566 区分4 533 | 区分6 520 区分5 474 区分4 440 |
| 5人に1人 | 区分6 561 区分5 515 区分4 482 | 区分6 469 区分5 422 区分4 389 |
グループホームでの個人単位の居宅介護の利用の注意点とは?

これまでの説明で、グループホームでの個人単位の居宅介護の利用の要件がわかったと思います。
しかしこのような利用はあくまで特例の経過措置なので、運用には十分な注意が必要です。
そこで気になるのは、
グループホームで個人単位の居宅介護の利用をする時、どのような点に注意すればいいの?
ではないでしょうか。
そこでループホームでの個人単位の居宅介護の利用の注意点についてお伝えいたします。
グループホームの人員配置基準

これまで弊所もグループホームでの個人単位の居宅介護の利用について、多くの相談を受けてきましたが、その中で感じる注意点は、
個人単位で居宅介護を利用する時でも、グループホームに必要なスタッフを配置しているか
という点です。
制度的にはこのような特例措置の間のグループホームでの人員配置基準は、
個人単位での居宅介護等を利用する者の生活支援員の配置基準については、当該利用者数を2分の1として算定
とされています。
ポイントは生活支援員の配置について、その数の計算を通常の2分の1で行う点です。
通常のグループホームにおける生活支援員の配置基準は次のように計算いたします。
そこで特例の基準である「当該利用者数を2分の1として算定」とはどのように考えるのでしょうか?
事例:区分3/2人、区分4/2人、区分5/1人
この事例において、個人単位で居宅介護を利用する方を、
- 区分4の2人と区分5の1人
として考えます。
その場合、
2÷9+1(※2人の2分の1)÷6+0.5(※1人の2分の1)÷4=0.4
となります。
つまり常勤換算にして0.4以上だけ配置していればいいというわけです。
普通の場合では、
2÷9+2÷6+1÷4=0.7
になるので、経過措置の特例を利用する場合は通常より少ない配置でいいというわけです。
しかし「当該利用者数を2分の1として算定」した上での人員配置基準は守ようにしてください。
グループホームでの個人単位の居宅介護の利用の活用事例とは?

グループホームでの個人単位の居宅介護の利用に関する要件や注意点については説明してきました。
加えてそこで気になるのは、
この特別経過措置の活用事例はどのようなものがあるのか?
ではないでしょうか。
例外的な措置とはいえ、認められている期間にこの制度を有効活用して事業基盤を固めることができるならチャンスです。
他の加算との組み合わせ

ポイントは、
グループホームでの個人単位の居宅介護の利用とは主に重度の方が対象である
という点です。
そこでお勧めの活用事例として、
グループホームで利用できる「重度の方向け」の他の加算と組み合わせる
ことが挙げられます。
グループホームで利用できる重度の方向けの加算とは、
・重度障害者支援加算・・・・・・重度の方を支援する専門的な体制がある場合に加算
・強度行動障害者体験利用加算・・重度の方を受け入れる専門的な体制がある場合に加算
があります。
これらの加算が想定する対象者は、ほとんどこの特別な経過措置の利用者と重なるでしょう。
従って支援するスタッフ側に、重度の方支援を行う専門的な体制を築くことができれば、
他の加算も取得することができて支援に手厚い事業携帯を整えること
ができます。
重度訪問介護事業も併せて行う

グループホームでの個人単位の居宅介護の利用で、重度訪問介護などのサービスを受けることができます
この制度を別の見方からすれば、
グループホーム運営法人で重度訪問介護も行う
という選択肢を取ることができます。
つまりグループホーム内で行う介護支援も、同じ法人が管轄する事業でカバーすることができることになります。
そうすると、
・サービスの最適化
・連絡調整作業の円滑化
・監視監督の適正化
という点でも、グループホーム支援と介護事業の連携がスムーズになるのでお勧めしたい活用方法です。
まとめ
近年行政に評価されるグループホームの特徴は、重度の障害の方や高齢者を受け入れ適切な支援ができることです。
そのためにはグループホーム事業において、「個人単位で居宅介護を利用する特例」を活用することは大切です。
ただあくまで特例措置なので適切に運営できているか気をつけていないとトラブルになる可能性があるので注意してください。
・重度障害者支援加算とは?注意点や活用事例あり
・夜間支援等体制加算とは?注意点・活用事例も紹介
戸根行政書士事務所からのお知らせ
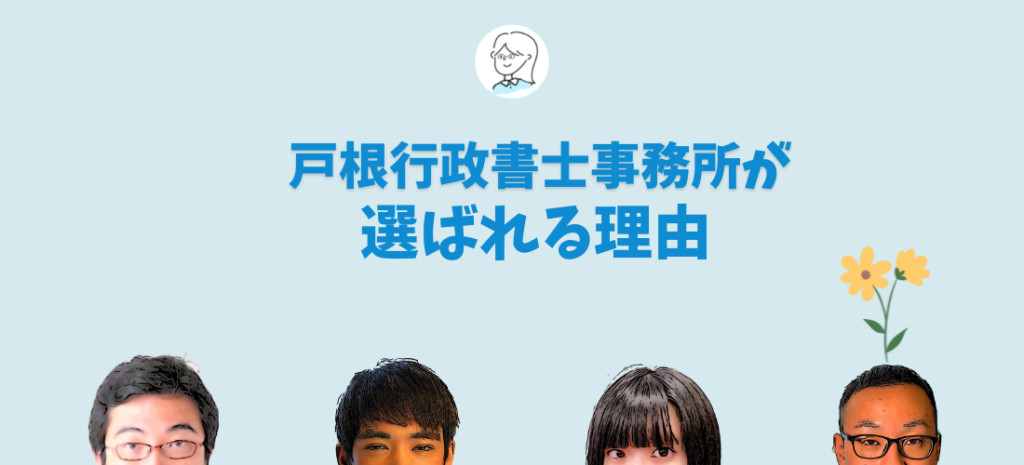
<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ
・【まとめ】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から注意点まで解説
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
<減算について>
・【基本】人員欠如の減算とは?計算方法や注意点も解説
・【詳解】人員欠如の減算:基準や緊急対応・防止策をご説明
・【詳解】サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算とは?
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題点と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
<夜間支援の加算等>
・【基本】夜勤職員加配加算の要件とは?注意点やオススメ活用事例あり
・【基本】重度障害者支援加算とは?注意点や活用事例あり
・【最新版】夜間支援等体制加算とは?注意点・活用事例も紹介
・【注意】グループホームの夜間支援体制のスタッフ配置:注意点も解説
・【要点】「夜間支援等体制加算」の利用者数の計算とは?
<医療/入院関係の加算等>
・【基本】看護職員配置加算とは?要件・活用事例も解説
・【基本】医療連携体制加算とは?要件・注意点・おすすめ活用も解説
・【注意点】個人単位で居宅介護は利用できるの?要件や注意点を説明
・【基本】強度行動障害者体験利用加算とは?取得条件や活用事例も紹介
・【基本】長期入院時支援特別加算とは?基準や注意点を解説
・【基本】入院時支援特別加算とは?基準や注意点を解説
・【基本】医療的ケア対応支援加算とは?加算条件や活用方法も解説
・【基本】「帰宅時支援加算」とは?取得条件や間違えやすいポイントを解説
・【基本】「長期帰宅時支援加算」とは?取得条件や間違えやすい点を解説
・【基本】「地域生活移行個別支援特別加算」とは?取得条件や活用法を解説
<利用者さんとのトラブルを避ける対策>
・【まず知りたい】グループホーム運営は何が難しいの?
・【注意】グループホーム利用者との金銭トラブルについて
・【質問】「通院時も付き合って欲しい」と言われたら?通院支援の対策を解説
・【注意】グループホームの費用設定はどのように?利用者負担も解説
・【基本】グループホーム体験利用の注意点とは?利用者負担の設定に留意
<実地指導のトラブルにならないための対策>
・【まず知りたい】実地指導とは?チェックリストもお教えします
・【直前対策】実地指導を受ける時の対応の注意点!
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【トラブル多発】グループホームの土日祝の支援とは?基本や注意点も解説
・【よく間違える】日中支援加算とは?基準や注意点を解説
・【基本】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から徹底解説
・【注意】生活支援員を外部業者に委託する際の注意点とは?
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【注意】大規模住居等減算とは?あえて減算になるメリットも解説
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】サービス管理責任者を配置する注意点とは?間違いやすい例も解説
・【注目】生活支援員の配置の注意点とは?外部の業務委託も解説
・【基本】勤務体制一覧表の注意点は?間違えやすいシフト例も解説
・【注意】定員増加の注意点とは?報酬額や人員配置の問題解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】障害者グループホームに短期入所を併設して収益を上げる方法とは?
<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり
・【注意】処遇改善加算等の社会保険料の計算の仕方とは?改善額の組み入れ