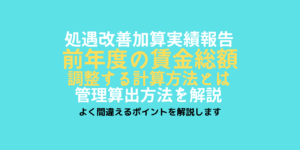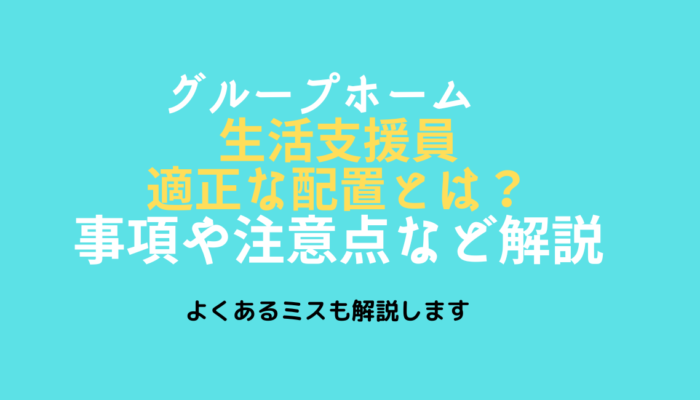
長い間準備をしてきて障がい者を対象とするグループホームを開業することが決まりました。。
サービス管理責任者は前もって確保しているのですが、生活支援員等の人材が中々見つかりません。
障がい者グループホームで生活支援員を配置する際にどのような点に注意すればいいでしょうか?
生活支援員の役割は、利用者さんの入浴や排泄などの生活介護、家事や金銭管理を担うことにあります。
ただ生活支援員の人手不足が問題になっていますが、グループホームの生活支援員は例外的に外部委託を認められています。
この記事ではグループホームの事業者様の理解の一助になるように以下のような内容がわかるように説明いたします。
- 外部へ業務委託できる生活支援員の業務範囲がわかります
- 業務委託できる生活支援員の指示・管理に必要な書式がわかります
- 外部へ業務委託できる生活支援員の損害賠償事故の対策がわかります
<グループホーム事業の人員配置の経営の課題>
グループホームで収益を安定させるにはパート職員を効率よく配置して人件費を抑えることが課題でありますが、非常勤の人員が増えると管理業務の負担も大きくなります。
そんな課題を解決するための一策が、本日お話しする生活支援員業務の外部委託です。
目次
(グループホーム)業務委託の生活支援員の配置の注意点は?
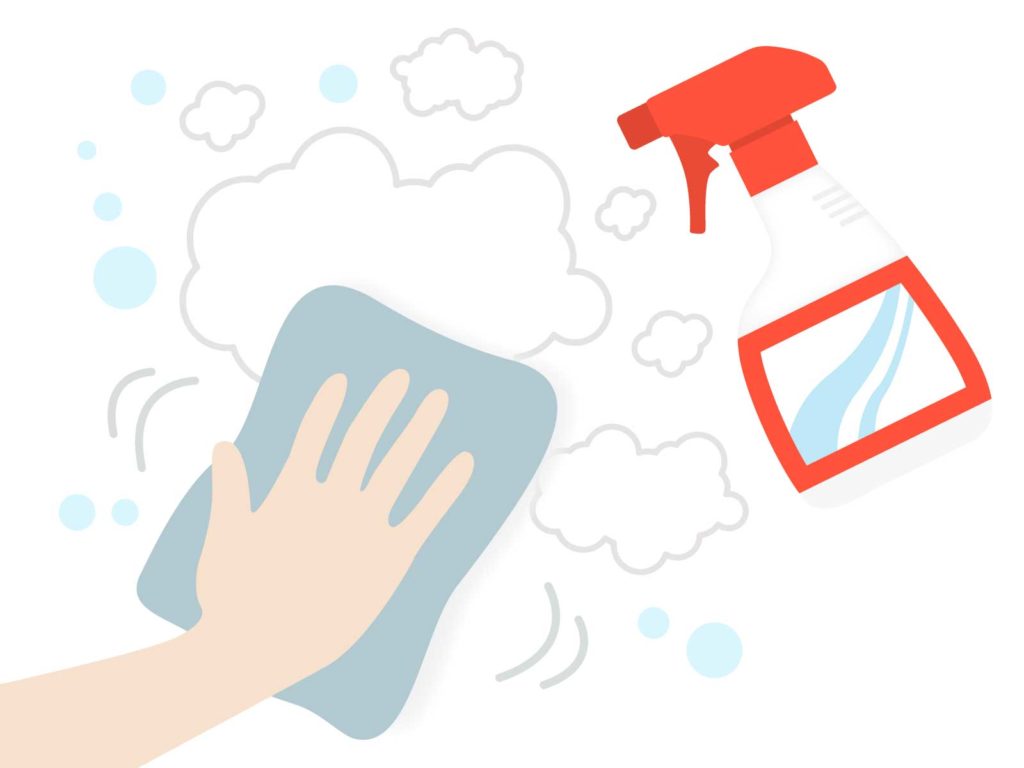
障がい者グループホームは全部で3種類あり、外部サービス利用型以外は利用者さんの障害区分に応じて生活支援員を配置する必要があります。
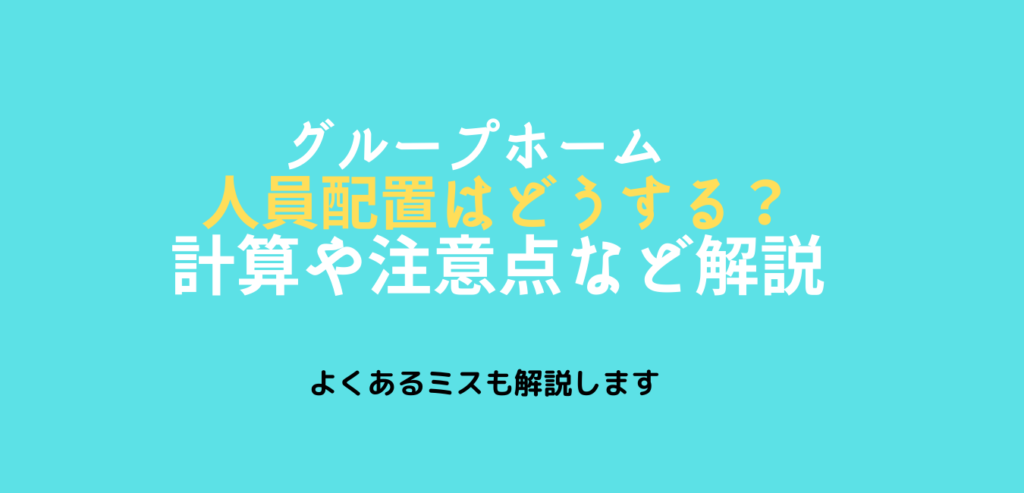
障害者グループホームの「生活支援員」の配置のポイントは、全障害福祉事業でも珍しくこの「生活支援員」だけ業務委託が認められている点です。
殆どの障害福祉サービスの支援員は、外部への業務委託が認められていないのでご注意ください。
<障害福祉サービスの人員の外部委託が一般的に認められない理由>
・業務委託では勤務時間の指定ができない
・業務委託では事業所側の管理と指示が徹底できない可能性がある
・業務委託では事業所側の加入保険のカバーができない
障がい者グループホームの生活支援員は外部への業務委託として可能であることを知って驚きました。
外部へ生活支援員の業務委託をすれば、人手不足の問題も解消しそうなのですが、グループホームの生活支援員の配置の注意点など教えてもらえるでしょうか?
生活支援員を外部委託することは、所得税の計算や年末調整など労務管理の軽減の面でも大きなメリットがあります。
しかし障害福祉サービスの外部への業務委託は一般的には容認されていないので、外部委託の利用の際は注意点をしっかり守必要があります。
それではグループホームの生活支援員の配置の注意点についてしっかり説明したいと思います。
委託できる業務の範囲の限定

障がい者グループホームの事業者は、業務委託する外部のサービス業者に事前に生活支援員の業務の範囲を明確化する必要があります。
※例えば契約書を作成いたします。
<委託業務の範囲の限定のポイント>
・生活支援員の職務以外を指示しない(※警備など)
・生活支援員の職務の一部でも委託できる
・受託した業務の再委託は認められない
外部へ業務委託しても事業者側で一定の管理を行う必要があり、何を外部へ委託しているのかは整理する必要があります。
実地指導の時に業務委託の範囲を限定せず何でも委託していてトラブルになったケースも聞きます。
口頭ではなく文面で業務委託の内容を明示化しておくことをお勧めいたします。
指示書の付与

障がい者グループホームの事業者は、業務委託する外部のサービス業者に事前に生活支援員の業務の指示を書面で行う必要があります。
<外部への業務委託の指示書作成の注意点!>
・利用者さんのアセスメントから個別支援計画の共有を踏まえる
・1週間ごとに作成する
・指示書はサービス管理責任者の確認を得る
外部へ業務委託しても事業者側で業務の統制を行う必要があり、外部の事業者にどのように業務を進めてもらうか指示する必要があります 。
特に利用者さんの個人情報を共有することになるので秘密保持の誓約書は得ておいてください。
外部への業務の指示書は書面で残し、実地指導の時のために分かりやすいところに保管いたしましょう。
定期的な確認

障がい者グループホームの事業者は、外部のサービス業者に業務委託した内容を定期的に確認し、書面で確認記録を残す必要があります。
<外部への業務委託内容の確認のポイント>
・業務委託した内容から逸脱していないか
・事前の指示書通りに支援したか
・人員配置は必要基準を満たしているか
業務委託の確認業務は主に業務日報やサービス提供記録を確認して行います。
確認して不備があると請求業務にも影響が出てくるので、翌月10日の請求前には必ず確認業務を終えてください。
業務委託の確認作業を終えると確認記録として何をどのように確認し、結果はどうであったかを書面で残しておきましょう。
責任の所在の明確化

障がい者グループホームの事業者は、外部に生活支援員の業務委託をしている際に、利用者に「賠償すべき事故」が発生した場合の責任の所在を明確化しておく必要があります。
<責任の所在の明確化のポイント>
・委託している側が責任を負わない内容を明確にする
・事故が起こった際の対処の手順をマニュアル化しておく
・利用者に対して業務委託における責任の所在を事前に説明しておく
委託する側の障害福祉サービス事業所は損害賠償保険に加入しているのが一般的ですが、その保険は業務委託した外部にまで適用されることは殆どありません。
委託された外部事業者が独自で保険に加入していることが望ましいですが、いずれにせよ責任の所在は利用者さんやご家族に対して前もって説明しておく必要があります。
また利用者さんからの苦情は直接事業所の方へ伝えられる仕組みも整えておきましょう。
まとめ
本日は障がい者グループホームの生活支援員の配置のポイントをご説明いただきありがとうございました。勉強になりました。
生活支援員のスタッフが集まらないので、外部への業務委託という方法を教えていただいて経営の不安が少し軽くなりました。
生活支援員の業務を外部に委託しても、指示命令と管理の責任は委託側の事業所にあります。
グループホームの経営はパート職員をいかに効率よく配置して人件費を抑えるかに要点があるので、外部への業務委託は魅力的な方法です。
その他にも所得税の計算や年末調整をしなくてもいい点など管理業務の負担軽減にもつながりますので、生活支援員の外部委託について前向きにご検討ください。
戸根行政書士事務所からのお知らせ
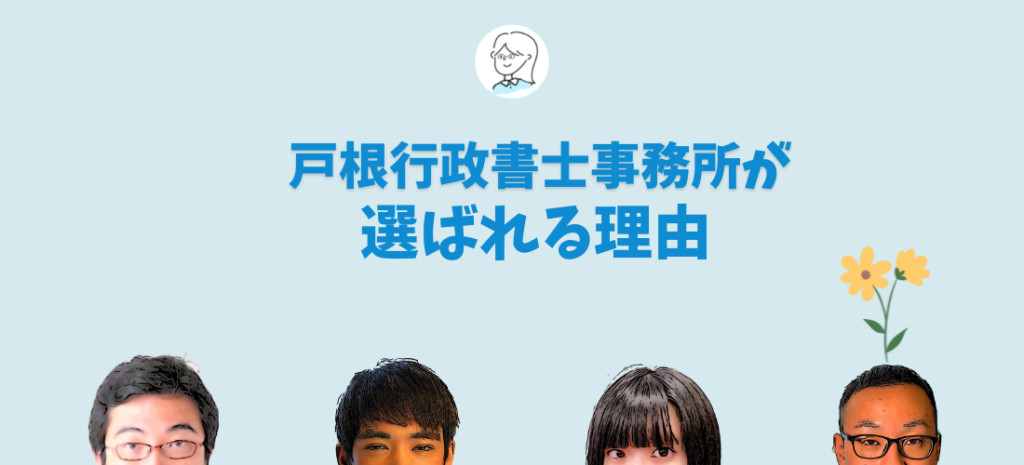
<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ
・【まとめ】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から注意点まで解説
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
<減算について>
・【基本】人員欠如の減算とは?計算方法や注意点も解説
・【詳解】人員欠如の減算:基準や緊急対応・防止策をご説明
・【詳解】サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算とは?
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題点と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
<夜間支援の加算等>
・【基本】夜勤職員加配加算の要件とは?注意点やオススメ活用事例あり
・【基本】重度障害者支援加算とは?注意点や活用事例あり
・【最新版】夜間支援等体制加算とは?注意点・活用事例も紹介
・【注意】グループホームの夜間支援体制のスタッフ配置:注意点も解説
・【要点】「夜間支援等体制加算」の利用者数の計算とは?
<医療/入院関係の加算等>
・【基本】看護職員配置加算とは?要件・活用事例も解説
・【基本】医療連携体制加算とは?要件・注意点・おすすめ活用も解説
・【注意点】個人単位で居宅介護は利用できるの?要件や注意点を説明
・【基本】強度行動障害者体験利用加算とは?取得条件や活用事例も紹介
・【基本】長期入院時支援特別加算とは?基準や注意点を解説
・【基本】入院時支援特別加算とは?基準や注意点を解説
・【基本】医療的ケア対応支援加算とは?加算条件や活用方法も解説
・【基本】「帰宅時支援加算」とは?取得条件や間違えやすいポイントを解説
・【基本】「長期帰宅時支援加算」とは?取得条件や間違えやすい点を解説
・【基本】「地域生活移行個別支援特別加算」とは?取得条件や活用法を解説
<利用者さんとのトラブルを避ける対策>
・【まず知りたい】グループホーム運営は何が難しいの?
・【注意】グループホーム利用者との金銭トラブルについて
・【質問】「通院時も付き合って欲しい」と言われたら?通院支援の対策を解説
・【注意】グループホームの費用設定はどのように?利用者負担も解説
・【基本】グループホーム体験利用の注意点とは?利用者負担の設定に留意
<実地指導のトラブルにならないための対策>
・【まず知りたい】実地指導とは?チェックリストもお教えします
・【直前対策】実地指導を受ける時の対応の注意点!
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【トラブル多発】グループホームの土日祝の支援とは?基本や注意点も解説
・【よく間違える】日中支援加算とは?基準や注意点を解説
・【基本】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から徹底解説
・【注意】生活支援員を外部業者に委託する際の注意点とは?
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【注意】大規模住居等減算とは?あえて減算になるメリットも解説
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】サービス管理責任者を配置する注意点とは?間違いやすい例も解説
・【注目】生活支援員の配置の注意点とは?外部の業務委託も解説
・【基本】勤務体制一覧表の注意点は?間違えやすいシフト例も解説
・【注意】定員増加の注意点とは?報酬額や人員配置の問題解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】障害者グループホームに短期入所を併設して収益を上げる方法とは?
<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり
・【注意】処遇改善加算等の社会保険料の計算の仕方とは?改善額の組み入れ